「蘇るザビエル聖堂」
7月 22nd, 2013土田 充義(鹿児島大学名誉教授) 『致知』2013年8月号 致知随想よりフランシスコ・ザビエル上陸の地、鹿児島。 一九九八年一月十一日、その中心部にあるザビエル記念聖堂で 「感謝のミサ」が執り行われました。 ザビエル渡来を記念して、 一九〇八年に建てられた石造り聖堂は 太平洋戦争で焼失。 その後、一九四九年の渡来四百年祭に合わせ、 木造聖堂として再建されるのです。 しかし、五十年にわたって人々を見守り続けてきた 木造聖堂も、老朽化のため建て替えられることに なったのでした。 感謝のミサは同時に「お別れのミサ」でもあったのです。 文化財修復を専門とする私は、 木造聖堂の建築的価値をよく理解していました。 天井を高くするトラス工法などは、 同時代の教会には見られない独自の構造でした。 建て替えに向けた話が進む中、 地元の市民や信徒の方々からは 旧聖堂を残したいとの声が上がっていたものの、 私は新聖堂建築の建設委員でもあり、 資金面から旧聖堂の保存・移築までは 言い出すことができないでいたのです。 私の活動の原点には、学生時代に洗礼を受けた カトリックの信仰があるのだと思います。 「人間を大切にする」という教えが、 先人から受け継いできた文化を 守っていきたいという想いに繋がっているのでしょう。 また、伝統的建造物が次々と破壊されていく高度成長期に、 「古いもの」の修復に黙々と取り組んでいた 恩師の姿も忘れられません。 「長い間存在してきた建築物を無駄に壊してはいけない。 せめて壊す前にお別れの挨拶をするとか、 なんらかの形に留めることが人間として大事なことなのだよ」 文化財修復には外観のみならず、 それを造った先達に想いを馳せ、 創意工夫の意味を損なわないことが 大切なのだと教わったのでした。 ただ、それまでの私は、 学者の立場からの見解は述べても、 自ら資金などを工面し文化財を守る ということはありませんでした。 しかし、消えゆくザビエル聖堂を前にして、 人を頼むばかりであっては 無責任ではないのかとの想いが湧いてきたのです。 一九九七年秋、六十歳を迎えた私は、有志とともに 「ザビエル聖堂を文化財として再生させる会」を結成。 翌一月、解体しながら調査を行う許可を得て、 聖堂内部へと入りました。 そこで私たちが目にしたのは、 昭和二十四年当時の最先端技術を駆使した 職人たちによる第一級の仕事だったのです。 特に漆喰仕上げなどの施工技術の美しさには 思わず目を奪われました。 この技術を次世代に伝えなければならない――。 調査を経て、私の心は完全に移築再生へと傾いたのでした。 再生へと動き出した時、 ある知人からこう言われたのを思い出します。 「再生なんて無謀だよ。結局自分が苦しむだけだよ」 と。事実、移築予定先の福祉施設に解体した部材を 運んだものの、理事長の突然の交代で計画は白紙に。 資金も人手も、無いもの尽くしの出発となったのでした。 しかし、懸念された事業資金は、 知人六百人に寄付を募る手紙とその取り組みをまとめた 『聖堂再生』を送り、さらに私自身の大学の退職金の 半分を注ぎ込み工面。 これにより欲得抜きで聖堂再生に懸けている想いが 周囲に伝わったのかもしれません。 市民の方たちが手伝いに来てくれるようになり、 方々から大きな寄付が集まり始めたのでした。 移築先についても、思いがけないことが起こりました。 事情を知った福岡県宗像市にある修道院の神父様から 「私たちの敷地に建ててはどうか」と申し出があったのです。 ////////////////////////////////////////////////// まほろばブログに土田先生のことが書かれています。
驚きの数珠繋がり
「森下自然医学7月号」に連載の「北の空から」の 『六段の調べと再生』を読まれて、…
投稿: まほろばblog on2011年07月09日 20:04
ザビエル記念大聖堂
昨日、レジナ(?鰍フ土田社長から連絡が入り、 お父様が再建中の「ザビエル記念大…
https://www.mahoroba-jp.net/newblog/?s=%E5%9C%9F%E7%94%B0+%E5%85%85%E7%BE%A9

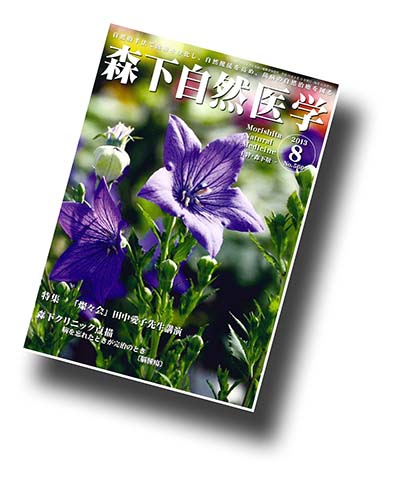
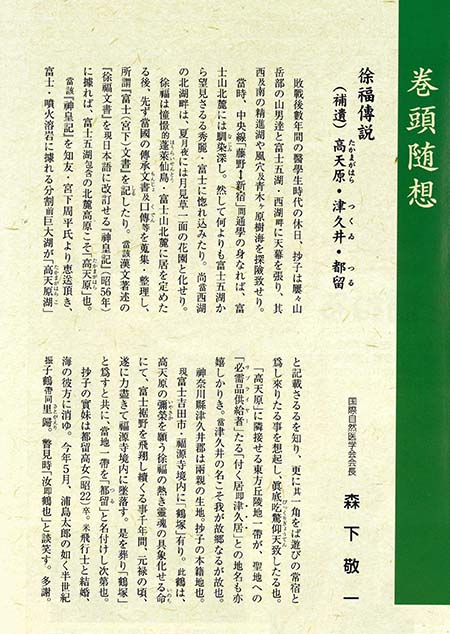
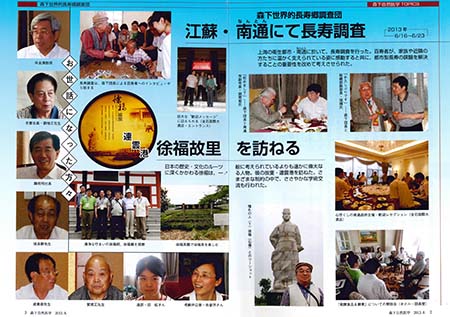
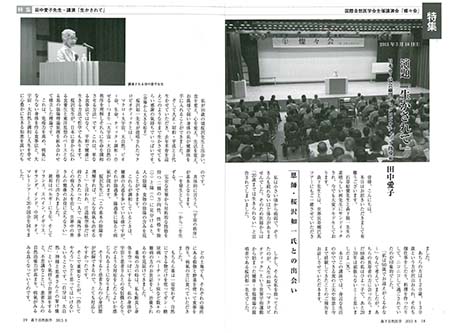

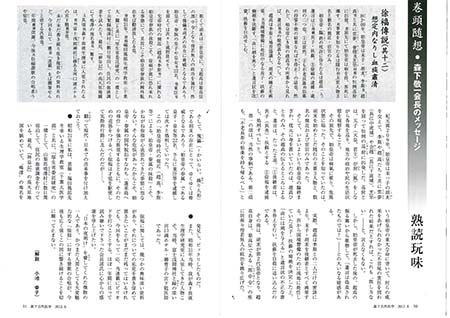
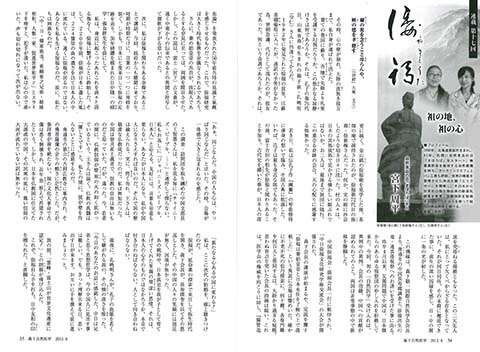
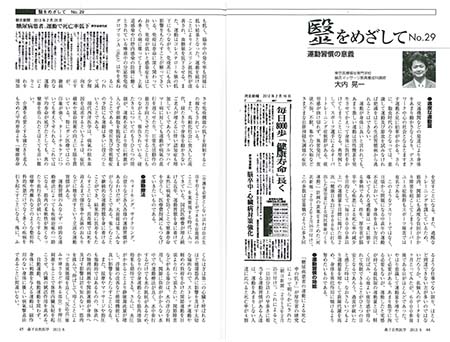
 【記者:小さい頃にご両親から特訓を受けられたと
おっしゃっていましたが、
どのようなことをなさっていたのですか?】
皆さんもなんで手で食事をするのって
急に言われると困るじゃないですか。
それと同じように私も唯一あったこの三本の指で、
ごく自然と周りのものを触ったり、掴んだりしていたようです。
それを見た母が、
「あれ? もしかしたら足でいろいろできるんじゃないか」
と思ったらしく、積み木やおもちゃで遊ばせたり、
フォークやスプーンを持たせてくれたんです。
三歳の時、あゆみ学園という
肢体不自由児施設に一年間だけ通っていたのですが、
そこで着替えの練習をしていた記憶があります。
これは私の中で一番嫌な訓練でしたね。
フックのついた柱が二本あって、
その間にパンツやTシャツをかけておくんです。
そこをお尻で移動して、脱いだり穿いたりする
練習をしたんですけど、なかなか上手くいかない。
私が「できない」って言うと、
母は「やってみなきゃ分からない」と。
ところが、何回やってもできないわけですよ。
それで段々嫌になってしまったんです。
ただ、どんなに弱音を吐いても、
「いや、大丈夫。もう一回やりなさい。有美ならできるから」
と言って、母はとにかくやめさせてくれませんでした(笑)。
そうやって毎日、毎日、言われるがままにやっていたら
ある日、Tシャツを着ることができました。
その時、母に
「ほらね。やっぱり有美はできるんだよ」
って言われたのが凄く嬉しくて、
そこからどんどんチャレンジ精神が出てきました。
そのうち道具を使わずに、足でTシャツの裾を引っ張って
着脱したりと、自分でいろいろ考えていけるようになりました。
私は、他人と同じ方法ではできません。
ピアノを弾いたり、字を書いたり、
裁縫とかも自分なりに工夫してできるようになりました。
それから、小学校三年生の時に水泳で
二十五メートル泳ぎたいって思ったんです。
一般学校に通っていたので、私以外はみんな手足があって、
普通に泳いでいました。
それを見て、私もみんなのように泳ぎたいなと。
そしたら父が協力してくれて、
どうやったら泳げるか一緒に考えてくれました。
そして辿り着いたのが有美泳ぎ(笑)。
バタフライのように体全体をうねらせるんです。
息継ぎする時はクルンと仰向けになって、
またクルンと戻る。
それなら泳げるんじゃないかということで、
地元の市民プールで父と特訓を始めました。
ところが、何度も溺れるんですよ。
それで水が怖くなってしまって、やっぱり私には無理だと。
でも、その時に父が
「ここで諦めていいのか?
さっき一人で五メートル泳げただろ。まだ行けるぞ」
って励ましてくれたんです。
「そっか、私の目標は二十五メートルだ。
諦めるわけにはいかない」
と思い直して、頑張って練習を重ねて、
遂に二十五メートルを泳ぐことができたんですよ。
そしたら父が
「学校でも泳いでみろ。もっといけると思うよ」
と。それで先生に
「限界まで泳がせてください」とお願いして、
クラスの皆に見守られながら泳ぎました。
ターンの際は、片足を水中で回し、
体を半回転させて短い足で壁を精いっぱい蹴る。
そして、顔を上げた瞬間、もう先生も友達も大拍手。
気づいたら百メートルも泳いでいたんです。
あの時の達成感はもう本当に忘れられません。
いま振り返ると、初めて心の底から
諦めないでよかったって思えた瞬間だったと思います。
●
【記者:小さい頃にご両親から特訓を受けられたと
おっしゃっていましたが、
どのようなことをなさっていたのですか?】
皆さんもなんで手で食事をするのって
急に言われると困るじゃないですか。
それと同じように私も唯一あったこの三本の指で、
ごく自然と周りのものを触ったり、掴んだりしていたようです。
それを見た母が、
「あれ? もしかしたら足でいろいろできるんじゃないか」
と思ったらしく、積み木やおもちゃで遊ばせたり、
フォークやスプーンを持たせてくれたんです。
三歳の時、あゆみ学園という
肢体不自由児施設に一年間だけ通っていたのですが、
そこで着替えの練習をしていた記憶があります。
これは私の中で一番嫌な訓練でしたね。
フックのついた柱が二本あって、
その間にパンツやTシャツをかけておくんです。
そこをお尻で移動して、脱いだり穿いたりする
練習をしたんですけど、なかなか上手くいかない。
私が「できない」って言うと、
母は「やってみなきゃ分からない」と。
ところが、何回やってもできないわけですよ。
それで段々嫌になってしまったんです。
ただ、どんなに弱音を吐いても、
「いや、大丈夫。もう一回やりなさい。有美ならできるから」
と言って、母はとにかくやめさせてくれませんでした(笑)。
そうやって毎日、毎日、言われるがままにやっていたら
ある日、Tシャツを着ることができました。
その時、母に
「ほらね。やっぱり有美はできるんだよ」
って言われたのが凄く嬉しくて、
そこからどんどんチャレンジ精神が出てきました。
そのうち道具を使わずに、足でTシャツの裾を引っ張って
着脱したりと、自分でいろいろ考えていけるようになりました。
私は、他人と同じ方法ではできません。
ピアノを弾いたり、字を書いたり、
裁縫とかも自分なりに工夫してできるようになりました。
それから、小学校三年生の時に水泳で
二十五メートル泳ぎたいって思ったんです。
一般学校に通っていたので、私以外はみんな手足があって、
普通に泳いでいました。
それを見て、私もみんなのように泳ぎたいなと。
そしたら父が協力してくれて、
どうやったら泳げるか一緒に考えてくれました。
そして辿り着いたのが有美泳ぎ(笑)。
バタフライのように体全体をうねらせるんです。
息継ぎする時はクルンと仰向けになって、
またクルンと戻る。
それなら泳げるんじゃないかということで、
地元の市民プールで父と特訓を始めました。
ところが、何度も溺れるんですよ。
それで水が怖くなってしまって、やっぱり私には無理だと。
でも、その時に父が
「ここで諦めていいのか?
さっき一人で五メートル泳げただろ。まだ行けるぞ」
って励ましてくれたんです。
「そっか、私の目標は二十五メートルだ。
諦めるわけにはいかない」
と思い直して、頑張って練習を重ねて、
遂に二十五メートルを泳ぐことができたんですよ。
そしたら父が
「学校でも泳いでみろ。もっといけると思うよ」
と。それで先生に
「限界まで泳がせてください」とお願いして、
クラスの皆に見守られながら泳ぎました。
ターンの際は、片足を水中で回し、
体を半回転させて短い足で壁を精いっぱい蹴る。
そして、顔を上げた瞬間、もう先生も友達も大拍手。
気づいたら百メートルも泳いでいたんです。
あの時の達成感はもう本当に忘れられません。
いま振り返ると、初めて心の底から
諦めないでよかったって思えた瞬間だったと思います。
●






