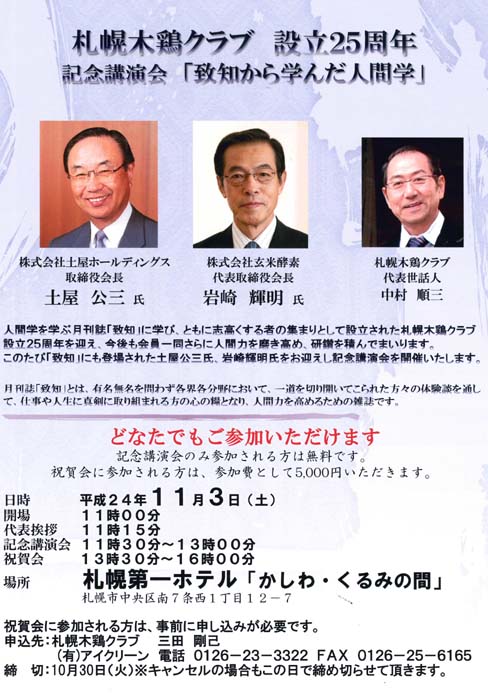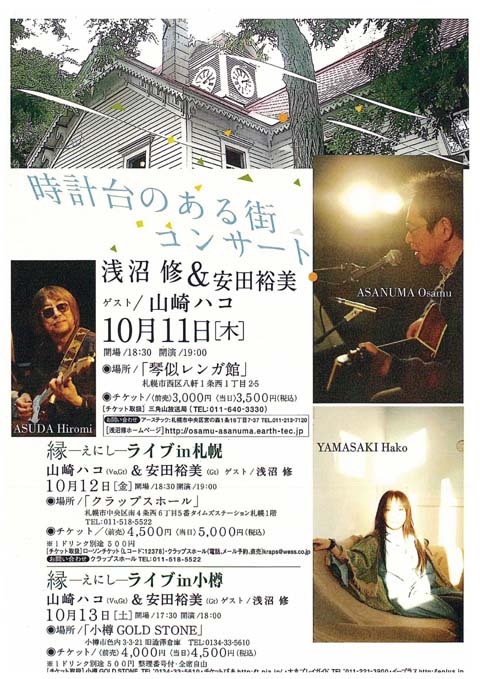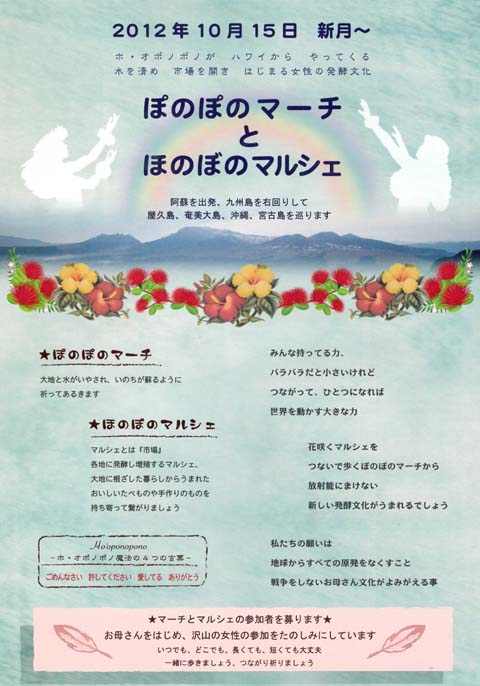杉浦貞(プロ街頭紙芝居師)
『致知』2012年10月号
致知随想より
└─────────────────────────────────┘
まだ誰もいない公園を背に、
よく音のとおる拍子木を打ちながら街を回る。
二十分もすれば、子供たちが公園に集まり出す。
子供たちが自らの感覚で小さい子は前、
大きい子は後ろの順で座りだせば、
いよいよ街頭紙芝居の始まりだ。
街頭紙芝居は、マンガ一巻、続き物の物語一巻、
最後にとんちクイズ十問が出て、
正解者は水飴券がもらえるという決まりで行われる。
もっとも紙芝居はただ子供たちを喜ばせればよいと
いうものではない。
例えば水飴券は一週間後にしか使えないため、
その間子供たちには我慢することを教えている。
また、クイズでの「ハイ」の返事は、
私の目を見てしないとやり直しをさせている。
元気な返事が子供たちの自立心を育て、
友達関係を良好に築く原点となるのだ。
私はプロの街頭紙芝居師としてこの道三十二年、
毎週十二か所以上、年間六百回以上紙芝居を
上演することを生活のためのノルマとしてきた。
しかも駄菓子の値段を三十二年間、
一度も値上げすることなく一律五十円を守り続けているのだ。
だが最盛期だった昭和三十年代に
紙芝居師が全国に五万人いたのもいまは昔。
現在、紙芝居で生計を立てているプロの街頭紙芝居師は
八十一歳になる私一人のみだが、
二百年の歴史を持つ紙芝居という、
日本独自の文化を担っているという気負いはない。
むしろいまの仕事は我が天分であり、
楽しくてやめられないというのが本音だ。
初めて街頭紙芝居を見たのは二十歳の時だった。
石川県羽咋市という田舎から身一つで大阪に出てきた私は、
その日も日雇いの仕事を終え、
大道芸が並ぶ盛り場をあてもなく歩いていた。
ふと広場の片隅に年配の老人が子供や婦人たちを集めて
何かをしているのに気がついた。
聞けば紙芝居屋といって、いっぱしの職業だという。
肉体労働だけが生きる道だと考えていた自分には、
口先一つで生活ができると知った時の
驚きと感動はいまも忘れられない。
紙芝居師を志したのは勤めていた会社が
倒産する一年前、四十八歳の時だった。
すでに紙芝居師は街からほとんど姿を消していたが、
かつて二十歳の時に大阪で偶然出会っていた
紙芝居への潜在意識に火がついたのだ。
最初は祝祭日に知人から道具一式を借り、
家から遠く離れた公園で見よう見まねで上演した。
当時紙芝居師は乞食の一つ上と蔑視され、
家族は私が近所で紙芝居を演ずることを嫌がったからだ。
そんな最中に会社が倒産。
過去二度倒産の憂き目を味わった私にとって
新たな職探しは気が重く、
その反動からかますます紙芝居にのめり込んだ。
だが失業保険が切れる頃になると、
家族の強い反対もあって焦りが募り、
職探しで紙芝居を一週間ほど休んだことがあった。
すると街で私を見つけた子供たちが
しきりに紙芝居をせがんでくる。
いつの間にか、子供たちとの間に仲間意識が芽生えていたのだ。
私の紙芝居を待つ子供たちがいる――。
この瞬間、腹が決まった。
「明日必ず行くから待っとれ!」。
紙芝居屋として生きていこうという
強烈な人生の決断が生まれたのだ。
しかし現実は厳しい。
私の収入が減ったため、妻はパートに、
そして子供二人は高校生になると
バイトに出ざるを得なくなった。
将来への不安が常につきまとい、
それまでの温かい家庭の雰囲気は消え、
殺伐とした空気が漂うようになった。
さらに追い討ちをかけるように、
紙芝居に子供が集まらなくなってきた。
いま思えば紙芝居がマンネリ化していたのだが、
それでも雨さえ降らなければ
毎日、毎日公園へと夢中で出掛けていった。
一月下旬、その日は朝から雪だったが、
午後から急に晴れ間が差すとすぐに街中へ飛び出す。
しかし、目指す市営団地の広場には
雪が積もり誰も集まらない。
いたたまれない気持ちでその場を去ろうとした時、
一人の女の子が自転車置き場の隅からそっと現れた。
私の顔をじっと見つめ、
「おっちゃん、水飴ちょうだい」
と百円玉を差し出してきた。
私は自分が惨めでしょうがなかったが
しぶしぶ水飴をつくった。
そしてもう一本水飴を求めたその子に
「おっちゃん、ご飯食べられるんか」と言われた時には、
私のさもしい心が見透かされてしまったように感じ、
逃げるようにその場を後にした。
その子のことが頭から離れぬままに
十日ほど過ぎただろうか。
ふと自分は心のどこかで子供たち相手の商売を
馬鹿にしていたことに気がついた。
お菓子を買ってくれるのは大人ではなく子供たちなのだ。
自分たちの仲間だと思って対等な気持ちで
水飴を買ってくれる子供たちは、
私の生活の神様なのだ。
そう閃いた瞬間、心が晴れ晴れとして気持ちが
どんどん前向きになるのを感じた。
そして子供たちが喜んでくれることだけを
四六時中考え続けるようになって、
俄然紙芝居が面白くなってきた。
それからは「村田兆治物語」など
意欲的に新しい紙芝居の題材にも取り組んだ。
今年二月には新作「応答せよはやぶさ」を持って、
毎月一週間、東北三県の復興支援ボランティア紙芝居を実践し、
老人や子供たちに諦めない心の大切さと
生きる勇気や感動を伝えている。
きょうも街のいつもの広場や公園で
拍子木を合図に私の紙芝居が始まる。
辛いことは幾度もあったが、
紙芝居師としての自負心や楽しさと、
溢れる感性を武器にその時その時の道を切り開いてきた。
プロ紙芝居師とは、子供たちとの友情を創造し、
深め合える神聖な職業だ。
そして仕事を通じて人格を磨き高め、
紙芝居道の確立に命を燃やすことが私の生きる道なのである。