滝本さんの農法
8月 13th, 2013春に出荷される赤井川の滝本農園のアスパラ。
その苦心の跡を偲ばせる農法の苦労を語った報告書。
是非読まれて、来年の全国発送にご使命ください。

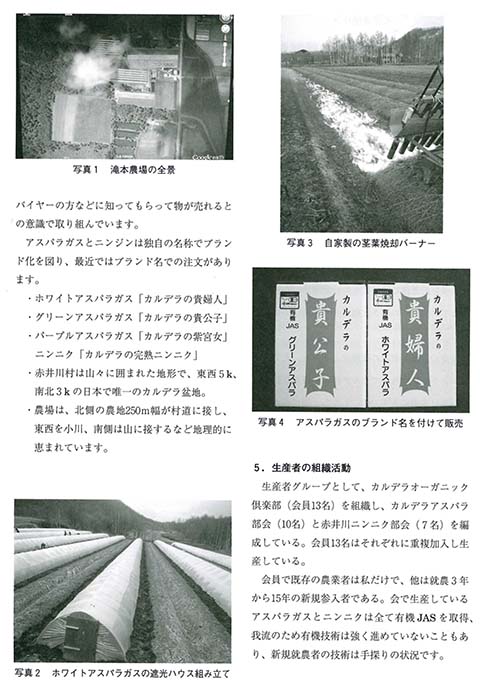
春に出荷される赤井川の滝本農園のアスパラ。
その苦心の跡を偲ばせる農法の苦労を語った報告書。
是非読まれて、来年の全国発送にご使命ください。

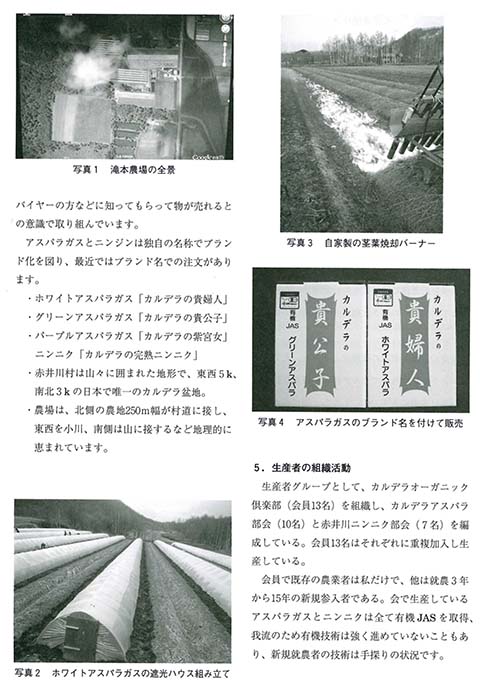
奥野 博(オークスグループ会長) 『致知』1998年8月号 特集「命の呼応」より【記者:昭和42年、40歳のときに経験された倒産が、 今日の奥野会長の土台になっているようですね】 倒産が土台とは、 自分の至らなさをさらけ出すようなものですが、 認めないわけにはいきません。 戦後軍隊から復員し、商社勤務などを経て、 兄弟親戚に金を出してもらい、 事業を興したのは30歳のときでした。 室内設計の会社です。 仕事は順風満帆でした。 私は全国展開を考えて飛び回っていました。 だが、いつか有頂天になっていたのですね。 足元に忍び寄っている破綻に気づかずにいたのです。 それが一挙に口を開いて。 【記者:倒産の原因は?】 「滅びる者は、滅びるようにして滅びる」 これは今度出した本の書き出しの一行です。 倒産の原因はいろいろありますが、 つまるところはこれに尽きるというのが実感です。 私が滅びるような生き方をしていたのです。 出資者、債権者、取引先、従業員と、 倒産が社会に及ぼす迷惑は大きい。 倒産は経営に携わる者の最大の悪です。 世間に顔向けができず、私は妻がやっている 美容院の2階に閉じこもり、 なぜこういうことになったのか、考え続けました。 すると、浮かんでくるのは、 あいつがもう少し金を貸してくれたら、 あの取引先が手形の期日を延ばしてくれたら、 あの部長がヘマをやりやがって、 あの下請けが不渡りを出しやがって、 といった恨みつらみばかり。 つまり、私はすべてを他人のせいにして、 自分で引き受けようとしない 生き方をしていたのです。 だが、人間の迷妄の深さは底知れませんね。 そこにこそ倒産の真因があるのに、 気づこうとしない。 築き上げた社会的地位、評価、人格が倒産によって 全否定された悔しさがこみあげてくる。 すると、他人への恨みつらみで 血管がはち切れそうになる。 その渦のなかで堂々めぐりを繰り返す毎日でした。 【記者:しかし、会長はその堂々めぐりの渦から抜け出されましたね】 いや、何かのきっかけで一気に目覚めたのなら、 悟りと言えるのでしょうが、凡夫の悲しさで、 徐々に這い出すしかありませんでした。 【記者:徐々にしろ、這い出すきっかけとなったものは何ですか?】 やはり母親の言葉ですね。 父は私が幼いころに死んだのですが、 その33回忌法要の案内を受けたのは、 奈落の底に沈んでいるときでした。 倒産後、実家には顔を出さずにいたのですが、 法事では行かないわけにいかない。 行きました。 案の定、しらじらとした空気が寄せてきました。 無理もありません。 そこにいる兄弟や親族は、 私の頼みに応じて金を用立て、 迷惑を被った人ばかりなのですから。 【記者:針の莚(むしろ)ですね】 視線に耐えて隅のほうで小さくなっていたのですが、 とうとう母のいる仏間に逃げ出してしまいました。 【記者:そのとき、お母さんはおいくつでした?】 84歳です。 母が「いまどうしているのか」と聞くので、 「これから絶対失敗しないように、 なんで失敗したのか徹底的に考えているところなんだ」 と答えました。 すると、母が言うのです。 「そんなこと、考えんでもわかる」 私は聞き返しました。 「何がわかるんだ」 「聞きたいか」 「聞きたい」 「なら、正座せっしゃい」 威厳に満ちた迫力のある声でした。 (八十四歳のお母さんが) 「倒産したのは会社に愛情がなかったからだ」 と母は言います。 心外でした。 自分のつくった会社です。 だれよりも愛情を持っていたつもりです。 母は言いました。 「あんたはみんなにお金を用立ててもらって、 やすやすと会社をつくった。 やすやすとできたものに愛情など持てるわけがない。 母親が子どもを産むには、死ぬほどの苦しみがある。 だから、子どもが可愛いのだ。 あんたは逆子で、私を一番苦しめた。 だから、あんたが一番可愛い」 母の目に涙が溢れていました。 「あんたは逆子で、私を一番苦しめた。 だから、あんたが一番可愛い」 母の言葉が胸に響きました。 母は私の失態を自分のことのように引き受けて、 私に身を寄せて悩み苦しんでくれる。 愛情とはどういうものかが、痛いようにしみてきました。 このような愛情を私は会社に抱いていただろうか。 いやなこと、苦しいことはすべて人のせいにしていた 自分の姿が浮き彫りになってくるようでした。 「わかった。お袋、俺が悪かった」 私は両手をつきました。 ついた両手の間に涙がぽとぽととこぼれ落ちました。 涙を流すなんて、何年ぶりだったでしょうか。 あの涙は自分というものに 気づかせてくれるきっかけでした。

今年も「wine & music 芸森ハーベスト」開催します! 好評につき、今年は 2days で実施! おとなの音楽収穫祭を自然溢れる環境で、ゆっくり味わいませんか? 昨年の様子はこちら
2013年 9月21日(土)、22日(日) ☆21日 open start 11:00 close 21:00予定 ☆22日 open start 11:00 close 18:00予定
芸森スタジオ(札幌市南区芸術の森3丁目915-20)
◯前売券¥5,000(税込 ¥1,000分の買い物チケット付) ◯当日券¥5,500(税込 ¥1,000分の買い物チケット付) ◯2日間通し券¥9,000(税込 ¥2,000分の買い物チケット付) ※中学生以下無料 ※臨時バス随時運行:真駒内駅〜芸森スタジオ間 片道 ¥500 ※臨時バス随時運行:真駒内駅〜芸森スタジオ間 片道¥500 時間帯等詳細は追って発表します ※大型無料駐車場有り
2013年 8月10日(土)
ローソンチケット Lコード 16455、チケットぴあ Pコード 209-846、e+、大丸プレイガイド、芸森スタジオにて発売
2013年 9月21日 大貫妙子 with 小倉博和 & 林立夫、MITCH、and more! 2013年 9月22日 大貫妙子 with 小倉博和 & 林立夫、福居良、MITCH、山木将平、and more!
【大貫妙子 with 小倉博和 & 林立夫】

1973年、山下達郎らとシュガー・ベイブを結成。75年に日本初の都会的ポップスの名盤『ソングス』をリリースするも76年解散。日本のポップ・ミュージックにおける女性シンガー&ソング・ライターの草分けのひとり。その独自の美意識に基づく繊細な音楽世界、飾らない透明な歌声で、多くの人を魅了している。CM・映画音楽関連も多く、映画「Shall weダンス?」(監督:周防正行 96年)のメイン・テーマや、映画「東京日和」の音楽プロデュース(監督:竹中直人 第21回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞)、映画「人間失格」劇中歌「アヴェ・マリア」(歌唱)や映画「マザーウォーター」主題歌(作詞・作曲・歌唱)など数多く手がけている。南極も含む 6大陸を旅した経験や、日々の暮らしの視点から、環境、エネルギー、食料などの問題についての発言も多く、農作業や、東洋医学に基づく健康管理を実践するという行動派でもある。今年デビュー40年の記念の年を迎え、エッセイ集の出版や、さまざまなライブ出演が予定されている。大貫妙子ホームページ
1960年香川県高松市生まれ。1982年ビデオの音楽、コマーシャルなどに楽曲を提供。プロとしての活動を始める。1990年桑田佳祐に才能を見いだされ「稲村ジェーン」音楽に参加。1994年桑田佳祐ソロアルバム「孤独の太陽」で全編にわたりサポートをする。その年の日本レコード大賞においてシングル「月」で日本レコード大賞・優秀賞を受賞、『孤独の太陽』でアルバム大賞を受賞した。1998年佐橋佳幸とのギター・デュオ 山弦 1st アルバム「JOY RIDE」リリース。JAPANESE FUSION SELCTION ベスト・レコード賞を受賞。これまでに 5枚のオリジナル・アルバムそしてLIVE DVD、アナログボックスをリリースしている。2005年小林武史、Mr.Children の櫻井和寿を中心に結成された Bank Band のメンバーとして、毎年静岡県つま恋にて開催される「ap bank fes」に参加。桑田佳祐、大貫妙子、福山雅治、槇原敬之など数多くのアーティストからの信望も厚く、スタジオ・ミュージシャン、作・編曲家・プロデューサーとして活躍する傍ら、近年では、ナチュラルハイ等、多くのフェスに単身参加し、観客を魅了するなど活動の場を広げている。
1951年5月21日生まれ。東京都出身。AB型。1972年、細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆とキャラメルママを結成。のちにティンパンアレーと名を改め、ユーミン、吉田美奈子、いしだあゆみ他数多くのアルバムをプロデュース。70年代半ばに大村憲司、村上秀一、小原礼らとバンブーを結成。その後パラシュート、アラゴンなどバンド活動と共にスタジオミュージシャンとして数千曲のセッションに参加。2000年に細野晴臣、鈴木茂と Tin Pan を結成、アルバムリリース。 現在は、札幌でライフスタイルイベント『ttc』を主催する他、大貫妙子、小坂忠らとライブを楽しんでいる。
【MITCH】
13才よりトランペットを始める。 宮村聡、奥田章三、河村直樹 各氏に師事。1993年大阪音楽大学在学中に BLACK BOTTOM BRASS BAND を結成。1996年にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。 国内外の様々なアーティストとの共演、ツアー、レコーディングに参加。 MITCH個人では1996年~2000年までKBS京都、FM-COCOLO、FM滋賀でラジオのDJとしても活躍する。2000年、BLACK BOTTOM BRASS BANDを脱退し、単身New Orleansへ渡る。現地ではTREME地区(6th ward)を拠点にセカンドラインパレード、ブロックパーティー、Tuba Fatsとのストリートライブに日々参加し、地元のコミュニティーに深く溶け込んだ生活を送る。 Newbirth Brass Band, Lil’Rascals Brass Band, Russell Batiste Band, All Thatなど、各バンドのレギュラーメンバーとしてクラブ、ツアー、セカンドライン、葬式、ジャズフェスティバル等で演奏。Ghetto の黒人社会の中で様々な経験を積み、音楽の幅を広げ、タフさを身に付けた。2000年以降、1年の半分は New Orleans で生活する。2002年 初ソロアルバム「MITCH」をリリース。2003年 京都市芸術文化特別奨励者に選ばれる。2004年春、公開の映画「この世の外へ~クラブ進駐軍」(阪本順治監督)では萩原聖人、オダギリジョー、村上淳、松岡俊介らとともに主演グループの1人に抜擢され映画デビュー。役作りのために短期間で体重を10kg以上減量し、麻薬に溺れて死んでいくジャズトランペッター浅川広行役を見事に演じている。 2008年 2ndアルバム「MITCH ORLEANS」をリリース。 河内音頭 本家鉄砲節 鉄砲光丸師に弟子入り。音頭取り「河洲虎丸」としても修行中
【福居良】
1948年 平取町生まれ。18歳でアコーディオンを始め、22歳の時ジャズピアノを始める。1976年 1stアルバム『Scenery』。1977年に 2ndアルバム『Mellow Dream』を発表。1982年上京し、自己のトリオで新宿ピットイン・吉祥寺サムタイム・名古屋ラブリー等で活動。1986年 帰札。1989年 パリのジャズクラブ「ル・プティ・オポルチュン」に招かれ、1週間出演し好評を博す。1991年 HTB-TV「スクリーンHOT情報」にレギュラー出演。1995年 3rdアルバム『MY FAVORITE TUNE』発表。また、この年バリー・ハリス(p)のレギュラーメンバーであるリロイ・ウィリアムス(ds)ライル・アトキンソン(b)を招き、スーパートリオコンサートを主催。1996年 HBC-TV「オホーツク厳冬紀行」出演。山形県蔵王ジャズフェスティバルにスーパートリオで出演。1999年 4thアルバム『福居良 in New York』を発表。
【山木将平】
1989年札幌生まれのソロアコースティックギタープレイヤー。13歳よりギターを弾き始め、インストとブルースにのめり込む。オープンチューニングやスラッピング、タッピングなどの特殊奏法を用いて作曲・演奏活動を行っている。2010年 SAPPORO CITY JAZZでベストプレイヤー賞受賞。2011年 1st Album「NORTH WIND」リリース2012年 2nd Album「The Next SHOw Time」リリース2012年 7月『SAPPORO CITY JAZZ 2012 WHITE ROCK MUSIC TENT LIVE』出演(SOLD OUT) 2012年 8月『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO』出演(BOHEMIAN GARDEN)現在、日本だけに留まらず、定期的に世界各国でライブ活動を行なっている。
近日第一弾発表!お楽しみに!
芸森ハーベスト実行委員会
HAJ(株)北海道アルバイト情報社
芸森スタジオ、(株)WESS、札幌国際短編映画祭、他
芸森スタジオ 011-206-7355(月〜金 10:00-18:00)
森 士(もり・おさむ=浦和学院高等学校硬式野球部監督) 『致知』2013年9月号 致知随想より └─────────────────────────────────┘ 二〇一三年四月三日、春の甲子園で 我われ浦和学院高等学校は初めて頂点に立った。 苦節二十二年――。 振り返るといろいろなことが頭の中を駆け巡る。 その都度目の前に敵が現れ、 思うようにいかないことの連続であったが、 生徒や家族、守るべき存在がいたからこそ 頑張ってこられたのだろう。 今回優勝できた一番の要因は私自身の意識にあると思う。 まだまだ未熟だが、やはりトップに立っている 人間の器を広げないと組織は伸びていかない。 教育とは自分自身を磨くことだと日々実感している。 甲子園優勝は夢のような瞬間だった。 しかし、それ以上に私が誇っていることは、 この二十二年間、春夏秋とある埼玉県大会で 決勝戦に行っていない年が一度もないということだ。 毎年生徒が入れ替わる高校野球では、 時としていい選手が集まらないこともある。 だからといって、「今年は諦めて来年勝てばいい」という チームづくりは一切してこなかった。 集まってくれた生徒が常に主人公であり、 とにかくいま目の前の代に懸ける。 その積み重ねが成果に繋がったのではないだろうか。 私が今日あるのは上尾高校時代の恩師・野本喜一郎監督が いてくださったからに他ならない。 大学時代、私は怪我に泣かされ、 このまま選手として続けるか、指導の道に進むか悩んでいた。 野本監督は上尾高校から浦和学院高校に移られていたが、 そんな時、野本監督から 「もし指導者を志すなら、手伝わないか」と 声を掛けていただいた。 ところが、である。 大学四年の時、野本監督はすい臓がんで亡くなってしまった。 その年、浦和学院は初の甲子園出場を果たし、 ベスト4まで勝ち進んだのだが、秋の大会では一回戦負け。 選手たちは恩師を亡くした悲しみに 打ちひしがれていたようだった。 そんな彼らの姿を見た時に、学校さえ違うものの、 同じ師のもとに集った一人の人間として、 残された後輩たちに何か手助けができないだろうかと思い、 師の亡き後の浦和学院高校を守り立てようと決めた。 五年間のコーチ指導を経て、 監督に就任したのは一九九一年、二十七歳の時。 以来、負けたら終わりという勝負の世界に ずっと身を置いてきた。 その中で何が勝敗を分けるのかと考えると、 それは瞬間的集中力の継続、に尽きるのではないかと思う。 私はよく生徒たちに 「野球とは人生一生のドラマを二時間に凝縮したもの」 と言っている。 その時その時の決断が後の人生を大きく左右するように、 野球の試合も一瞬のパフォーマンス次第で 状況は目まぐるしく変化していく。 例えば……
松川昌義(日本生産性本部理事長) 『致知』2013年9月号 連載「私の座右銘」より心の支えとなる座右の銘を持つことは、 山あり谷ありの人生を歩んでいく上で 非常に大事なことだと思います。 特に逆境に立たされた時、そういう言葉が自分を鼓舞し、 果敢に立ち向かっていく力を与えてくれるのです。 組織を導くリーダーとして、 私が常に反芻(はんすう)してきたのは、 陽明学者・張詠(ちょうえい)の言葉です。 「事に臨むに三つの難あり。 能く見る、一なり。 見て能く行う、二なり。 当に行うべくんば必ず果決す、三なり」 事に臨む、変化に対応していくには 三つの難しいことがあります。 一つは対象をよく見て 的確に判断するための観察力、調査力。 二つ目はそれを行動に移す実行力。 しかしそれだけでは不十分で、 その上にさらに重要なのが果決であるということです。 これは、日本生産性本部における私の上司であり、 人生の師とも仰ぐ牛尾治朗会長が、 安岡正篤先生から教わった言葉として お話しくださったものです。 安岡先生は、果決という言葉の意味を、 次のように説いてくださったそうです。 果物の木に咲いている花を すべて実らせてしまってはいい果実は採れない。 どの花を残すかを考え抜き、勇気を持って決断し、 選んだ花から立派な実を育てなければならないと。 よし、これでいこう。 折しも強い危機の最中にあった私の心に、 この言葉はストレートに響き、肚を固めることができたのでした。 それは、私が日本生産性本部の理事長に就任した 二年前のことでした。 その年の三月に発生した東日本大震災により、 予定していたプロジェクトの多くが中止や規模縮小を 余儀なくされ、経営は赤字転落。 このまま手をこまねいていては 生産性本部の存続そのものが危うくなる―― 損傷した日本生産性本部のビルを見上げながら 強い危機感を抱いていた頃に教わったのが、 この果決という言葉でした。 日本生産性本部は昭和三十年、 経済同友会の設立に尽力された郷司浩平さんが、 当時まだ生産性の低かった日本企業の近代化を 促進するために設立された財団法人です(現在は公益財団法人)。 しかし、その後社会情勢は大きく変わり、 時代にそぐわない事業が増えてきたにもかかわらず、 旧弊を引きずりなかなか思い切った改革に 踏み出せずにいました。 理事長就任前から牛尾会長の熱心なご指導を受け、 ピンチをチャンスに変えよと繰り返し 説いていただいていた私は、 この震災を機に事業再生に 根本から取り組もうと決意を固めたのです。 そこで六月に理事長に就任すると、 私は「事業再生タスクフォース」を立ち上げ、 既存の百の事業を徹底的に精査し、 各々の経常利益まで分析しました。 その分析結果をもとに、 私は一つひとつ存続の可否を決断。 まさしく果決を実践したのです。 それは容易な作業ではなく、考えに考え、 思い悩んだ末に決断を下した体験から、 私は果決という言葉の重さを実感したのでした。

「鳥の歌」の原曲はキリストの誕生を祝い鳥たちが歌う という内容の、
カタロニア地方に伝わるクリスマス・キャロル。
現代でもキリスト教の聖歌として歌われている。
整体法の故・野口晴哉氏が終生「わが心の師なり」と尊敬した
チェリスト、パブロ・カザルスが、
カタルーニャ民謡『鳥の歌』(El Cant dels Ocells)を演奏し始めたのは、
第二次世界大戦が終結した1945年といわれる。
この曲には、故郷への思慕と、平和の願いが結びついており、
以後カザルスの愛奏曲となった。
1971年10月24日、カザルス94歳のときにニューヨーク国連本部において
「これから短いカタルーニャの民謡《鳥の歌》を弾きます。
私の生まれ故郷カタルーニャの鳥は、ピース、ピース(英語の平和)
と鳴きながら飛んでいるのです」と語り、
『鳥の歌』をチェロ演奏したエピソードは伝説的で、録音が残されている。
カザルスの故郷スペインは1939年の内戦以降、
独裁者フランコによる軍事政権が続き、
「自由な政府ができるまで祖国には帰らない」 と語り、
スペインを離れたカザルスは、 祖国の土を踏むことは二度となかった。
彼は優れたチェリストであるばかりでなく、 大指揮者であり、
またシュバイツァーと共に、 核実験禁止の運動にも参加した平和主義者だった。
この演奏の声は、音楽を超えて、私達に迫る。
それは、平和を訴えると共に、音楽の本質は何かと訴えるものなのだ。

その「鳥の歌」をスペインの誇る国民的歌手、同じカタルーニャ地方出身の
「MARINA ROSSELL・マリナ・ルセイユ」が歌います。
魂に打ち続けるチェロと声の響きに、音楽と人間の深遠さを思うのは、私ばかりでしょうか。
中桐万里子(二宮尊徳七代目子孫・リレイト代表) 『致知』2013年9月号 特集「心の持ち方」より http://www.chichi.co.jp/monthly/201309_pickup.html#pick1金次郎の教えで有名な 「たらいの水の話」というのがありますね。 水を自分のほうに引き寄せようとすると 向こうへ逃げてしまうけれども、 相手にあげようと押しやれば自分のほうに戻ってくる。 だから人に譲らなければいけないと。 けれどもこの話には実は前段があるのです。 人間は皆空っぽのたらいのような状態で生まれてくる、 つまり最初は財産も能力も何も持たずに生まれてくる というのが前段にあるのです。 そしてそのたらいに自然やたくさんの人たちが 水を満たしてくれる。 その水のありがたさに気づいた人だけが 他人にもあげたくなり、 誰かに幸せになってほしいと感じて 水を相手のほうに押しやろうとするんです。 そして幸せというのは、自分はもう要りませんと 他人に譲ってもまた戻ってくるし、 絶対に自分から離れないものだけれども、 その水を自分のものだと考えたり、 水を満たしてもらうことを当たり前と錯覚して、 足りない足りない、もっともっととかき集めようとすると、 幸せが逃げていくんだというたとえ話だと祖母から教わったんです。 それから金次郎は、偉大な思想家、経済学者、農政家と いわれていますが、彼はやっぱり農民だった、 土と一緒に生きた人だったと凄く感じるんです。 例えば金次郎が残した道歌にこういうものがあります。 「米まけば 米の艸(くさ)はえ 米の花 さきつゝ米の みのる世の中」 米を植えれば米が実るという 当たり前の道理を歌っているんですが、 金次郎はこの歌の米の部分を茄子や麦や芋や あらゆるものに置き換えて歌っていて、 とてもありきたりなんですが、そのことをとても楽しんでいる。 農業という自分の仕事に力を尽くしてきた人だ というのが伝わってくるとともに、 とても大切なことを教えられるような気がするんです。 仕事をやっていると、自分は小さなことしかできていない という焦りや、不安に苛まれることもあります。 けれども金次郎は常に目の前の現実、 自分の一歩を大事にし、愛おしみ、 感謝しなさいと教えてくれ、 浮ついてしまいがちな自分を 地面に引き戻してくれる人だと私は感じています。 ※中桐さんが、作家の三戸岡道夫氏と語り合った 「二宮尊徳の残した教え~心田の開発こそあらゆる繁栄の本~ 」。

一昨日、「無着色タラコ」「無着色明太子」の生産地・寿都の南波さんに行って来ました。
長年、魚を扱って来て、ようやく地元でタラコの安定供給の道を見出したのです。
しかも、ずべて原材料は地物日本海産のスケソウ鱈の卵。
輸入物は一切なしという徹底振りで、その工場の衛生・製品管理の徹底さにも驚嘆しました。

(「無着色明太子」80g 、「無着色たらこ」70g )
また、全く添加物を加えないという一貫性。
産地は北海道で、加工は福岡、・・・なる明太子。
それを、北海道の人々が何十倍もの値段で買って食べるという馬鹿な構図がありました。
しかし、これからは、地物を地元で作って、地場で売って買う健全な構図にしなければなりません。
そんな意味でも、この商材を起爆剤にして、裾野を押し広げることは、
地域活性にとても重要なことです。
これから、南波さんとタッグを組んで、前向きに商品開発に力をそそぎたいと思います。
詳しくは、後号まほろば便りの報告をご覧ください。

貧乏と小児マヒを乗り越えた孝行社長の物語 川辺 清・著* * 焼肉の「情熱ホルモン」をはじめ、 様々な事業を手がける「五苑マルシングループ」は、 今年4月で創業から50年を迎えます。 創業者の川辺清氏は昭和13年生まれ。 靴職人で博打好きだった父はほとんど家に帰ることなく、 母は生活費を得るために、 夫の行方を捜しながら4人の子供を育てたといいます。 清が2歳の頃のことです。 帰ってきた母がボロ布団の中でぐったりと横たわる清を見つけました。 布団をめくってみると、 紫色に腫れ上がった清の左足首からは膿が垂れ、虫が湧いています。 急いで病院に駆け込んだものの、 清の左足は完治することなく、 小児マヒの身となってしまいました。 その後、父の意向で清だけが 親戚の家に預けられることになります。 継ぎ接ぎだらけの服、小児マヒで骸骨のようになった左足、 それを引きずるようにして歩く姿がおかしいと、 近所の子供たちから毎日のようにいじめられました。 孤独でつらい日々でしたが、 清の心の中にはいつもやさしい母の存在がありました。 子供の頃から抱いていた この「お母ちゃんを早く楽にしてあげたい」という思いは、 清が大人になってからも続きます。 中学を出た清は、 奈良の靴職人のもとへ奉公に出ました。 仕事は朝6時半から夜中の12時まで、 休みは月に2回のみでしたが、 早く一人前になりたい一心から懸命に働きました。 ところが2年経った頃、結核を患ってしまい、 不本意にも実家へと追い返されてしまったのです。 「俺は本当に駄目なやつだ」 絶望した清は自らの命を絶とうと迫り来る機関車に身を投げました。 ところが次の瞬間、清は傍らの草むらの上に倒れていたのです。 恐れに飛び退いたか、風圧に飛ばされたか、ともかく生きていました。 ふと線路を見ると、 ポケットから転がり出た5円玉が身代わりに機関車に潰され、 平べったくなっていました。 「俺は5円玉や。5円玉の輝きを見せてやる」 新たな決意に病魔も退き、無事年季を全うした清は25歳で会社を創業。 以来、異業種にも果敢に挑戦しながら、 経営者として事業に情熱を注ぐ一方、 子として母に孝養を尽くしました。 実話を元に記された川辺氏の半生が描かれた本書は、 遡ること平成5年に刊行された作品です。 この20年、川辺氏は正月になると本書を読み返し、 自身の原点を振り返ってきたといわれます。 親が子を思い、 子が親を思う姿が美しく綴られた感動の名作から、 親子関係や孝行のあり方について、 見つめ直してみるのはいかがでしょうか。