駒村 純一(森下仁丹社長)
※『致知』2014年1月号
特集「君子、時中す」より
![komamurajunichi_CJ6C9490_800[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/komamurajunichi_CJ6C9490_8001.jpg)
――2006年に社長に就任され、
僅か2年で黒字転換を成し遂げられましたが、
その要因はなんだと思われますか。
組織の構造自体を見直したことが大きかったと思います。
何をしたかというと、社内の部署を
一度すべてなくしてフラットにしました。
――部署を取り払う!?
簡単に言えば、部署をバラバラにして、
プロジェクトチームをたくさんつくるということです。
結局それまでは縦割りのお役所仕事になっていたんです。
まず企画部が商品のアイデアを考え、決裁を取り、
デザイン、製造、営業と、
それぞれ稟議書に判子が押されないと
次のステップに行けない。
それでは時間がかかってしまって、
仕事にスピード感が生まれないんですね。
そこで異なる部署の人同士でチームをつくり、
一つのテーマに関して徹底的に議論を重ねていったんです。
私もその現場にできる限り足を運び、
社員と対話をするよう心掛けていました。
――ああ、現場に出ていかれた。
役員室にいたって、ただ数字を眺めているだけで
何も起きないわけです。
リポートを待っていても出てきませんから、
逐次デイリーな情報を現場で拾い上げる。
例えば、商品のパッケージについて話し合った時、
私が「このデザイン買う気にならないね。
なんでこんなふうになってるの?」と聞くと、
「上の人がこれがいいって言っているので」と。
「いや、君らはどう思うの?」
「ちょっと古臭いかなと……」
「じゃあなんで言わない。
いまの市場に合わないんだったら売れるわけないよね」
そこで分かったのは、
伝統企業のしきたりゆえに物凄く儀礼が先行し、
妙に上の人に遠慮してしまう部分があるということでした。
だから、バカ丁寧な言葉遣いは一切やめさせたんです。
例えば、「お言葉ですが」ではなく、
「私の意見としては」と言いなさいって。
そうすることで活発に議論ができる社風へ変えていくとともに、
市場のニーズを捉えた商品づくりに挑んでいきました。
それを何年も繰り返し続けていくことで、
160億円の負債があった森下仁丹は
現在、売上高96億円、4億円の経常利益を出す
企業へと生まれ変わりました。
――目覚ましい変化ですね。
それでも私自身が手応えを感じ始めたのは、
社長就任から4年くらい経った頃でした。
やはり組織というのは
「1」の力で「1」変わるのではなく、
「10」の力でようやく「1」変わるものだと思います。
組織をフラットにしたもう一つの理由は、
人材の適性を見るためでした。
この人、一体どういう人?
どこが最適なの?って。
ただ、それだけですべて見極めることは
できないので、まずはやってもらう。
だから私は年齢に関係なく
ポジションを逆転させ、
若い人を積極的に抜擢していきました。
――キャリアに拘らず、見込みのある人材をどんどん登用された。
もちろん全部が成功するってわけじゃない。
だから、人事は比較的早く変えました。
合わないなと思ったらすぐ移す。
この人の性格とか仕事のやり方を見てると、
どうもこっちの畑のほうがいいんじゃないかなと。
なのでそこに関しては「石の上にも三年」
というのとは少し違うんですよ。
どっちかというと朝令暮改。
半年くらい見ていると分かるんですね、
その人のポテンシャルが。
無理なことをいつまでもやらせていたら、
本来一番伸びるところまで潰れちゃうんです。
だからまずは得意なところで実績を出すことが第一です。
そこで才能を伸ばした上で、
次のキャリアで苦手分野にチャレンジして経験を積んでいく。
自分の持ち味を発揮できない状態で、
立派なジェネラリストにはなれないですよ。
自分の強み、そこがやっぱり自信の源になってきますから。
* * *
・三菱商事の事業投資先で社長を務めていた駒村氏が
52歳の時、赤字の森下仁丹へ転職した理由とは?
・伸びる社員と伸びない社員の差
・リーダーに求められるものは
情報量とインスピレーション
・企業再建に当たって大切にしてきた言葉
・駒村流「経営の極意」とは?
続きはぜひ『致知』1月号P40をご一読ください。


![img_1045610_45946126_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/img_1045610_45946126_11.jpg)
![img_bd48007576520c86ce18847c56e61e5a32934[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/img_bd48007576520c86ce18847c56e61e5a329341.jpg)

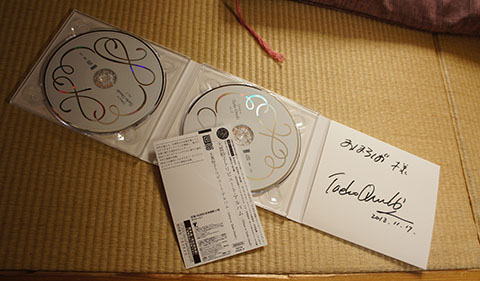



![2011040219532562b[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/2011040219532562b1.jpg)
![20110402195523e89[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/20110402195523e891.jpg)
![20100102-769784-1-N[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/20100102-769784-1-N1.jpg)




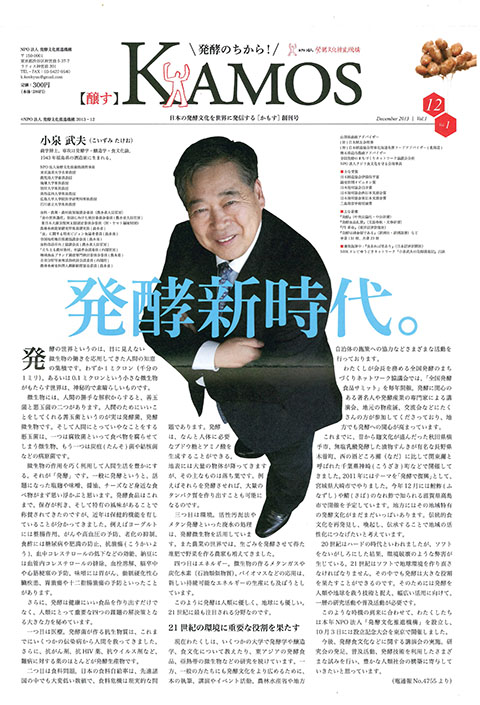

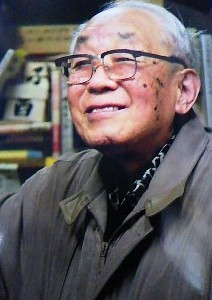
![komamurajunichi_CJ6C9490_800[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/12/komamurajunichi_CJ6C9490_8001.jpg)