3月 17th, 2012
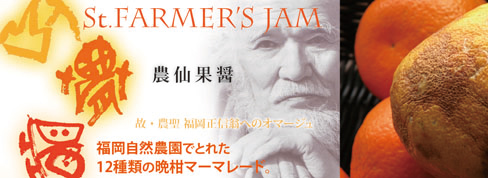
「St、Farmer’s Jam」。
「聖なる農人のジャム」・・・・こう書くと、連想するのが故・福岡正信翁しかありません。
あえて、農聖と冠したのは、まほろばが初めてかもしれません。
農聖・福岡正信翁へのオマージュとして、このジャムママレードを作りました。

丁度、福岡自然農園では雑柑が揃うのも終わりの頃。
甘夏、宮内・大谷伊予柑、八朔、文旦、ネーブル、清見柑、金柑、
小林柑、スィートスプリング、ひめまり、レモンの12種類。
それに、一二三糖と果糖を加えました。

これを、中国語で農業の仙人(聖人)による果醤(ジャム)、
『農仙果醤』と名付けました。
ジャムというより、果肉や皮が原型で入ったたっぷりのママレードです。
ケーキの達人、大和シェフによる手作りは、その勘所を押さえた妙にして絶妙。
実に、自然で豊かな福岡翁の哲学と美味が迫って来ます。

我田引水とはいえ、こういう素材の質と取り合わせは、
世界を見てもないと思います。
福岡先生でこそ成し得た、農の遺産でもあります。
それを結晶化した『St、Farmer’s Jam』、
『農仙果醤』を広くご愛用下さい。
200g ¥890
Posted by mahoroba,
in 商品
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 17th, 2012
![nomiyama[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/nomiyama1-242x300.jpg)
野見山暁治(洋画家)
『致知』2012年4月号
連載「生涯現役」より
────────────────────────────────────
【記者:野見山さんは戦没画学生の作品を集めた
「無言館」の創設にも携わっておられますね】
戦後二十年が経ち、僕が四十五歳頃のことですが、
NHKから戦没画学生の特集を組みたいからと
ゲスト出演の依頼があったんです。
その後、出版部から画集にしたいので、
遺族の家を回ってくれないかと相談がありました。
それでゲストに出た三人で手分けし、
十五軒ずつ回ったんですがね。
三軒目に亡くなった親友の家を訪ねたら
「あなた、どうして生きて帰れたんですか」
とお母さんが言う。
その時に、僕は何か自分だけが
うまく生き延びたような気がしてね。
息子を亡くし悲嘆に暮れている人を、
俺は見物しに回っているじゃないかという
後ろめたさがありました。
そしてその家から帰る時のことです。
玄関にあったコートに袖を通そうとするとお母さんが
「向こうを向きなさい」
と言って着せてくれたのはいいんですけど、
その手がね、離れないんですよ。ずうっと。
こう、僕の背中を触って…。
長年待ち侘びた子供が帰ってきたという、
その実感なんだなぁ。
僕はもう耐えられなくなってね。
翌日NHKに行って、頼むから降ろしてくれ。
とても回れないと言ったんですが、
それなら代わりの人を推薦してほしいと。
でも自分が途中で放り出して
人に頼むことなんてできないから、
結局続けて回ることにしたんです。
やがてNHKから『祈りの画集』という本が出ました。
すると窪島誠一郎という人が、
以来、十何年とその本を持っていて、
何回も何回も読み返したというんです。
そしてこの人たちの絵を集めて、
美術館をつくりたいから協力してもらえないかと言ってきた。
僕は彼に、よしなさいと言いました。
労力や時間やお金がかかるのはもちろん、
行った先々で、もうこれは止めにしたいという
切ない思いになる。
なにしろ当時は戦没者の遺族を回る詐欺が
横行していましたから。
僕が訪ねていくと
「どうせ、金をせびりに来たんだろう。
おまえさん、いくら欲しいんだ?」
などと言われる。
画集を作りたいと言っても
「写真を撮ったらすぐに帰れ。後は一切関わらない」
とか。
ところが彼はね、何度言っても、
やると言って聞かないんですよ。
俺は協力しない、二度と回る気がしないと言っても、
「どんなことでも覚悟していますから」
と言って聞かない。
でも僕はね、実はそういう人が現れるのを待っていたんです。
これだけ言ってもやると言うなら、
この人は本当にやるな、やってくれるなと思った。
僕はその十年前にいろいろな家を回った時、
こんな別れ方を遺族の方としているんです。
「私たち夫婦が死んだら、
戦死したこの弟の絵はどうなるか分からない。
それじゃ私たちは死にきれません。
お願いします。待ってますから。
保存する機関を探して必ず連絡ください」
「……分かりました」。
そう言わないと帰れない家が何軒もありました。
これでやっとあの方たちとの約束を果たせると思いました。
そして窪島さんと一緒に全国を回ることになったんですが、
彼がまた周到な人で、美術館設立への思いを
前もって文章に託して、皆に配っていたんです。
最初に栃木の農家を訪ねた時は、
爺さんが森の前に立って我われを待っていた。
そしてこう言った、僕に。
ぎゅっと強く手を握ってね。
「あれから十八年間ずうっとあなたが来られるのを
待っておりました。
弟の絵を預かるところを必ず探してくるとおっしゃったから」。
僕はその時にね、こういう人がいるんだから
こうして生きててよかったな、
これはどうしても美術館を
つくらなきゃいけないと思いました。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 17th, 2012
まほろばは花卉も扱っている。
お花や鉢物など、・・・・春の苗木時には、玄関前が、
パッと花咲いたように輝く。まるで浄土の園にいるような感じだ。

先日、「あせび」の鉢が入荷した。
そのすずらんが連立したような可憐な感じが、何とも良かった。
「馬酔木」と書く「あせび」と謂えば、さだまさしの『まほろば』が思い起こされる。
馬酔木(あせび)の森の馬酔木(まよいぎ)に
たずねたずねた 帰り道
牛馬がこの花を食べれば、毒性成分で酔ったようになることで、馬酔木の字が当てられたという。
若き男女の恋の迷いと、散策する奈良・春日野の森が響き合っています。
アセビ(馬酔木)を調べると 多くの草食ほ乳類は食べるのを避け、食べ残される。
そのため、草食動物の多い地域では、この木が目立って多くなることがある。
たとえば、奈良公園では、鹿が他の木を食べ、この木を食べないため、アセビが相対的に多くなっている。
食物は、自ら動けないので、自分の身を守るために毒ガスなどを出す。
これを自然(漢方)農薬とも謂うが、虫や動物を避けて生き延びるための培われた智慧だ。
可憐さゆえの、健気な防御本能だ。
この鉢には、「屋久島あせび」とあり、一層いとおしく感じた。
寝ぐらを捜して鳴く鹿の
後を追う黒い鳥鐘の声ひとつ
馬酔の枝に引き結ぶ
行方知れずの懸想文(けそうぶみ)
Posted by mahoroba,
in 文化
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 17th, 2012
![1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/11.jpg)
南雲 吉則 (ナグモクリニック院長)
『致知』2012年4月号
連載「大自然と体心(たいしん)」より
────────────────────────────────────
10数年前、当時30代後半の私は、
身長173センチ、体重77キロの立派なメタボ予備軍。
いつも腹回りが苦しく、心臓に負担がかかっている
感覚がありました。
さらに、ワキガ体質で、加齢臭も気になり出していました。
ところが、18年経って現在56歳の私は、
体重62キロをキープ。
メタボリックシンドロームとは程遠く、
ワキガも加齢臭もまったくありません。
当時より、見た目も体の中身も、気持ちまでも若返っています。
初対面の人に私の年齢を言うと、たいてい驚かれます。
どうも実年齢より20歳くらい若く見えるようなのです。
ためしに、体の各部分が何歳くらいに相当するか
調べてみたところ、脳年齢が38歳、骨年齢は28歳、
血管年齢は26歳という結果になりました。
どうして私が若さを保ち続けることができているのでしょうか。
私の生活習慣は実にシンプルです。
「腹六分の食事」
「早寝早起き」
「通勤時のウオーキング」
の3つを柱に、規則正しい生活を続けているだけです。
サプリメントを飲んだり、ハードなトレーニングを
課しているわけでもありません。
ただ、この生活習慣を強力にサポートし、
その効果をアップさせてくれているものがあります。
それが「ゴボウ茶」です。
私がゴボウ茶と出合ったのは40代半ばでした。
当時の私はひどい便秘症で、トイレでいきむと不整脈になり、
生命の危機さえ感じていました。
家系的にも祖父が52歳で心筋梗塞で亡くなり、
父も62歳で倒れてリタイア。
自分もいずれそうなるのでは、と不安になり、
まずは知り合いの農家の方に便秘を治す方法を相談したところ、
教えてもらったのが「ゴボウ茶」だったのです。
作り方を教わり、飲み始めると、便秘が治るどころか、
なんだか体が元気になったような気がするのです。
鏡で見ると肌つやもよくなって、
どこか生き生きとした感じです。
「これはすごい!」と、ゴボウの成分について調べてみたところ、
ゴボウには人間を若返らせ、元気にする栄養分が
たくさん含まれていたことが分かりました。
* *
ゴボウ本体に含まれる食物繊維は野菜の中でもダントツ。
しかも、ゴボウには朝鮮人参並みの
漢方薬成分が含まれています。
以下にその素晴らしい効果をご紹介します。
<ダイエット・美肌効果>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ゴボウを皮ごと水にさらすと出てくる真っ黒な汁。
これは灰汁ではなく、皮に含まれる
「サポニン」というポリフェノール成分で、
朝鮮人参の薬効成分とほぼ同じなのです。
サポニンの「サポ」は「シャボン」と同じ語源に由来し、
界面活性作用を持っています。
石鹸の泡が油に吸着して洗い流すのと同様に、
ゴボウに含まれるサポニンが体内のコレステロールや
脂肪に吸着して、洗い流してくれます。
この界面活性作用によって太りにくい体に
体質を改善することができます。
さらに、ゴボウ茶を飲み始めると肌がきめ細かくなります。
皮脂の分泌が抑えられ、毛穴が小さくなるためです。
また、サポニンには強い「抗酸化作用」があり、
老化の原因となる「活性酸素」を除去し、
肌の修復力を高め、老化の進行も抑えてくれます。
その他、がん・糖尿病予防、血行促進・整腸作用、
ゴボウ茶の作り方や、その効果を倍増させる秘訣など……、
Posted by mahoroba,
in 人生論, 長寿
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 16th, 2012
ジェノベーゼ・ペースト 270g ¥1.832
国産のフレッシュバジルとイタリア産のグラナバダーノチーズ、オリーブオイルから
作ったペースト。パスタソース以外にも、温野菜サラダのドレッシングや
ソテーした肉や魚のソースなど幅広くご利用いただけます。

セミドライトマトオイル漬け(オーガニック) 200g ¥834
南イタリアさんの完熟トマトを天日で半乾燥させ、香草と共にオイル漬けにしました。
甘みと旨みが凝縮した味わいで、そのままおつまみに、パスタやピッツアの具に、
またはつぶしてソースなどにお使いいただけます。
本当に、この隠れ味、隠し道具があれば、來客もビックリしますよ。
家庭でレストランの腕が振るえます。
Posted by mahoroba,
in 商品
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 15th, 2012
先日、三越のデパートに寄ったとき、たまたま催し会場で、
「工藤和彦展」が開かれていた。
久し振りの再会で、本店に飾ってある絵の作者・上杉さんの
障害者施設で、お世話や陶芸を教えていたりする好青年だ。
その工藤君が、全国的にもメキメキ頭角を現して、
あの料理研究家の「栗原はるみ大賞」を受賞したり、
裏千家の雑誌「淡交」の裏表紙を飾って宣伝せられたりと、
中央でも評価が上がっている。
使い勝手がよく、軽く、しかもリーズナブルさが好まれる所以でもあろう。
時間がありましたら、覗いてみて下さい。

ごあいさつ
私は北海道の広い大地と豊かな自然の中で、
のびのびと創作に励んでいます。
私の創作には、北海道の地元の粘土を使用しています。
この粘土は、4万年の歳月をかけて日本海を超えて
北海道北部に堆積した「黄砂」からなるものです。
粘土の年代を測定すると、2億年前のものだそうです。
恐竜がいた白亜紀に地表にあったものです。
このダイナミックな地球の息吹を大切にして、
作品に出来ればと、日々精進しております。
末永くご愛用いただければと幸いと存じます。
工藤 和彦
工藤君のHP、ブログがあります。

「工藤和彦作陶展」
3月13日~19日
三越ギャラリー 本館9階
Posted by mahoroba,
in 文化
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 15th, 2012
占部賢志(福岡県立太宰府高等学校教諭)
(『致知』2004年12月号 特集「徳をつくる」より)
日本の文化伝統を次代を担う
子どもたちにどう伝えていくか。
これが学校教育の中核であるべきだと思っているんです。
私がこういう考えを抱くようになったのも、
小林秀雄さんの教えなのです。
私は学生時代以来、一所懸命読んだのは
小林秀雄さんの本でね、
ある時宮崎の延岡に講演にいらっしゃるというので、
会いに行ったことがあるんです。
その時、私はどうしても質問したいことがあったんです。
![TKY201003170292[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/TKY2010031702921.jpg)
「歴史を知ることは自分を知ることだ」
と小林さんはよくおっしゃっていたが、
その意味が当時の私にはよく分からなかったんですね。
夜の11時近くなっていたでしょうか。
小林さんが地元の名士と一緒に
ホテルへ戻ってこられたところへ
「質問があります」
と割って入っていったんです。
小林さんは
「君を産んでくれたのは誰か。
君のおっかさんだろう。
おっかさんのいいところも悪いところも
みんな君の中に流れている。
そうすると、おっかさんを大事にすることは、
君自身を大事にすることだ。
君が君自身を大事にすることは、
おっかさんを大事にすることになる。
歴史だって同じじゃないか。
日本の2千年の歴史は君のこの身体に流れている。
君が君自身を大事にすることは、
歴史を大事にすることだ。
だから歴史を知ることは、自己を知ることに繋がるんだ」
ということを噛み砕いてお話しくださった。
考えてみればその通りで、日本の古典には
「鏡もの」というのがありますね。
『大鏡』や『吾妻鏡』。
あれは全部、歴史書です。
日本人は古来、歴史を鏡だと思っていたんですね。
歴史を学べば本当の自分の姿が見えてくるんです。
そういう意味で、生き方の鏡として
歴史を子どもたちに提供していけば、
期せずして徳をつくる教育になるのではないかと思います。
Posted by mahoroba,
in 歴史
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
3月 15th, 2012
![114_61382[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/114_613821-150x150.jpg)
鈴木 武 (環境プランナー)
『致知』2007年2月号
特集「一貫(いちつらぬく)」より
────────────────────────────────────
排出物の分別置き場には、いくら分別の注意書きを貼っても
真面目に読んでくれる人はほとんどいません。
だからといって、指示通りに出してくれない社員を
その場で呼び止めて注意しても効果はありません。
自分の仕事と関係なく、やりたくもないゴミ出しを
やらされて頭にきている人を説教すれば、
火に油を注ぐようなものです。
「あの生意気な環境の新人はなんだ」と反感を買い、
その後の協力が望めなくなるばかりか、
悪い噂が広がりクビにつながる可能性もあります。
だから私は、こうしなさいと命令したことは一度もありません。
指をさしたらその相手は敵になるのです。
ではどうやって無関心な社員の意識を喚起し、
気分よく協力してもらうか。
すべては仕掛け、仕組み、工夫次第です。
まず、前日の夕方に分別の棚を
全部きれいに片付けて雑巾がけをしました。
そして各コーナーに一つずつ、
排出物を模範的なやり方で出しておくのです。
翌朝各部署から排出物を持ってきた人がそれを見ると、
「よそは結構きれいに置いてるな。
いいかげんな出し方はできないぞ」
となります。
出しておいた排出物がモデルになって
私の代わりにしゃべってくれるのです。
出しておく位置を毎日少しずつ変えておけば
不自然な感じはせず、私が演出していることがばれずに済みます。
コピー用紙の束を持ってきた人が、
縛り方が悪いために荷崩れしてしまった時には、
「これは私がやりますから」
と、まず自分がやって見せながらうまく協力を求めます。
「実はこの荷造りでは、業者のおばちゃんが腰を痛めるし、
引き取りの値段も減ってしまうんです。
だからできれば次からは、おばちゃんのためにも
こんなふうに縛っていただけるとありがたいんですが」。
そう言えば、「分かった、考えとくよ」と、
怒りに火が点かないし、
「俺もやるよ」と手伝ってくれる人も出てきます。
それから、私は七つ道具を常に携帯して
いろんな場面で活用しました。
ゴミの出し方について説明する時など、
懐からおもむろに十手を出して指し示しながら話をする。
まるで漫画です。
しかめっ面をしていた相手の表情も
「それ、何ですか」と和らぎ、
笑いの中で分別に興味を持ってもらえるのです。
日光江戸村で仕入れてきた大判金貨も、
たいていの人は現物を見たことがありませんから
興味を持ちました。
ゴミを捨てに来た社員に触ってもらい、
重さを実感してもらいながら、
この百グラムの金塊(きんかい)は、
携帯電話のICに使われている金メッキを
5000~7000台分集めることでできるんですよ、
とうんちくを披露します。
金貨とともに分別の大切さが強く印象に残り、
噂が広まって他の人も見に集まってきます。
分別意識を高めてもらう絶好のPRになるのです。
置き場が隣接していたガラスと電池は、
なかなか指定通りに分別されず、
よく二つが混じった状態で放り込まれていました。
考えに考えた結果、私は一つの妙案を思いつきました。
排出物を入れる缶の位置を、
床から1メートル高く設置したのです。
人間の心理とは面白いもので、
入れ物が床にあればろくに分別もせずに放り投げるけれども、
位置が少し高くなっただけで、
そばまで寄ってきて丁寧に分けて入れる。
これは劇的な効果がありました。
何をやるにせよ、それにとことん燃えて取り組んでいると、
次々とアイデアが閃くものです。
朝の3時、5時、6時と閃いては目が覚め、
メモしたアイデアを私は次々と実行していきました。
その結果、それまでゼロに等しかった
松下通信工業のリサイクル率は99%になり、
それによって約2億円かかっていた
廃棄物の処分費が節減できました。
工場内はほとんどゴミのない状態となり、
33か所ある排出物置き場はいつ開けても空っぽです。
その運動は他の松下グループにも広がり、
私が定年を迎えた平成14年には、
松下グループ全体で98%のリサイクル率が実現しました。
こうした活動は通常、トップダウンで進められるものです。
松下通信工業のようにボトムアップで改革を成功した実例は
これまで日本になく、常識をひっくり返す快挙でした。
多くの企業で
「うちの社長は頭が固くて駄目だ」
「下がガタガタ言ったって、
上がやる気ないんだからできるわけない」
といった愚痴が聞かれます。
しかし、力のない窓際族でも、知恵と努力と工夫を重ねれば、
一万人の会社でも改革することはできるのです。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »


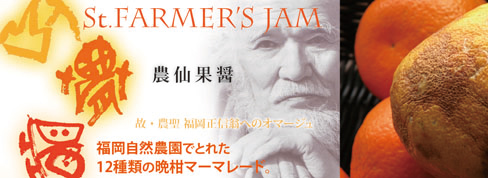

![nomiyama[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/nomiyama1-242x300.jpg)

![1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/11.jpg)
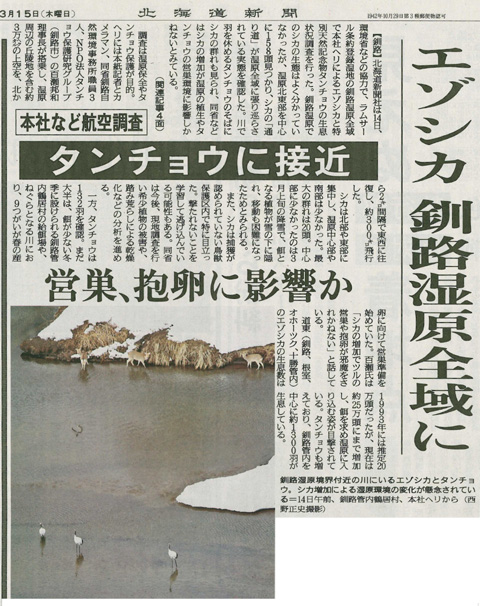

![misuzu[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/misuzu1.jpg)


![TKY201003170292[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/TKY2010031702921.jpg)
![114_61382[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/114_613821-150x150.jpg)