9月 24th, 2012
創業663年の歴史を持つ日本の饅頭の元祖・
塩瀬総本家会長の川島英子氏が語る
『致知』2012年10月号
特集「心を高める 運命を伸ばす」より
http://www.chichi.co.jp/monthly/201210_pickup.html#pick4
└─────────────────────────────────┘
◆ 自分というものは、ここにひょっと
いきなり成り立っているわけじゃなく、
遠いご先祖様からの命がずうっと続いてきて、いまこうしてある。
それを忘れてはいけないし、感謝しなくてはいけない。
そしてありがたいと思ったら、その気持ちを言葉なり、
字なり、行動なり、形に表すということを即刻やることが大切です。
◆ 悪い時は慎ましくそれなりに暮らしていく。
自分の代に沈むことがあっても、
必ず後に浮く時がくるのが世の常なのだと。
だから物事は長いスパンで考えることですね。
逆に「いい時はいいようにやっていく」のも大切で、
沈む時に備えてものを蓄えておきなさい、ということでしょう。
まさに「繁盛するに従つて益々倹約せよ」です。
◆ あまり「こだわり過ぎる」ということをしては
運は開けないのではないでしょうか。
時代の変化に対する柔軟な考え方と
挑戦する気持ちを持っていれば、
道は開けてくるように思います。
◆ 仏教に「無常」という言葉がありますが、
やはり世の中はいつも同じであるわけがない。
だから調子がよくても驕らず、沈んでも必ず浮く時が来る
という信念を持って取り組むことが
商売をやっていく上で大事なことですね。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 21st, 2012
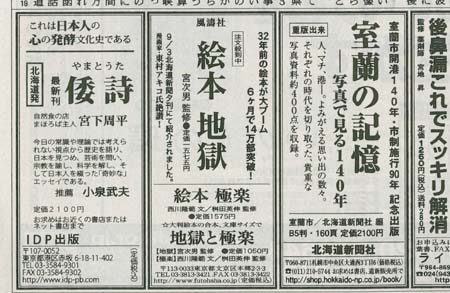
この19日(水)にも、北海道新聞の一面左下に『倭詩』の広告が。
北海道発となっておりますが、歴史のない北の涯から、
歴史ある日本の国を語っても良いのではないかと思うのです。
客観的に眺望し、そして主観的に一体となり、
新たなる眼差しで、日本の越し方行く末を綴って行きます。
その果に、和の国が再び甦らんことを・・・・。
Posted by mahoroba,
in 「倭詩/やまとうた」, 歴史
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 20th, 2012
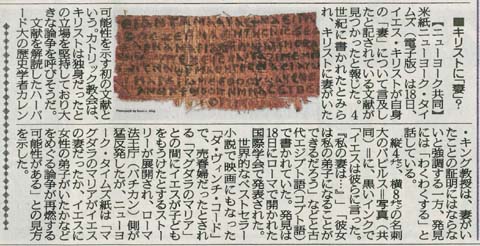
今さらの感もあるが、「イエスに妻が」居たことが話題になっている。
あの「ダ・ヴィンチ・コード」で物議を醸し、映画は世界的にセンセーションを起した。
これに関する文献は枚挙に暇がないほど、溢れている。
実際、若き日に読んだ「聖書外典」には散見できていた。
客観的歴史性から紐解いても、決して故なきことではない。
これらのこと、「エリクサーから無限心へ」の小冊子に詳しい。
それにしても、パピルスとコプト語・・・・というと、
遠い古代に、ロマンの夢が馳せてゆく。
Posted by mahoroba,
in 文化, 歴史
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→1 コメント »
9月 20th, 2012

札幌すすき野の「銀巴里」の幕が閉じるという。
銀座の銀巴里のことは、もう去りし日のこと、今や見聞きするすべも無い。
ただ金子由香里さんや三輪明宏さんの映像やレコードで、当時を偲ぶしかない。
その雰囲気を伝えるべく札幌の銀巴里の灯も消えるという。
寂しい限りだ。かといって、常連でもなく、数度ドアを潜っただけなのだが、
ただ、そこのママが、まほろばの初期からのお客様で、西野に住んでいらっしゃった。
そんな間柄で、初めて有機野菜の米内会長に連れられてお邪魔したは20年も前のこと。
なかなか、身近にシャンソンは聴けないものの、
唯一札幌での本格的ステージが堪能できる聖地でもあった訳だ。
また一つ、文化の灯が消えるのかと思うと、何か後ろ髪の引かれる思いでもある。
やはり、そういう何ともいえない歌の数々を聴けない世代が、
世の中の大半になったせいであろう。
しみじみと人生の哀歓を味わう心の受け皿がなくなってしまった。
Posted by mahoroba,
in 文化
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 20th, 2012

明日から江差町では、「江差追分」第50回全国大会が開催される。
記念すべき大会で、全国で、これほど大掛かりな民謡大会はないという。
私も少し関係しているので、土曜から見学したいと心待ちにしている。
何時も、江差追分の大家・青坂師匠がおっしゃるのは、上記の新聞記事のように、
コンクールで審査基準が設定されると、それに合わせて練習して、
本来の持ち味の情緒性が失われてゆくという懸念である。
これは、どんな分野でもいえることだが、一つのものを統合することで、
様々な多様性、多義性、多面性が失われてしまうということだ。
江戸・明治期、幾多の古調追分が散在していたのを、一つにまとめ正調追分を標準化した。
当初、それで試行錯誤して一つの方向性で進んだが、
それが安定期になって、それぞれの技法が先鋭化されると、
技術的には極めて高度になってゆくのだが、逆に最も大切な情緒性が損なわれて来た。
追分は、元々地場のもので、漁師や浜で暮らす人々の哀歓が底に流れている。
唄が広がり、生活臭がなくなった都会人が洗練させてゆくのはいいのだが、
逆に、本来の味や本質から遠ざかる。
果たして、競争という原理で、何が残り、何が失われてゆくか。
甚だ、憂うるものがある。
情緒を忘れず、技術を磨くことが、最上の道なのだろう。
これは、現代社会の警告でもあり、示唆でもある。
Posted by mahoroba,
in 文化, 歴史
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 19th, 2012

Organic Cafe 「知恵の木」さんからの掲載依頼です。
マクロビオティックの久司道夫先生の講演会が、上記の通り開かれます。
知恵の木さんでもチケットを取り扱っています。
Tel 011-853-5134 Fax 011-853-3211

Posted by mahoroba,
in イベント, 食
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 19th, 2012

「水産新聞」に、新刊書『倭詩』の紹介文が掲載されました。
今釧路沖では、ミンククジラの試験操業が始まっており、かねてから
小泉武夫先生が孤軍奮闘、伝統漁法としての捕鯨復活を訴えております。
その辺りの消息も、詳しく書かれている本書。
漁業関係者にも必読の一書としてお奨めいたします。

Posted by mahoroba,
in 「倭詩/やまとうた」, 漁業
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 19th, 2012
栃木県佐野市の自然食品店「セフティーまなべ」の真鍋辰彦代表から、
次のお知らせを頂きました。
彼の地出身の足尾銅山の田中正造翁も、国策と熾烈なる戦いをして来た先達であり、
小出裕章助教が、理想像として尊崇して来た方でもあります。
関東近辺にお住いの方は、是非「アースデー田中正造」の講演会にご参加下さい。
下に、小出仲間と言うべき「熊取6人組」の興味深い記事が掲載されています。




Posted by mahoroba,
in イベント, 震災 原発
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 19th, 2012
![dk22x02x01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/dk22x02x011-150x150.jpg) 玉置 半兵衛 (半兵衛麩会長・11代目当主)
玉置 半兵衛 (半兵衛麩会長・11代目当主)
『致知』2012年10月号
特集「心を高める 運命を伸ばす」より
http://www.chichi.co.jp/monthly/201210_pickup.html
──────────────────────────────
私の父は「老舗(しにせ)」という言葉が
一番嫌いだったんです。
老舗は老に舗(みせ)と書くけれど、
こんなに失礼な言葉はない。
うちの店は老いていない。
舗(みせ)は老いたらあかんのや。
舗が老いたら死を待って潰れるだけやと。
しにせの「し」は止とも表せますが、
進化を止めてしまったらそこで終わり。
だからしにせではなく、
新しい舗、しんみせでいきなさいと言うんです。
一代一代が、自分が新しい舗の創業者になったつもりで
商売をしなさい。常に新しいことをしていきなさい。
商売の本質
「先義後利(せんぎこうり=義を先にして、利を後にする者は栄える)」
を変えずに、常に時代の流れに合わせて革新の連続をしなさいと。
まさに「不易流行」です。
しんみせの「しん」は「真」の字で「しんみせ」とも表せます。
お客様に真心を尽くしなさいと。
他にも、信用、信頼を大切にの「信(しん)」。
驕らず控えめにせよの「慎(しん)」。
思いやりや仁の精神の「心(しん)」。
先祖を大切にしたり、お客様に親しみを感じてもらうの「親(しん)」、
規則を守り常に清らかの「清(しん)」、
辛い苦しいことでも辛抱できる「辛(しん)」、
人柄、家柄のよい紳士としての「紳(しん)」……、
こういう商売をしていけば自ずとしんみせになると。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 18th, 2012

昨日は、時々小雨降る中、「芸森ハーベスト」が開催された。
芸術の森や野外コンサートホールは知っていたが、少し先に、
このような温泉完備の宿泊施設が、録音スタジオ付きであることを、
ついぞ今日まで知らなかった。
いつか、道新に紹介された芸森スタジオは、世界でも折紙付きのもので、
坂本龍一と大貫妙子さんの「utau」を録音したことで、一躍有名になった。
11時から、市内の名店が出店しての賑わい、なかなか愉しい一時。
各ライブが終わっての5時からは、大貫さんのスタジオでのライブ。
初めての彼女の生声に、皆感銘。
ことに、音楽嫌いの家内は、スーと心に入って溶け込み、一体となって陶酔したという。
自分と同質の自然性を感受したのだろう。
これは、長い付き合いの中で、初めての驚くべき感想で、私がビックリした。
それほど、身も心をも溶かすほどの彼女の音楽性に脱帽したのだった。
そんな彼女の、いよいよ本格的な札幌での生活が始まる。
この雪国の都市から、文化の香りが世界に発信されれば嬉しい、と市民はみな思っている。
Posted by mahoroba,
in イベント, 文化
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
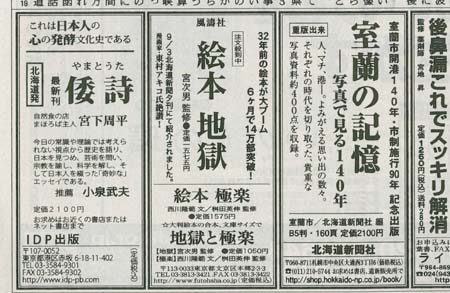
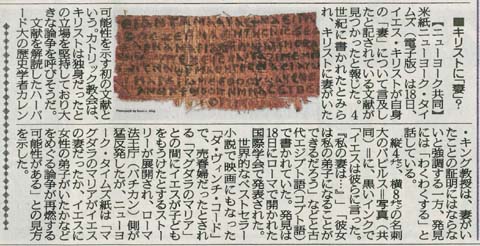









![dk22x02x01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/dk22x02x011-150x150.jpg)
