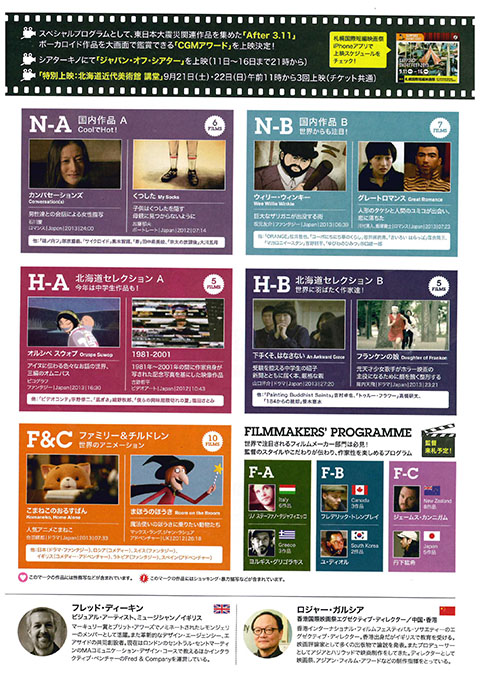9月 16th, 2013
女優の黒柳徹子さんが
「心から尊敬してやまない」と讃える人、福島智氏。
三歳で右目を、九歳で左目を失明、
十四歳で右耳を、十八歳で遂に左耳の聴覚まで奪われ、
光と音を喪失した氏は、絶望の淵から
いかにして希望を見出したのでしょうか。
現在発行中の『致知』10月号より、
その記事の一部をご紹介します。
┌───今日の注目の人───────────────────────┐
「肥溜めを肥やしに変える」
福島 智(東京大学先端科学技術研究センター教授)
『致知』2013年10月号
特集「一言よく人を生かす」より
http://www.chichi.co.jp/monthly/201310_pickup.html#pick1
![f0054757_19563521[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/f0054757_195635211.jpg) 私の場合は日々生きていること自体に勇気が必要です。
見えなくて、聞こえない世界にいるので、
未知の惑星にいるようなものでいつ何が起こるか分からない。
ただそうした道を歩んでくる中で、
自分が盲ろうになった時、
到達した一つの思いがあるんです。
十八歳の一月から三か月間で、
全く聞こえなくなっていくわけですが、
その過程で、自分は目が見えないのに、
その上どうして、さらに耳までが
聞こえなくなるんだろうかと考えました。
運命の理不尽さについて、
あるいは僕が何か罪を犯したんだろうか、
何か悪いことをしたんだろうか、
なぜ自分はこんな状況になっているんだろうか
などといろいろ考えたんです。
そして最終的に私が思い至ったのは
こんな考えでした。
なぜこんな状態になったかは分からないけれども、
自分は自分の力で生きているわけではない。
人間の理解の及ばない、
大いなる何ものかが私たちを生かしているとすれば、
僕がいま経験しているしんどさ、
この苦悩というのも、その存在が与えたものであろうから、
この苦しい状況にも何かしらの意味があるんじゃないか――。
そしてこの苦悩をくぐることによって
人生が輝くのではないかと、思おうとしたんです。
しんどい状況を経験することが
自分の人生の肥やしになるんじゃないかと。
要するに肥溜めみたいなものですね。
肥溜めのままだったら役に立たないけれども、
それを畑に撒くことによって肥やしとなり、
実りをもたらすかもしれない。
そして同じ頃次のような手紙を
友達に書き送っているんです。
「今俺は静かに思う。
この苦渋の日々が俺の人生の中で
何か意義がある時間であり、
俺の未来を光らせるための土台として、
神があえて与えたもうたものであることを信じよう。
信仰なき今の俺にとってできることは、
ただそれだけだ。
俺にもし使命というものが、生きるうえでの
使命というものがあるとすれば、
それは果たさねばならない。
そしてそれをなすことが必要ならば、
この苦しみのときをくぐらねばならぬだろう。
(中略)
俺はそう思ったとき、突然、今まで脳の奥深く、
遠いところで、この両耳の六種類の耳鳴りの
空間の向こうで回っていた、
半透明の歯車が回るのを止めたように感じた」
私の場合は日々生きていること自体に勇気が必要です。
見えなくて、聞こえない世界にいるので、
未知の惑星にいるようなものでいつ何が起こるか分からない。
ただそうした道を歩んでくる中で、
自分が盲ろうになった時、
到達した一つの思いがあるんです。
十八歳の一月から三か月間で、
全く聞こえなくなっていくわけですが、
その過程で、自分は目が見えないのに、
その上どうして、さらに耳までが
聞こえなくなるんだろうかと考えました。
運命の理不尽さについて、
あるいは僕が何か罪を犯したんだろうか、
何か悪いことをしたんだろうか、
なぜ自分はこんな状況になっているんだろうか
などといろいろ考えたんです。
そして最終的に私が思い至ったのは
こんな考えでした。
なぜこんな状態になったかは分からないけれども、
自分は自分の力で生きているわけではない。
人間の理解の及ばない、
大いなる何ものかが私たちを生かしているとすれば、
僕がいま経験しているしんどさ、
この苦悩というのも、その存在が与えたものであろうから、
この苦しい状況にも何かしらの意味があるんじゃないか――。
そしてこの苦悩をくぐることによって
人生が輝くのではないかと、思おうとしたんです。
しんどい状況を経験することが
自分の人生の肥やしになるんじゃないかと。
要するに肥溜めみたいなものですね。
肥溜めのままだったら役に立たないけれども、
それを畑に撒くことによって肥やしとなり、
実りをもたらすかもしれない。
そして同じ頃次のような手紙を
友達に書き送っているんです。
「今俺は静かに思う。
この苦渋の日々が俺の人生の中で
何か意義がある時間であり、
俺の未来を光らせるための土台として、
神があえて与えたもうたものであることを信じよう。
信仰なき今の俺にとってできることは、
ただそれだけだ。
俺にもし使命というものが、生きるうえでの
使命というものがあるとすれば、
それは果たさねばならない。
そしてそれをなすことが必要ならば、
この苦しみのときをくぐらねばならぬだろう。
(中略)
俺はそう思ったとき、突然、今まで脳の奥深く、
遠いところで、この両耳の六種類の耳鳴りの
空間の向こうで回っていた、
半透明の歯車が回るのを止めたように感じた」
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 16th, 2013

21,22日の「芸森ハーベスト」に向けての大貫妙子さんの記事が道新に掲載されました。
その中の自然農園というくだりは、まほろば農園のことかな?・・・・・・
ともあれ、札幌人に次第にもみじの赤のように染めなして行く彼女。
仲間として、末永くお付き合いして行ければ、嬉しく思います。
Posted by mahoroba,
in イベント
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 14th, 2013
山本 富士子(女優)
『致知』2013年10月号
特集「一言よく人を生かす」より
![img_1200998_34382144_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/img_1200998_34382144_01.jpg) 小津安二郎監督とは会社が違ったので、
出演したのは『彼岸花』の一本だけでしたけれども、
人間的魅力に溢れたとても素晴らしい方でした。
それまで自分の持っているものを
フルに出そうとしていた私に、
「百%、百二十%やらなくていいんだよ」
と、自然体で演じることを教えてくださいました。
心に残る言葉もたくさんいただきました。
「どうでもいいことは流行に従う。
重大なことは道徳に従う。
芸術は自分に従う」
「品行が悪いのは直せる。
品性のないのは直せない」
いずれも深く心に残りました。
小津安二郎監督とは会社が違ったので、
出演したのは『彼岸花』の一本だけでしたけれども、
人間的魅力に溢れたとても素晴らしい方でした。
それまで自分の持っているものを
フルに出そうとしていた私に、
「百%、百二十%やらなくていいんだよ」
と、自然体で演じることを教えてくださいました。
心に残る言葉もたくさんいただきました。
「どうでもいいことは流行に従う。
重大なことは道徳に従う。
芸術は自分に従う」
「品行が悪いのは直せる。
品性のないのは直せない」
いずれも深く心に残りました。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 12th, 2013
金沢 景敏(プルデンシャル生命ライフプランナー)
『致知』2013年10月号
「致知随想」より
└─────────────────────────────────┘
私は平成二十四年度、プルデンシャル生命の
営業コンテスト個人保険部門で頂点に立ちました。
入社一年目、特に最後の数か月は
「物理的には不可能」と言われた大差を
覆しての勝利でした。
プルデンシャル生命に転職したのは昨年、
三十二歳の時。
前職では大手テレビ局でスポーツ中継などを担当し、
名刺を出せば誰もが会ってくれるというような
一見、何不自由ない日々を送っていました。
そんな私が固定給なし、経歴関係なし、
「いかに多くのお客様を満足させたか」で
すべてが決まる完全フルコミッションの
生命保険営業の世界に飛び込んだのは、
自分はこのままでいいのだろうかとの
思いがあったからでした。
周囲からするとなぜ?
という思いがあったでしょう。
京都大学在学中には
名将・水野彌一監督率いる
アメリカンフットボール部でプレーし、
卒業後も特に苦労なく大手企業へ就職。
しかし学生時代、口では日本一になると言いながら
満足に勝つこともできず、
厳しい練習から逃げていた自分がいました。
「完全燃焼できなかった」との後悔の念が
卒業後も拭えず、学歴や大手企業の
“看板”の中で生きるのではなく、
自分の力をもう一度がむしゃらに
試してみたいとの思いがあったのです。
また就職後、記者としてアスリートに接する中で、
選手を取り巻く厳しい現実にも直面しました。
若くして高給をもらう選手の多くは金銭感覚に乏しく、
引退後には厳しい生活になることも少なくありません。
引退後に彼らが安心して競技に打ち込める環境を
つくれないかと考えるようになっていました。
プルデンシャル生命の社員から
「一緒にやらないか」と
声をかけていただいたのはそんな時でした。
「フルコミッションの世界なら、
どこまでも自分の力を試すことができる。
また保険を通じてアスリートの手助けも
できるかもしれない」
と、すべてを抛ち、転職を決意したのです。
しかし、転職後の二か月はいくら電話をかけても、
もうこれ以上ないというほど断られる日々が続きました。
こちらの名前を名乗った途端、
「保険の営業ですか」と電話を切られてしまう……。
しかし、ある時、ふと手に取った
『鏡の法則』という本の中でこんな言葉に出合ったのです。
“あなたの人生の現実は、あなたの心を映し出した鏡”
自分が冷たい対応をされてきたのも、
逆の立場だったら同じことをしていたかもしれない。
そう思うと、いくらかは相手の気持ちが
理解できるようになった気がしました。
商談が失敗しても、アポが取れなくても
すべての原因は我にあり――。
自分がされて嫌なことは相手にもしない、
自分がされて嬉しいことを
とことんやっていこうと発想を変えました。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 11th, 2013
鳥濱 初代(富屋旅館三代目女将)
『致知』2013年10月号
特集「一言よく人を生かす」より
http://www.chichi.co.jp/monthly/201310_pickup.html#pick2
![01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/011.jpg) 鳥濱トメが富屋旅館を開業したのは昭和二十七年。
戦後、特攻隊員のご遺族や生き残られた方々が
知覧を訪れた時、泊まるところがないと困るだろうと、
隊員さんたちが憩いの場としていた離れを買い取り、
旅館にしたのです。
「ここは、生きれども生きられなかった人たちが
訪れていた場所。
何かを感じ、自分が明日生きるという力に変えてほしい」
トメはそう願い、旅館業の傍ら、
平和の語り部として、この離れで隊員さんとの
エピソードなどを語っていました。
ここではその一部をご紹介したいと思います。
* *
光山文博さんは厳しい訓練が続く中、
休みになると必ず富屋食堂を訪れていました。
しかし、隊員とは誰とも話さず、大人しくしている。
なんでこの子だけ独りぼっちなのだろうか。
トメは心配していました。
するとある日、光山さんはトメにこう告げたのです。
「僕、実は朝鮮人なんだ」
この方の母親は戦時中に亡くなり、
父親から日本男児として本望を遂げよと教育されたそうです。
「明日出撃なんだ。小母ちゃんだけだったよ、
朝鮮人の僕に分け隔てなく接してくれたのは。
お別れに僕の国の歌を歌っていいかな」
そう言って光山さんは帽子を深々と被り、
トメと共に祖国の歌『アリラン』を大声で涙ながらに歌いました。
「小母ちゃん、ありがとう。
みんなと一緒に出撃していけるなんて、
こんなに嬉しいことはないよ」
そう言い残して、飛び立っていったのが光山文博さん、
二十四歳なのです。
もう一人は、十九歳の中島豊蔵さん。
中島さんは右手を骨折していたため、
なかなか出撃の許可が下りませんでした。
しかし、いま行かなければ日本は負けてしまう。
その並々ならぬ思いで司令部に掛け合い、
ついに許可が出たのです。
出撃前夜、トメは骨折で長くお風呂に入れなかった
中島さんのために、せめて最後にこの子の背中を流そうと、
お風呂に入れてあげました。
ああ、この子ももういなくなるのか……。
そう思うと、トメの目に涙が溢れました。
しかし、涙を見せてしまうと、
中島さんの決意を鈍らせてしまう。
心を掻き乱してしまう。
トメは涙を堪えるため、とっさに身をかがめました。
「小母さん、どうしたんですか?」
「いや、お腹が痛くなって……」
そう誤魔化すと、中島さんは、
「それなら、僕たちを見送らなくていいですよ。
小母さんは自分の養生をなさってください」
明日飛び立つ自分の身よりも、
とっさについたトメの嘘にまで優しい心をかけてくれる。
そんな中島さんは翌朝、折れた右腕を
自転車のチューブで操縦桿に括りつけ出撃していったのです。
* *
特攻平和記念館などに飾られている
十代後半から二十代前半の彼らの顔写真を拝見すると、
実に立派で、清々しく輝いた眼をしていらっしゃる。
それはやはり、彼らの中にぶれない軸が
一本通っていたからなのだと思います。
トメは平和の語り部として語る時、
いつもこう言っていました。
「私は多くの命を見送った。
引き留めることも、慰めることもできなくて、
ただただあの子らの魂の平安を願うことしかできなかった。
だから、生きていってほしい。命が大切だ」
されど、書き残した物の中には
「善きことのみを念ぜよ。
必ず善きことくる。
命よりも大切なものがある。
それは徳を貫くこと」
とも記されています。
この言葉を見るにつけ、後の世の幸福を願って
命を賭した隊員さんたちの姿が思い起こされてなりません。
鳥濱トメが富屋旅館を開業したのは昭和二十七年。
戦後、特攻隊員のご遺族や生き残られた方々が
知覧を訪れた時、泊まるところがないと困るだろうと、
隊員さんたちが憩いの場としていた離れを買い取り、
旅館にしたのです。
「ここは、生きれども生きられなかった人たちが
訪れていた場所。
何かを感じ、自分が明日生きるという力に変えてほしい」
トメはそう願い、旅館業の傍ら、
平和の語り部として、この離れで隊員さんとの
エピソードなどを語っていました。
ここではその一部をご紹介したいと思います。
* *
光山文博さんは厳しい訓練が続く中、
休みになると必ず富屋食堂を訪れていました。
しかし、隊員とは誰とも話さず、大人しくしている。
なんでこの子だけ独りぼっちなのだろうか。
トメは心配していました。
するとある日、光山さんはトメにこう告げたのです。
「僕、実は朝鮮人なんだ」
この方の母親は戦時中に亡くなり、
父親から日本男児として本望を遂げよと教育されたそうです。
「明日出撃なんだ。小母ちゃんだけだったよ、
朝鮮人の僕に分け隔てなく接してくれたのは。
お別れに僕の国の歌を歌っていいかな」
そう言って光山さんは帽子を深々と被り、
トメと共に祖国の歌『アリラン』を大声で涙ながらに歌いました。
「小母ちゃん、ありがとう。
みんなと一緒に出撃していけるなんて、
こんなに嬉しいことはないよ」
そう言い残して、飛び立っていったのが光山文博さん、
二十四歳なのです。
もう一人は、十九歳の中島豊蔵さん。
中島さんは右手を骨折していたため、
なかなか出撃の許可が下りませんでした。
しかし、いま行かなければ日本は負けてしまう。
その並々ならぬ思いで司令部に掛け合い、
ついに許可が出たのです。
出撃前夜、トメは骨折で長くお風呂に入れなかった
中島さんのために、せめて最後にこの子の背中を流そうと、
お風呂に入れてあげました。
ああ、この子ももういなくなるのか……。
そう思うと、トメの目に涙が溢れました。
しかし、涙を見せてしまうと、
中島さんの決意を鈍らせてしまう。
心を掻き乱してしまう。
トメは涙を堪えるため、とっさに身をかがめました。
「小母さん、どうしたんですか?」
「いや、お腹が痛くなって……」
そう誤魔化すと、中島さんは、
「それなら、僕たちを見送らなくていいですよ。
小母さんは自分の養生をなさってください」
明日飛び立つ自分の身よりも、
とっさについたトメの嘘にまで優しい心をかけてくれる。
そんな中島さんは翌朝、折れた右腕を
自転車のチューブで操縦桿に括りつけ出撃していったのです。
* *
特攻平和記念館などに飾られている
十代後半から二十代前半の彼らの顔写真を拝見すると、
実に立派で、清々しく輝いた眼をしていらっしゃる。
それはやはり、彼らの中にぶれない軸が
一本通っていたからなのだと思います。
トメは平和の語り部として語る時、
いつもこう言っていました。
「私は多くの命を見送った。
引き留めることも、慰めることもできなくて、
ただただあの子らの魂の平安を願うことしかできなかった。
だから、生きていってほしい。命が大切だ」
されど、書き残した物の中には
「善きことのみを念ぜよ。
必ず善きことくる。
命よりも大切なものがある。
それは徳を貫くこと」
とも記されています。
この言葉を見るにつけ、後の世の幸福を願って
命を賭した隊員さんたちの姿が思い起こされてなりません。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 10th, 2013
吉田 栄勝(吉田沙保里選手の父/
一志ジュニアレスリング教室代表)
『致知』2013年4月号
特集「渾身満力(こんしんまんりき)」より
![yoshidasaori[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/yoshidasaori1.jpg) 以前うちの教室に、一万人に一人ともいえる逸材がいましてね。
本当に、格闘技をやるために生まれてきたような子で、
出る大会出る大会、全部優勝していきました。
そして小学生の時、柔道に転向し、
それも日本一になって
もう一度レスリングに戻ってきたんですよ。
ところが彼は、俺は日本一だという偉そうな顔をしていて、
態度が悪いものでね。
あれがもうちょっと素直だったら、
五輪も出られるんだろうなと思うんですが。
そういう選手は他にもいて、教えたことはすぐ覚えるし、
教えなくても相手がやっているのを上手に真似る。
ただその子が本当に強くなるかというと、
やっぱり最後は素直でなきゃダメですね、人間。
「はい」という返事や
「すみません」「ありがとう」という言葉を
ちゃんと知っている人間でないと。
俺は強いんだ、なんて偉そうにしている人間は
もう人が相手にしない。
小さい頃からそういうことをしっかり叩き込んでおかないと、
大きくなってから必ず損をします。
私は(娘の)沙保里によくこんな話をしてきました。
「もしおまえが途中で負けてしまったら、
おまえに負けた子がまた泣いてしまうぞ。
だからおまえに負けた子の分まで勝たなきゃいけない」と。
一方、女房は二〇〇八年に連勝記録が百十九で途切れた時、
「いままでおまえが勝たせてもらったその裏で、
他の子は皆泣いていたんだよ。
一度負けたくらいでクヨクヨするな」
と言いました。
連勝の記録ももちろん大事ですが、
やっぱり人間、負ける悔しさというのを覚えていってこそ、
本当の成長へと繋がるのだと思います。
以前うちの教室に、一万人に一人ともいえる逸材がいましてね。
本当に、格闘技をやるために生まれてきたような子で、
出る大会出る大会、全部優勝していきました。
そして小学生の時、柔道に転向し、
それも日本一になって
もう一度レスリングに戻ってきたんですよ。
ところが彼は、俺は日本一だという偉そうな顔をしていて、
態度が悪いものでね。
あれがもうちょっと素直だったら、
五輪も出られるんだろうなと思うんですが。
そういう選手は他にもいて、教えたことはすぐ覚えるし、
教えなくても相手がやっているのを上手に真似る。
ただその子が本当に強くなるかというと、
やっぱり最後は素直でなきゃダメですね、人間。
「はい」という返事や
「すみません」「ありがとう」という言葉を
ちゃんと知っている人間でないと。
俺は強いんだ、なんて偉そうにしている人間は
もう人が相手にしない。
小さい頃からそういうことをしっかり叩き込んでおかないと、
大きくなってから必ず損をします。
私は(娘の)沙保里によくこんな話をしてきました。
「もしおまえが途中で負けてしまったら、
おまえに負けた子がまた泣いてしまうぞ。
だからおまえに負けた子の分まで勝たなきゃいけない」と。
一方、女房は二〇〇八年に連勝記録が百十九で途切れた時、
「いままでおまえが勝たせてもらったその裏で、
他の子は皆泣いていたんだよ。
一度負けたくらいでクヨクヨするな」
と言いました。
連勝の記録ももちろん大事ですが、
やっぱり人間、負ける悔しさというのを覚えていってこそ、
本当の成長へと繋がるのだと思います。
Posted by mahoroba,
in 人生論
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
9月 9th, 2013

4日の朝、道新の朝刊一面を見てビックリ!!!
まほろば自然農園の「ローザビアンカ」が、
カラーで色鮮やかにアップされていたからだ。

今朝のミーティングでも話したのだが、
とに角、農業部門の、ことに今年の畑は、厳しい出発だった。
赤字に次ぐ赤字で、採算が取れない、人材が揃わない、
ないない続きでスタートし、今もなおないない尽くしなのだ。
新規就農者二人は、農業経験のない素人さんで、
経験者はチーフの福田君と家内だけだ。
それで6町歩、100種類以上の作物を栽培することは、
無謀としか言いようがない。
だから、3月から、家内は休みを一日も取っていない。
つまり全く日曜日がないのだ。
そんな中で、朝暗い4時5時から働き出して止めない。

今朝市場で、ある仲買さんの社長から
「あんまり、奥さんこき使うんでないヨ」と、
冗談半分、真実半分の笑い話を聞かされたが、半ば本当かもしれない。
周りからは何時までも厳しい経営を批判され、
それでもまほろばで作ることの大切さ、
その意味と意義を家内は訴えて、自らが骨身を惜しまずに引っ張って来た。

農園は<まほろばの生命線>と思い定めて微塵も揺らがない。
新しい光の道が見えるようがんばり続けた。
一本の大根、一把の菜っ葉は売るのも買うのも食べるのも一瞬だが、
それを作る陰の努力は、筆舌に尽くし難い。

だから、今回は、神様の農園のスタッフへのプレゼントかもしれない。
「ありがとう!みんな」「ありがとう、かあさん!」
今回は身内だが、てらいもなく感謝したい。
不意に戴いたこの好機を活かして、明日に繋げたい。

しかし、こういう感慨は家内にとって、世俗的なもので、
掲載云々は、全く意に介していない。
そんな大げさなことより、家族やお客様から、
「美味しかったヨ!」との一言の方が、よほど嬉しいという。
そんな人である。
Posted by mahoroba,
in 自然農園
コメント投稿はこちらからどうぞ♪→まだコメントがありません。 »
![f0054757_19563521[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/f0054757_195635211.jpg) 私の場合は日々生きていること自体に勇気が必要です。
見えなくて、聞こえない世界にいるので、
未知の惑星にいるようなものでいつ何が起こるか分からない。
ただそうした道を歩んでくる中で、
自分が盲ろうになった時、
到達した一つの思いがあるんです。
十八歳の一月から三か月間で、
全く聞こえなくなっていくわけですが、
その過程で、自分は目が見えないのに、
その上どうして、さらに耳までが
聞こえなくなるんだろうかと考えました。
運命の理不尽さについて、
あるいは僕が何か罪を犯したんだろうか、
何か悪いことをしたんだろうか、
なぜ自分はこんな状況になっているんだろうか
などといろいろ考えたんです。
そして最終的に私が思い至ったのは
こんな考えでした。
なぜこんな状態になったかは分からないけれども、
自分は自分の力で生きているわけではない。
人間の理解の及ばない、
大いなる何ものかが私たちを生かしているとすれば、
僕がいま経験しているしんどさ、
この苦悩というのも、その存在が与えたものであろうから、
この苦しい状況にも何かしらの意味があるんじゃないか――。
そしてこの苦悩をくぐることによって
人生が輝くのではないかと、思おうとしたんです。
しんどい状況を経験することが
自分の人生の肥やしになるんじゃないかと。
要するに肥溜めみたいなものですね。
肥溜めのままだったら役に立たないけれども、
それを畑に撒くことによって肥やしとなり、
実りをもたらすかもしれない。
そして同じ頃次のような手紙を
友達に書き送っているんです。
「今俺は静かに思う。
この苦渋の日々が俺の人生の中で
何か意義がある時間であり、
俺の未来を光らせるための土台として、
神があえて与えたもうたものであることを信じよう。
信仰なき今の俺にとってできることは、
ただそれだけだ。
俺にもし使命というものが、生きるうえでの
使命というものがあるとすれば、
それは果たさねばならない。
そしてそれをなすことが必要ならば、
この苦しみのときをくぐらねばならぬだろう。
(中略)
俺はそう思ったとき、突然、今まで脳の奥深く、
遠いところで、この両耳の六種類の耳鳴りの
空間の向こうで回っていた、
半透明の歯車が回るのを止めたように感じた」
私の場合は日々生きていること自体に勇気が必要です。
見えなくて、聞こえない世界にいるので、
未知の惑星にいるようなものでいつ何が起こるか分からない。
ただそうした道を歩んでくる中で、
自分が盲ろうになった時、
到達した一つの思いがあるんです。
十八歳の一月から三か月間で、
全く聞こえなくなっていくわけですが、
その過程で、自分は目が見えないのに、
その上どうして、さらに耳までが
聞こえなくなるんだろうかと考えました。
運命の理不尽さについて、
あるいは僕が何か罪を犯したんだろうか、
何か悪いことをしたんだろうか、
なぜ自分はこんな状況になっているんだろうか
などといろいろ考えたんです。
そして最終的に私が思い至ったのは
こんな考えでした。
なぜこんな状態になったかは分からないけれども、
自分は自分の力で生きているわけではない。
人間の理解の及ばない、
大いなる何ものかが私たちを生かしているとすれば、
僕がいま経験しているしんどさ、
この苦悩というのも、その存在が与えたものであろうから、
この苦しい状況にも何かしらの意味があるんじゃないか――。
そしてこの苦悩をくぐることによって
人生が輝くのではないかと、思おうとしたんです。
しんどい状況を経験することが
自分の人生の肥やしになるんじゃないかと。
要するに肥溜めみたいなものですね。
肥溜めのままだったら役に立たないけれども、
それを畑に撒くことによって肥やしとなり、
実りをもたらすかもしれない。
そして同じ頃次のような手紙を
友達に書き送っているんです。
「今俺は静かに思う。
この苦渋の日々が俺の人生の中で
何か意義がある時間であり、
俺の未来を光らせるための土台として、
神があえて与えたもうたものであることを信じよう。
信仰なき今の俺にとってできることは、
ただそれだけだ。
俺にもし使命というものが、生きるうえでの
使命というものがあるとすれば、
それは果たさねばならない。
そしてそれをなすことが必要ならば、
この苦しみのときをくぐらねばならぬだろう。
(中略)
俺はそう思ったとき、突然、今まで脳の奥深く、
遠いところで、この両耳の六種類の耳鳴りの
空間の向こうで回っていた、
半透明の歯車が回るのを止めたように感じた」



![img_1200998_34382144_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/img_1200998_34382144_01.jpg) 小津安二郎監督とは会社が違ったので、
出演したのは『彼岸花』の一本だけでしたけれども、
人間的魅力に溢れたとても素晴らしい方でした。
それまで自分の持っているものを
フルに出そうとしていた私に、
小津安二郎監督とは会社が違ったので、
出演したのは『彼岸花』の一本だけでしたけれども、
人間的魅力に溢れたとても素晴らしい方でした。
それまで自分の持っているものを
フルに出そうとしていた私に、
![01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/011.jpg) 鳥濱トメが富屋旅館を開業したのは昭和二十七年。
戦後、特攻隊員のご遺族や生き残られた方々が
知覧を訪れた時、泊まるところがないと困るだろうと、
隊員さんたちが憩いの場としていた離れを買い取り、
旅館にしたのです。
「ここは、生きれども生きられなかった人たちが
訪れていた場所。
何かを感じ、自分が明日生きるという力に変えてほしい」
トメはそう願い、旅館業の傍ら、
平和の語り部として、この離れで隊員さんとの
エピソードなどを語っていました。
ここではその一部をご紹介したいと思います。
* *
光山文博さんは厳しい訓練が続く中、
休みになると必ず富屋食堂を訪れていました。
しかし、隊員とは誰とも話さず、大人しくしている。
なんでこの子だけ独りぼっちなのだろうか。
トメは心配していました。
するとある日、光山さんはトメにこう告げたのです。
「僕、実は朝鮮人なんだ」
この方の母親は戦時中に亡くなり、
父親から日本男児として本望を遂げよと教育されたそうです。
「明日出撃なんだ。小母ちゃんだけだったよ、
朝鮮人の僕に分け隔てなく接してくれたのは。
お別れに僕の国の歌を歌っていいかな」
そう言って光山さんは帽子を深々と被り、
トメと共に祖国の歌『アリラン』を大声で涙ながらに歌いました。
「小母ちゃん、ありがとう。
みんなと一緒に出撃していけるなんて、
こんなに嬉しいことはないよ」
そう言い残して、飛び立っていったのが光山文博さん、
二十四歳なのです。
もう一人は、十九歳の中島豊蔵さん。
中島さんは右手を骨折していたため、
なかなか出撃の許可が下りませんでした。
しかし、いま行かなければ日本は負けてしまう。
その並々ならぬ思いで司令部に掛け合い、
ついに許可が出たのです。
出撃前夜、トメは骨折で長くお風呂に入れなかった
中島さんのために、せめて最後にこの子の背中を流そうと、
お風呂に入れてあげました。
ああ、この子ももういなくなるのか……。
そう思うと、トメの目に涙が溢れました。
しかし、涙を見せてしまうと、
中島さんの決意を鈍らせてしまう。
心を掻き乱してしまう。
トメは涙を堪えるため、とっさに身をかがめました。
「小母さん、どうしたんですか?」
「いや、お腹が痛くなって……」
そう誤魔化すと、中島さんは、
「それなら、僕たちを見送らなくていいですよ。
小母さんは自分の養生をなさってください」
明日飛び立つ自分の身よりも、
とっさについたトメの嘘にまで優しい心をかけてくれる。
そんな中島さんは翌朝、折れた右腕を
自転車のチューブで操縦桿に括りつけ出撃していったのです。
* *
特攻平和記念館などに飾られている
十代後半から二十代前半の彼らの顔写真を拝見すると、
実に立派で、清々しく輝いた眼をしていらっしゃる。
それはやはり、彼らの中にぶれない軸が
一本通っていたからなのだと思います。
トメは平和の語り部として語る時、
いつもこう言っていました。
「私は多くの命を見送った。
引き留めることも、慰めることもできなくて、
ただただあの子らの魂の平安を願うことしかできなかった。
だから、生きていってほしい。命が大切だ」
されど、書き残した物の中には
鳥濱トメが富屋旅館を開業したのは昭和二十七年。
戦後、特攻隊員のご遺族や生き残られた方々が
知覧を訪れた時、泊まるところがないと困るだろうと、
隊員さんたちが憩いの場としていた離れを買い取り、
旅館にしたのです。
「ここは、生きれども生きられなかった人たちが
訪れていた場所。
何かを感じ、自分が明日生きるという力に変えてほしい」
トメはそう願い、旅館業の傍ら、
平和の語り部として、この離れで隊員さんとの
エピソードなどを語っていました。
ここではその一部をご紹介したいと思います。
* *
光山文博さんは厳しい訓練が続く中、
休みになると必ず富屋食堂を訪れていました。
しかし、隊員とは誰とも話さず、大人しくしている。
なんでこの子だけ独りぼっちなのだろうか。
トメは心配していました。
するとある日、光山さんはトメにこう告げたのです。
「僕、実は朝鮮人なんだ」
この方の母親は戦時中に亡くなり、
父親から日本男児として本望を遂げよと教育されたそうです。
「明日出撃なんだ。小母ちゃんだけだったよ、
朝鮮人の僕に分け隔てなく接してくれたのは。
お別れに僕の国の歌を歌っていいかな」
そう言って光山さんは帽子を深々と被り、
トメと共に祖国の歌『アリラン』を大声で涙ながらに歌いました。
「小母ちゃん、ありがとう。
みんなと一緒に出撃していけるなんて、
こんなに嬉しいことはないよ」
そう言い残して、飛び立っていったのが光山文博さん、
二十四歳なのです。
もう一人は、十九歳の中島豊蔵さん。
中島さんは右手を骨折していたため、
なかなか出撃の許可が下りませんでした。
しかし、いま行かなければ日本は負けてしまう。
その並々ならぬ思いで司令部に掛け合い、
ついに許可が出たのです。
出撃前夜、トメは骨折で長くお風呂に入れなかった
中島さんのために、せめて最後にこの子の背中を流そうと、
お風呂に入れてあげました。
ああ、この子ももういなくなるのか……。
そう思うと、トメの目に涙が溢れました。
しかし、涙を見せてしまうと、
中島さんの決意を鈍らせてしまう。
心を掻き乱してしまう。
トメは涙を堪えるため、とっさに身をかがめました。
「小母さん、どうしたんですか?」
「いや、お腹が痛くなって……」
そう誤魔化すと、中島さんは、
「それなら、僕たちを見送らなくていいですよ。
小母さんは自分の養生をなさってください」
明日飛び立つ自分の身よりも、
とっさについたトメの嘘にまで優しい心をかけてくれる。
そんな中島さんは翌朝、折れた右腕を
自転車のチューブで操縦桿に括りつけ出撃していったのです。
* *
特攻平和記念館などに飾られている
十代後半から二十代前半の彼らの顔写真を拝見すると、
実に立派で、清々しく輝いた眼をしていらっしゃる。
それはやはり、彼らの中にぶれない軸が
一本通っていたからなのだと思います。
トメは平和の語り部として語る時、
いつもこう言っていました。
「私は多くの命を見送った。
引き留めることも、慰めることもできなくて、
ただただあの子らの魂の平安を願うことしかできなかった。
だから、生きていってほしい。命が大切だ」
されど、書き残した物の中には
![yoshidasaori[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/09/yoshidasaori1.jpg) 以前うちの教室に、一万人に一人ともいえる逸材がいましてね。
本当に、格闘技をやるために生まれてきたような子で、
出る大会出る大会、全部優勝していきました。
そして小学生の時、柔道に転向し、
それも日本一になって
もう一度レスリングに戻ってきたんですよ。
ところが彼は、俺は日本一だという偉そうな顔をしていて、
態度が悪いものでね。
あれがもうちょっと素直だったら、
五輪も出られるんだろうなと思うんですが。
そういう選手は他にもいて、教えたことはすぐ覚えるし、
教えなくても相手がやっているのを上手に真似る。
ただその子が本当に強くなるかというと、
以前うちの教室に、一万人に一人ともいえる逸材がいましてね。
本当に、格闘技をやるために生まれてきたような子で、
出る大会出る大会、全部優勝していきました。
そして小学生の時、柔道に転向し、
それも日本一になって
もう一度レスリングに戻ってきたんですよ。
ところが彼は、俺は日本一だという偉そうな顔をしていて、
態度が悪いものでね。
あれがもうちょっと素直だったら、
五輪も出られるんだろうなと思うんですが。
そういう選手は他にもいて、教えたことはすぐ覚えるし、
教えなくても相手がやっているのを上手に真似る。
ただその子が本当に強くなるかというと、