佐藤可士和(クリエイティブディレクター)
※『致知』2012年9月号
特集「本質を見抜く」より
![ph01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/11/ph011.jpg)
――ヒット商品を生む秘訣のようなものはありますか。
商品の本質を見抜くことが肝要です。
本質を見抜くとはある表層だけではなく、
いろいろな角度から物事を観察し、
立体的に理解するということです。
そのためのアプローチは様々ありますが、
中でも僕が最も重要だと思うのは、
「前提を疑う」ということです。
――前提を疑う、ですか。
これは僕のクリエイティブワークの原点ともいえる
フランスの美術家、マルセル・デュシャンから学んだことです。
20世紀初頭、皆が一所懸命絵を描いて、
次は何派だとか言って競っている時に、
デュシャンはその辺に売っている男性用の小便器にサインをして、
それに「泉」というタイトルをつけて、美術展に出したんです。
キャンバスの中にどんな絵を描くのか
ということが問われていた時代に、
いや、そもそも絵を描く必要があるのかと。
見る人にインパクトを与えるために、
敢えて便器という鑑賞するものとは程遠いものを提示して、
アートの本質とは何かをズバッと示した。
つまり、そういう行為自体が作品であると。
――まさに前提を覆したのですね。
そうです。
ただ、必ずしも前提を否定することが
目的ではありません。
一度疑ってみたけど、
やはり正しかったということも十分あり得るでしょう。
大事なのは、「そもそも、これでいいのか?」と、
その前提が正しいかどうかを一度検証してみることです。
過去の慣習や常識にばかり囚われていては、
絶対にそれ以上のアイデアは出てきませんから。
――前提を疑わなければ、よいアイデアは生まれないと。
はい。あと一つ挙げるとすれば、
「人の話を聞く」ことが本質を見抜く要諦だといえます。
相手の言わんとする本意をきちんと聞き出す。
僕はそれを問診と言っていますが、
プロジェクトを推進していく際は
この問診に多くの時間を割いています。
じっくり悩みを聞きながら、
相手の抱えている問題を洗い出し、
取り組むべき課題を見つけていくのです。
――問診するにあたって、何か心掛けていることはありますか。
自分が常にニュートラルでいること、それが重要です。
邪念が入るとダメですね。
人間なので好き、嫌いとか気性の合う、合わないは
当然あるじゃないですか。
ただ、合わない人の言っていることでも
正しければその意見に従うべきですし、
仲のいい人でも間違っていれば「違いますよね」と言うべきでしょう。
感情のままに行動するのではなく、
必要かどうかを判断の拠り所とする。
いつも本質だけを見ていようと思っていれば、
判断を間違えることはありません。
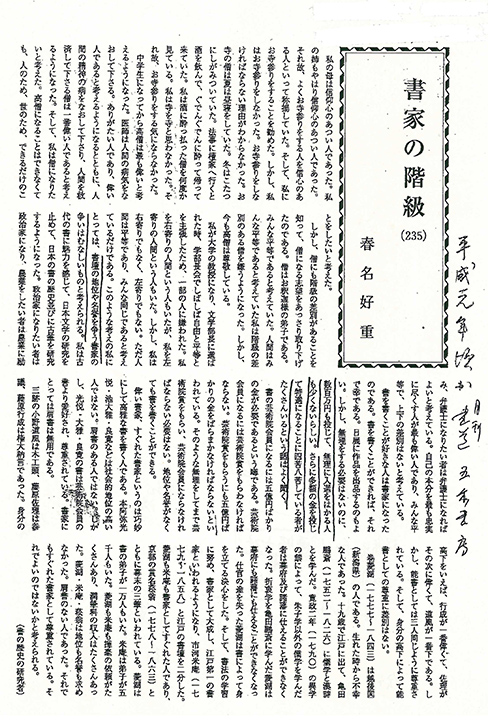
![0078[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/11/00781.jpg)
![ph01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/11/ph011.jpg)





















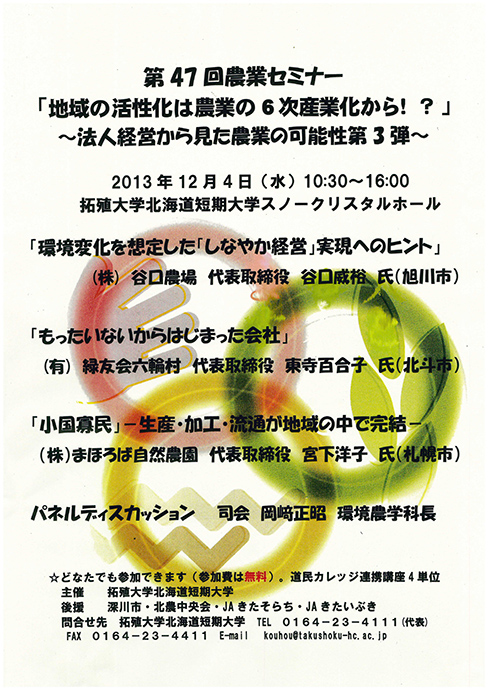

![1103003918[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/11/11030039181.jpg)



![2013_11_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/11/2013_11_s11.jpg)