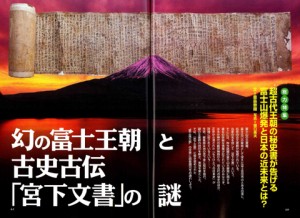![6a01287589fbf4970c01348671c037970c[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/6a01287589fbf4970c01348671c037970c1-225x300.jpg)
二村 知子
(隆祥館書店 取締役営業部部長)
※肩書きは『致知』掲載当時のものです
…………………………………………………………………………………………………
「お客と会話する書店」として新聞に紹介された我が家の店は、
大阪の心斎橋から地下鉄で十分ほどの距離にあります。
父が昭和二十七年に創業した、
わずか十五坪の家族経営の小さな街の本屋です。
出版不況に加え、大型書店やネット書店が台頭する中、
地域の小規模書店には非常に厳しい状況が続いています。
しかしありがたいことに当店には、
「本は隆祥館で買うと決めているから」と
大型店で見つけた書籍をわざわざ購入しに来てくださる方や、
遠く奈良から足を運んでくださる方などがおられます。
私が書店員になったのは、十六年前のことでした。
シンクロナイズドスイミングの日本代表選手として活動した後、
コーチ業に専念し非常にやりがいを感じていましたが、
経済的な自立は困難でした。
悩んだ末に、家業を継ぐことを決意したのです。
しかし当時の書店経営は曲がり角に来ていました。
コンビニエンスストアで雑誌が購入できる、
ネット書店が広がる、子供たちはゲームに夢中になるなど、
書店を取り巻く環境は厳しさを増す一方。
我が家の売り上げも下がり始めていました。
「両親が一所懸命築いてきた店を守りたい。
コンビニに負けたくない。
どうしたらうちで本を買いたいと思ってもらえるのだろう……」
必死に考えた結果、小規模店の利点を生かして
お客様のニーズに応えられるよう、
コミュニケーションを大切にすることにしました。
そのため、本をお求めになった方のお顔と
購入書籍を覚えるように努めました。
そうすることで、
「この前、あの雑誌を買ってくださった方だ」と
気づいた場合にはその最新号をお勧めできます。
また、「この本はあの方が好みそうだ」と思えば
注文がなくとも仕入れ、次回来店時にご紹介できます。
「この間紹介してくれた本、おもしろかったですよ」
と言ってくださる方も増え始め、会話が弾むことで、
お客様との繋がりが強くなっていきました。
時々店の手伝いをしてくれる学生の言葉に、
感動を覚えたこともあります。
無償では申し訳ないのでアルバイトをお願いしたところ、
断られる。
不思議に思うと、
「地方から出てきて、大阪の人はみな冷たいと思っていたけど、
この本屋で大阪の人の温かさに初めて触れてほっとしました。
元気になれるから手伝っているだけで、お金なんていらないです」
と言われました。
お客様を大切にしたい一心で、
時には卸問屋である出版取次を通さずに
直接出版社に注文を依頼することもあります。
いまでは小規模店に対しても
取次は柔軟に対応してくれますが、
十年ほど前は厳しい壁があり、
それを思い知らされる出来事がありました。
一大ブームになったあるベストセラーの
追加注文を取次が受けてくれず、
東京本社にお願いしても全く相手にしてもらえない。
当時ベストセラーは大型店に優先的に配本され、
中小の書店は入手困難な状況にありました。
お客様が欲しい本を手に入れられない。
あまりの悔しさに思わず涙がこみ上げてきました。
見かねた父から叱咤激励を受けても、
どう手を打てばよいのか分からない。
ある日、取次主催の講演会があることを知り、
藁にもすがる思いで参加しました。
そこで出版業界専門紙の発行人の話を聴き、
出版社の中には小規模店に対しても
大規模店と同様に対応してくれる人がいることを知ったのです。
なんとかなるかもしれない。
そう思った私は、初対面にもかかわらず
講演者にそのような方の紹介をお願いしました。
一か月後、ある大手出版社の営業部長が手紙をくださり、
その後やり取りを続けました。
その方はご自身の会社だけでなく、
出版業界全体のことを常々考えておられ、
そのためには全国に存在する街の小さな本屋を
守っていかなければならないという強い思いを持っておられました。
私はこんなことをお願いしてよいものだろうかと思い悩んだ末、
その方に直接電話をかけ、ベストセラーの注文を依頼しました。
すると当方の事情を理解し、
一定数を融通してくださったのです。
以来、出版社の営業の方と積極的に人脈をつくるようにし、
直接注文を増やしていきました。
販売実績を地道に積み上げていったことで
取次からの配本も受けやすくなりました。
ある人気雑誌の場合、お客様のために在庫が切れないよう、
売れ残りは買い取る覚悟で出版社に
追加注文をお願いし続けました。
取次からの毎月の仕入れ数も増加し、
数か月後には売り場面積百倍近い大型店を抑え、
関西地区で売り上げトップになったこともあります。
私の好きな言葉に、
“人を動かすのはお金ではなく、そこに傾ける情熱だ”
というものがあります。
「うちの店を選んでくださったお客様に喜んでいただきたい」。
その思いで、手探りながらも必死に取り組んでいるうちに、
手を差し伸べてくださる方が現れました。
お客様に助けていただいたことも数え切れません。
最近は電子書籍も本格的に普及し始め、
いずれ街の本屋はなくなるといわれたこともあります。
内心非常に不安ですが、希望を失ってはいません。
シンクロの選手時代、井村雅代元日本代表監督から、
「絶対に諦めてはいけない」と身に染みるほど
教えていただいたからです。
最近読んだ記事の中に、大規模店しか残らないといわれた
ニューヨークの書店の中で
個性ある街の小規模店にこそ元気がある、
というものがありました。
そういう書店を目指したい――。
お客様との距離が近い特長を生かし、
きょうもお一人おひとりに
本の魅力や読書の素晴らしさをお伝えしていきます。
![web-TB-6-nimura[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/web-TB-6-nimura1.jpg) 『致知』2011年3月号「致知随想」
『致知』2011年3月号「致知随想」
![photo_4[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/photo_41.jpg)
![TKY200911020071[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/TKY2009110200711.jpg)
![6a01287589fbf4970c01348671c037970c[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/6a01287589fbf4970c01348671c037970c1-225x300.jpg)
![web-TB-6-nimura[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/web-TB-6-nimura1.jpg)

![image3[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/image31-300x224.jpg)
![image2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/image21-300x224.jpg)

![175[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/1751-300x195.jpg)
![topix201109heuge_r19_c1_s1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/topix201109heuge_r19_c1_s11-186x300.jpg)
![01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/011.jpg)
![THM20090509-0001431-0001473[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/THM20090509-0001431-00014731.jpg)