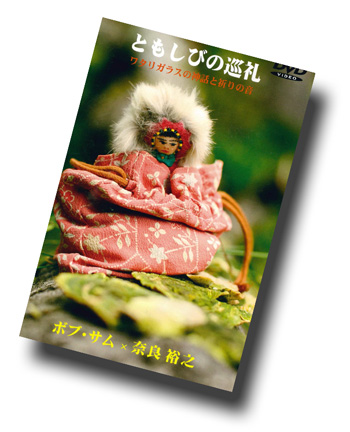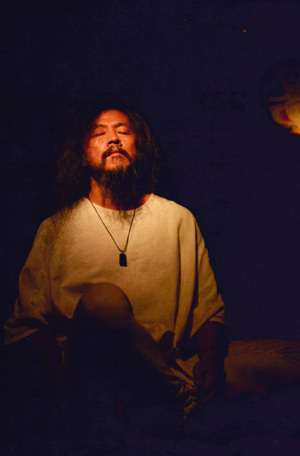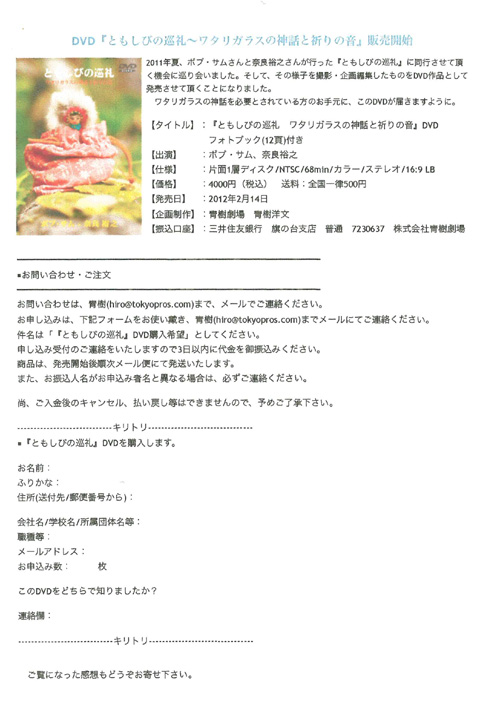「仕事は自ら探し出すもの」
3月 3rd, 2012 『致知』2012年3月号
連載「20代をどう生きるか」より
────────────────────────────────────
私がリコーに就職したのは一九六六年。
オリンピック景気を最後に日本の高度経済成長期が終わり、
「証券不況」という大きな不況の真っ只中だった。
そもそもなぜリコーを希望したかというと、
私は小さい頃から「これはなぜ動くのか」とその構造が知りたくて、
買ってもらったばかりのおもちゃの解体に
熱中するような子供だった。
その好奇心が高じて理工学部へ進学。
そして学生時代に熱中したのはカメラだった。
必然的に就職先は製造業で、
特にカメラを製造している企業を希望して、
リコーに行き着いたのだ。
ところが、面接時に衝撃的なことを言われた。
「いまほとんどカメラはやっていないよ。
いまのうちの主力は複写機(コピー機)だ」
「???」
当時、複写といえばガリ版刷りで、
私は複写機そのものがどんなものか分からなかったが、
咄嗟に「複写機でもいいです」と答えた。
さらに「なぜこの時期にリコーなんだ? うちは無配だよ」
と言われた。その瞬間、「無配」が何かが思いつかず、
「いや“無敗”は望むところです」と答えた。
いま振り返ると、よく通ったものだと思う。
そうして最初に配属されたのは原価管理課という部門だった。
しかし、不況の真っ只中、会社も無配の状態である。
上司に言われたのは「おまえたちにやる仕事はない」と
いうことだった。
最初こそ仕事がなくて楽だと思ったが、
三か月も経つと何もする仕事がないというのは
こんなにつらいものなのかと身に沁みて感じた。
他の部署の人たちが仕事をしていることへの焦り。
また、もっと本質的な部分で、
自分は会社や社会に何も貢献できていないという
「役割」のなさへの焦りがあった。
後々振り返って、社会人のスタート段階で
「仕事があるありがたさ」
「する仕事のないつらさ」
を体感できたのは幸せだったと思う。
* *
さて、そこで私は
「こうなったら、自分で仕事を探そう」と決意した。
原価管理課は、製品の原価を計算し、
コストダウンを提案して実践する部署だった。
提案は誰に対して行うのか、我われの提案を
利用する人たちにとってそれは十分な情報かどうか、
もっと欲しい情報はないのか、ヒアリングに向かったのである。
提案の利用者は、開発、設計、生産部門だから、
各部署を回ってみると次第に自分がすべき仕事が見えてきた。
複写機を取ってみても、いくつもの製品があり、
それぞれの製品間で部品が類似しながらも
微妙に違うものを使っていることに気がついた。
「本当に違う必要があるのか」
「コストアップの原因になってはいないか」……。
いまならコンピュータで類似部品一覧を管理しているだろうが、
あの当時、技術や設計の人間は手間隙かかる
類似部品のリスト化に手をつけていなかった。
私は五か月間、倉庫にこもって部品図面を種類ごとに分類。
材質や形状、原価などを加えたリストを作成し、設計部署に渡した。
その後、改善したほうがいい部分を指摘してもらい、
どんどんブラッシュアップしていった。
すると、現場は「部品を探す手間が省けた」と
重宝してくれる一方で、同じような形状であれば
一番安い部品を選ぶようになり、
大きなコストダウンに繋がったのである。
この経験から私が若い人たちに伝えたいことは、
「仕事は上司から与えられるものではなく、
自分で探し出すもの」
ということだ。
自分の仕事のアウトプットを利用するお客様は誰なのかを考え、
その人たちの役に立つことを探して実行すれば、
必ず成果となって現れる。
すなわち、それは自主自立、自己責任の全うということであり、
いま日本全体で最も求められていることではないだろうか。
![01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/0111.jpg)


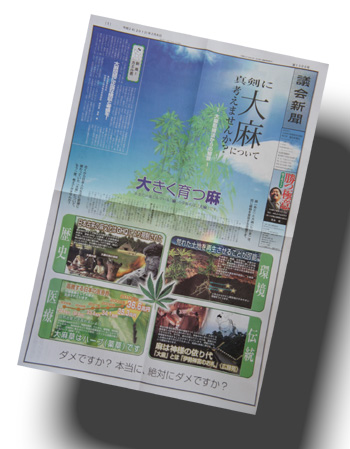





![65b28267736bc3ba0d6eb68c7458915e[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/03/65b28267736bc3ba0d6eb68c7458915e1-150x150.jpg)
![TOIYOSIO[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/TOIYOSIO1.jpg)


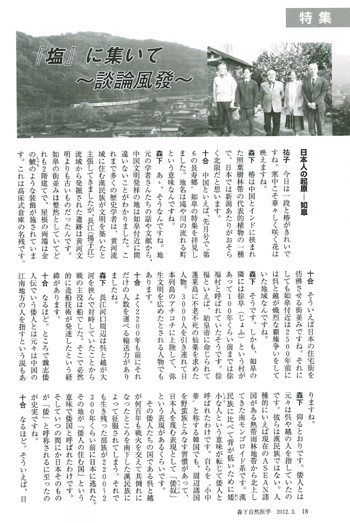
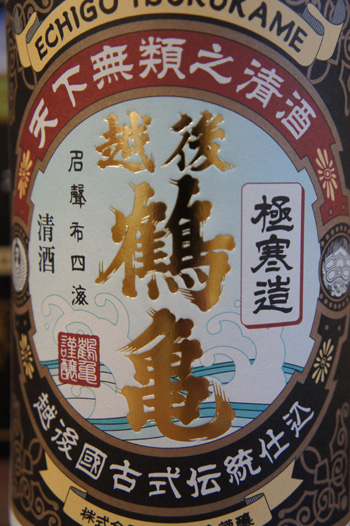
![intro001[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/intro0011.jpg)
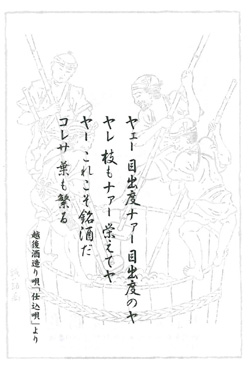
![turukame nihonn[]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/turukame-nihonn.jpg)
![fukushima[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/fukushima1.jpg)
![nodomyakuryu_img02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/02/nodomyakuryu_img021-150x150.jpg)