「当然の限度の高い社員。青天井型社員」
10月 6th, 2011
『致知』1997年5月号
特集「リーダーシップの本質」より
※肩書きは掲載当時です。
────────────────────────────────────
(長谷川社長は十数年で青汁を年商131憶円<末端ベース>の事業に
育てられたわけですが、そのエネルギーの源泉はどこにあるのですか)
これもまた難しい質問ですね(笑)。
先程いったように、私は仕事にのめり込む人間なんです。
でないといい仕事ができないと思っている。
経営計画書にも、切望する社員の人間像として
そう明記しています。
第一は、仕事に対して、こうしたいああしたいという
強い「念」を持っている人。
第二に、その仕事を成し遂げる「パワー」のある人。
第三に、その仕事に「のめり込む」人。
この他に何項目かあるのですが、例えば、
「当然の限度の高い社員。青天井型社員」
というのがある。
たとえば、ソフトバンクという会社は
翌日決算のできる会社です。
普通は翌月に月次決算が出ない会社がいくらでもある。
そんな会社で翌日決算を出せといっても、
そんなことは無理ですとなる。
しかし、社長の私はいろんな会社を見てますから、
そんなことは「当然できる」という。
それが「当然の限度が高い」ということです。
その限度は上層部の人間ほど高くなっていくもので、
社長が一番高い。
社員にも「当然の限度」を高くしていってもらいたい。
そして最後には、何でもできるという
「青天井型の社員」になってもらいたい。
* *
そしてもう一つ私のエネルギーの元といえば、
くよくよしないことです。
中村天風(てんぷう)先生の本にこういうのがあります。
虎に追いかけられて木に登ったら、
木の上から大蛇が出てきた。
枝に逃げたら、ポキッと枝が折れた。
下は断崖絶壁。
蔓に飛び移ると、ポリポリと音がする。
見上げるとリスが蔓を噛んでいる。
「さあ、どうする」と聞かれた天風先生は何と答えたか。
先生は「落ちてから考える」 (笑)とおっしゃったそうです。
私も「落ちてから考える」タイプの人間なんです。
頭には「いま、ここ」しかない。
過去の過ちも功績も
「そりゃそうだろう。それでよかったし、当然なんだ」と認め、
受け入れ、悲観せず、有頂天にもならない。
また、将来のことは、戦略や予測は真剣に考えるが、
思い煩うことはしない。
過去も未来も、
煩いをスッパリ切り捨て、いま、ここに集中する。
これを前後際断(ぜんごさいだん)というそうです。
![D-0609-1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/10/D-0609-11.jpg)
![img_1483407_58696367_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/10/img_1483407_58696367_01-300x276.jpg)
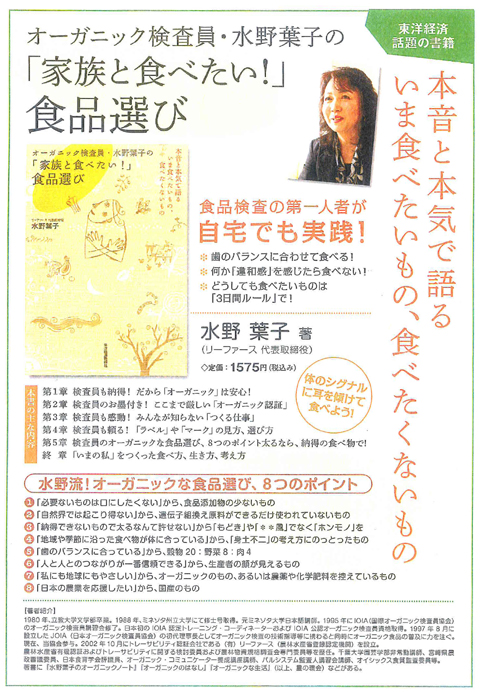
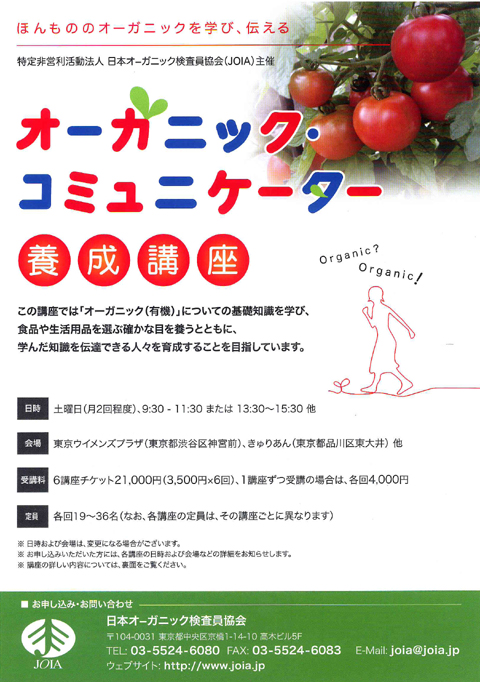
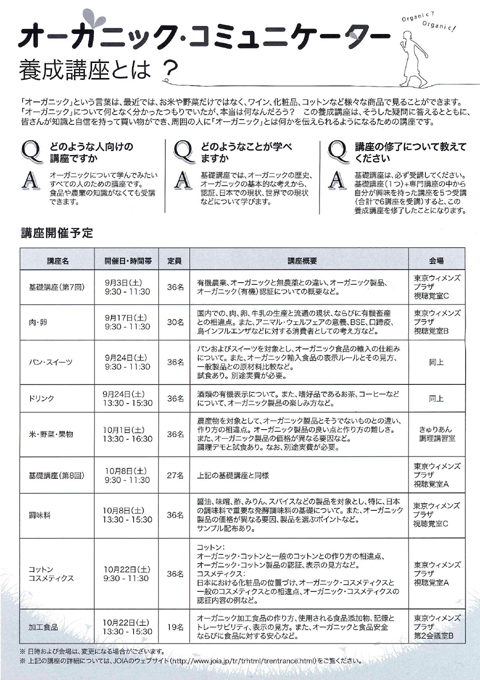
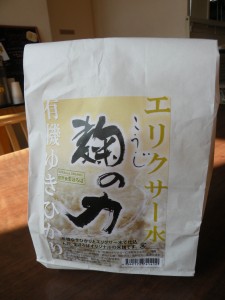
![zenkyousann1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/10/zenkyousann11.jpg) 17歳で養父によって両腕を切断されるも、菩薩行に一身を捧げた尼僧・大石順教氏。
17歳で養父によって両腕を切断されるも、菩薩行に一身を捧げた尼僧・大石順教氏。![humanrights14[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/10/humanrights141.jpg)










![terada-asai-200909[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/10/terada-asai-2009091.jpg)

