「苦しみの日々、哀しみの日々」
火曜日, 10月 22nd, 2013鈴木 秀子(文学博士)
『致知』2013年7月号
連載「人生を照らす言葉」より
![1102984551[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/11029845511.jpg)
詩人・茨木のり子さんの詩に、
「苦しみの日々 哀しみの日々」という作品があります。
分かりやすい詩ですから、そのままご紹介します。
苦しみの日々
哀しみの日々
それはひとを少しは深くするだろう
わずか五ミリぐらいではあろうけれど
さなかには心臓も凍結
息をするのさえ難しいほどだが なんとか通り抜けたとき 初めて気付く
あれは自らを養うに足る時間であったと
少しずつ 少しずつ深くなってゆけば
やがては解るようになるだろう
人の痛みも 柘榴(ざくろ)のような傷口も
わかったとてどうなるものでもないけれど
(わからないよりはいいだろう)
苦しみに負けて
哀しみにひしがれて
とげとげのサボテンと化してしまうのは
ごめんである
受けとめるしかない
折々のちいさな刺(とげ)や 病でさえも
はしゃぎや 浮かれのなかには
自己省察の要素は皆無なのだから
茨木のり子さんは大正十五年、大阪府に生まれました。
上京後、学生として戦中戦後の動乱期を生き抜き、
昭和二十一年に帝国劇場で見たシェークスピアの
『真夏の夜の夢』に影響を受け
劇作家としての道を歩み出します。
その後、多くの詩や脚本、童話、エッセイなどを発表し、
平成十八年に八十歳で亡くなります。
茨木さんの作品はどちらかと言えば反戦色が強く、
過激なものが目立ちますが、
「苦しみの日々 哀しみの日々」はそれとは趣の異なる、
内省的で穏やかな詩の一つです。
おそらく作者自身、いろいろな人生体験を経ていて、
それを克服していく過程でこの詩は生まれたのでしょう。












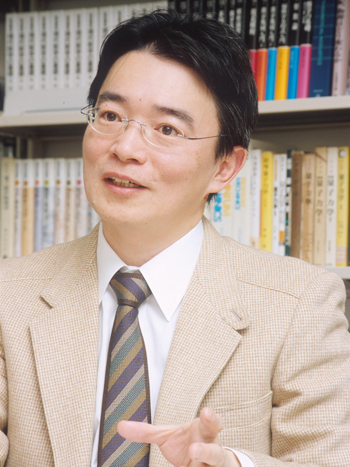



![6549775c6d752afb353ddaacdcde4a706b5deb6a.56.2.9.2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/6549775c6d752afb353ddaacdcde4a706b5deb6a.56.2.9.21.jpg)
![1319440173[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/13194401731.jpg) 安岡先生とドラッカー教授の教えが驚くほど
一致しているのを実感するようになったのは、
『易経』研究の第一人者である竹村亞希子先生に学んでからでした。
竹村先生によれば、
『易経』は時の変化の原理原則を説く書です。
そしてドラッカー教授もその著書において時の変化、
世界の変化を広く記されており、
変化を見る目が人一倍優れていました。
つまり『易経』もドラッカー教授も、
変化、特に兆しを知ることが
重要であるという点で一致しています。
『易経』は東洋思想の中核をなす古典であり、
安岡先生の教えとも深く結びついています。
そこに思い至り、私は安岡先生とドラッカー教授の教えの
共通点について思索を深めてきたのです。
ここで具体的に、安岡先生とドラッカー教授の言葉を通じて、
両者の教えの共通点を見てゆきましょう。
「人々は意識しないけれども、
何か真剣で真実なるものを求めるようになる。
これが良知というもので、
人間である以上誰もが本具するところであります。
致良知とは、その良知を発揮することであり、
それを観念の遊戯ではなくて、
実践するのが知行合一であります」
(安岡正篤『人生と陽明学』)
「自らを成果をあげる存在にできるのは、自らだけである。
(中略)したがってまず果たすべき責任は、
自らのために最高のものを引き出すことである。
人は、自らがもつものでしか仕事はできない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
「知識とは、それ自体が目的ではなく、
行動するための道具である」
(ドラッカー『既に起こった未来』)
両者の著作は膨大ですが、その教えの根本は活学であり、
実践である点で一致しています。
さらに二つの教えは、学びの手法においても共通しています。
「一度古人に師友を求めるならば、
それこそ真に蘇生の思いがするであろう」
(安岡正篤『いかに生くべきか』)
「理論化に入る前に、現実の企業の活動と行動を観察したい」
(ドラッカー『現代の経営(上)』)
ドラッカー教授の本には「IBM物語」「フォード物語」
といった経済人や企業の逸話が随所に盛り込まれています。
彼の著作には机上で生み出されたものは一つもなく、
すべて自らの目で見たものに基づいて記されています。
現実を観察し、一つの理想を提示し、実現を促しました。
これは安岡先生がお示しになる造化の位どり、
つまり理想‐実現‐現実、天‐人‐地の教えに適っています。
それは歴史や人物に学ぶことの大切を説き続けた
安岡先生と共通するスタンスといえるでしょう。
「自分を知り、自分をつくすことほど、
むずかしいことはない。
自分がどういう素質、能力を天賦されているか、
それを称して『命』という。
これを知るのを『知命』という。
知ってこれを完全に発揮してゆくのを『立命』という」
(『安岡正篤一日一言』)
「自らの成長のために最も優先すべきは卓越性の追求である。
そこから充実と自信が生まれる。
能力は、仕事の質を変えるだけでなく
人間そのものを変えるがゆえに重大な意味をもつ。
能力なくしては、優れた仕事はありえず、
自信もありえず、人としての成長もありえない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
安岡先生の説く「知命」「立命」は、
『大学』の「明徳を明らかにする」という言葉にも置き換えられ、
それはドラッカー教授の
「自分の持っているものを発現させる」
「卓越性の追求によって社会の役に立つ」
という言葉によって、より現代人にも
分かりやすい教えに転換されています。
安岡先生とドラッカー教授の教えが驚くほど
一致しているのを実感するようになったのは、
『易経』研究の第一人者である竹村亞希子先生に学んでからでした。
竹村先生によれば、
『易経』は時の変化の原理原則を説く書です。
そしてドラッカー教授もその著書において時の変化、
世界の変化を広く記されており、
変化を見る目が人一倍優れていました。
つまり『易経』もドラッカー教授も、
変化、特に兆しを知ることが
重要であるという点で一致しています。
『易経』は東洋思想の中核をなす古典であり、
安岡先生の教えとも深く結びついています。
そこに思い至り、私は安岡先生とドラッカー教授の教えの
共通点について思索を深めてきたのです。
ここで具体的に、安岡先生とドラッカー教授の言葉を通じて、
両者の教えの共通点を見てゆきましょう。
「人々は意識しないけれども、
何か真剣で真実なるものを求めるようになる。
これが良知というもので、
人間である以上誰もが本具するところであります。
致良知とは、その良知を発揮することであり、
それを観念の遊戯ではなくて、
実践するのが知行合一であります」
(安岡正篤『人生と陽明学』)
「自らを成果をあげる存在にできるのは、自らだけである。
(中略)したがってまず果たすべき責任は、
自らのために最高のものを引き出すことである。
人は、自らがもつものでしか仕事はできない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
「知識とは、それ自体が目的ではなく、
行動するための道具である」
(ドラッカー『既に起こった未来』)
両者の著作は膨大ですが、その教えの根本は活学であり、
実践である点で一致しています。
さらに二つの教えは、学びの手法においても共通しています。
「一度古人に師友を求めるならば、
それこそ真に蘇生の思いがするであろう」
(安岡正篤『いかに生くべきか』)
「理論化に入る前に、現実の企業の活動と行動を観察したい」
(ドラッカー『現代の経営(上)』)
ドラッカー教授の本には「IBM物語」「フォード物語」
といった経済人や企業の逸話が随所に盛り込まれています。
彼の著作には机上で生み出されたものは一つもなく、
すべて自らの目で見たものに基づいて記されています。
現実を観察し、一つの理想を提示し、実現を促しました。
これは安岡先生がお示しになる造化の位どり、
つまり理想‐実現‐現実、天‐人‐地の教えに適っています。
それは歴史や人物に学ぶことの大切を説き続けた
安岡先生と共通するスタンスといえるでしょう。
「自分を知り、自分をつくすことほど、
むずかしいことはない。
自分がどういう素質、能力を天賦されているか、
それを称して『命』という。
これを知るのを『知命』という。
知ってこれを完全に発揮してゆくのを『立命』という」
(『安岡正篤一日一言』)
「自らの成長のために最も優先すべきは卓越性の追求である。
そこから充実と自信が生まれる。
能力は、仕事の質を変えるだけでなく
人間そのものを変えるがゆえに重大な意味をもつ。
能力なくしては、優れた仕事はありえず、
自信もありえず、人としての成長もありえない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
安岡先生の説く「知命」「立命」は、
『大学』の「明徳を明らかにする」という言葉にも置き換えられ、
それはドラッカー教授の
「自分の持っているものを発現させる」
「卓越性の追求によって社会の役に立つ」
という言葉によって、より現代人にも
分かりやすい教えに転換されています。