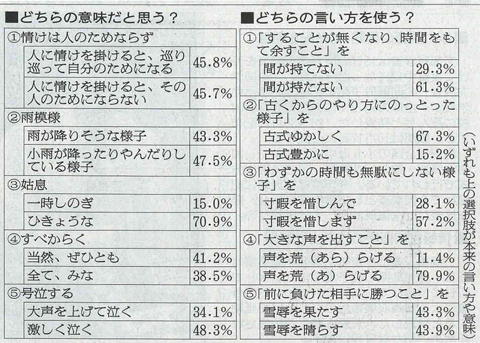川口 由一
(赤目自然農塾 主宰)
生きるのは大変だ。
生きている間は生きなければならないゆえに、本当に大変だ。
生まれてきたすべてのいのち達、生きている間は生きる営み自ずからにして、死にたくないのが基本である。
この基本の営みが、老い、やがて死への営みでもある。
生きること、死ぬことは、自ずから然らしむることであるが、
当人にとっては人生における最大の困難時である。
生まれることなく滅することのない絶対の存在である宇宙に、地球が生まれて47億年。
今日も生き続けている。太陽が誕生して50億年前後だろうか。
今日も生きて営み続けており、その営み自ずからにして、やはりもれることなき死滅への営みである。
不生不滅にして有り続ける宇宙に、人類が誕生して数十万年、数百万年生き続け、
親から子へと巡ること自ずからにして、やはり死滅への営みである。
一人ひとりの百年前後の生きる営みしかり、すべて生まれてきたもの自ずからにして、
生きる営みが成長、成熟、老、死への営みである。
この絶対の定めのなかで、それぞれの生の期間が過不足なく絶妙に定まっており、
それぞれが我がいのちを生きている間は生きている。
人類も与えられた生の期問を生きて全うすること自ずからであるはずだ。
一人ひとりの百年前後もまたしかりであるが、この百年前後の時空間を生きることは本当に難しい。
滅びることなくよくここまで人類は生き続けてきたものだ。
たくさんのたくさんの人が生まれて、生きて死に、生まれて生きて今日に続いている。
人が、地球上の生物が…、地球が、月が、太陽が、星々が、すべての物質が、
生まれ死に、生じ減するこの営みの舞台である宇宙は、
広大無辺の空間であり、無始無終の時代であり、姿形はない。
空間における時間の流れは、すなわちいのちの営みであり、
この営みに目的はない。
地球の、太陽の、星々の、人の、鳥の、、蝶の、花の…、
生滅、生死、いずれも無目的の営みからのものである。
この無目的の宇宙で生き、この混沌混乱の人間社会で生きてゆくことは本当に大変であり難しい。
ゆえに「死にたくない」を生きる営みの根源に抱きながらも、
「生きることから逃避する」「死を好む」「正しいものを好まず誤れるものに心惹かれる」
「生きているいのちを損ね傷つけることを喜ぶ」「生きる舞台である環境を破壊することに積極的になる」
「生きることを放棄して怠惰に親しむ」「死に至る退廃に魂を喜んであずける」…等々の性をも抱く私達人間であり、
数十万年、数百万年の歴史を混沌のなかで生きてきた人類であるが、現代に至るほどに生きることを放棄し、
死臭の発す退廃にとりつかれること顕著となり、死に向かって急いでいる。
今日のこのいのち本来の墓本から外れた生き方にほ、もちろん人類の寿命の全うはなく、
一人ひとりの心身健全にして厳かなる人生の全うもない。
真の幸福も平和もあり得ない。
人としての心豊かな情緒美しい行為行動からの日々の喜びもない。
生きることの意味も意義も悟り知ることなく、他を愛し他の存在を尊び感謝の思いの湧き出ずることもない。
生きることがさらにつらく困難となり、暗闇から抜け出すことができなくなる。
何があっても生きている間は生きなければならない。
生きるに正しい道を得てである。道を得ずして生きることはできない。
人間以外のすべてのいのち達は道からはずれない。
私達人間もいのちある生物として、いのち達の舞台、この宇宙自然界生命界を、損ねることなく、破壊することなく、
また他を侵すことなく、慈悲深い情緒豊かな人間として、心平和に、魂の根源から静かに智恵深く、
足るを知って生きなければならない。
正しいいのちの道、人の道、我が道を得たならば、生きて全うすることが本当に楽しく、生きることの困難はしりぞく。
人類白ら不幸に陥ってはいけない。
いのちを観ることのできない今日の科学文明、自然から大きく遊離した都市文明、
いのちを大切にしない物質文明、生きることの真の意味と意義を見失い消費を盛んとする経済優先の人間社会は、
精神を退廃に蝕ませ生命力を衰退させ、死に向かって突っ走り、死臭を放ちつつ、
なおあらぬものに執着するものだ。
川口 由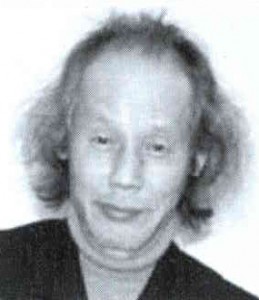 一 (かわぐち よしかず)
一 (かわぐち よしかず)
昭和14年、奈良県桜井市の専業農家に生まれる。慣行農業に23年問従事した後、自然の営みに添った真の生き方を求め、自然農と漢方医学に取り組んで33年となる。現在は自然農と漢方医学を求める人達に応え指導する。赤目自然農塾主宰。主な著書「妙なる畑に立ちて」(野草社)、「自然農から農を超えて」一カタツムリ社一、「自然農という生き方」一共著・大月書店)、「自然農」(共著・晩成書房一、「自然農への道」一編共著・創森社一他。ビデオ「妙なる巡リのなかで」一ナチュラルファーミングプロジエク上他。記録映画「自然農川口由一の世界」一フィオーナ・グループ現代一
![3250104304[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/32501043041.jpg)
![or_110718_shinnittetsu6-thumbnail2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/or_110718_shinnittetsu6-thumbnail211-150x150.jpg)
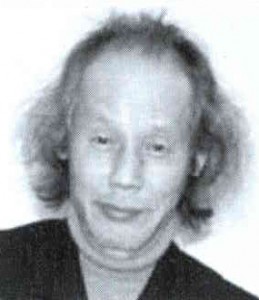
![E-1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/E-11.jpg)


![51SopcWRteL[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/51SopcWRteL1-187x300.jpg)
![seminars_image1_00030273[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/seminars_image1_000302731.jpg)
![img263de6f3zik4zj[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/img263de6f3zik4zj1.jpg)