中村 節子 (看護史研究会会員、藤沢市立看護専門学校元校長)
『致知』2007年6月号
「致知随想」より
────────────────────────────────────
江戸時代後期に、町医・平野重誠(じゅうせい)によって著され、
それまでの看護法を集大成した
日本初の看護書といわれる『病家須知(びょうかすち)』。
貝原益軒の『養生訓』と並ぶ養生書の二大金字塔とされながら、
その存在はほとんど知られていませんでした。
書名が「病人のいる家」+「須く知るべし」
から取られているように、内容は養生の心得に始まり、
療養、介護、助産、さらには医者の選び方や
終末期ケアについてなど多岐に亘ります。
昨年、看護史研究会が発足五十周年を迎えたのを機に
「何か看護学生のために役立つものを」と考え、
本書の現代語訳に取り組むことになりました。
メンバーは二十代から七十代の専門家十数人です。
現代語訳に取りかかる前に、
私はまずこれを書いた平野重誠の人となりを知りたいと思い、
図書館を訪ねてみました。
しかし詳しい資料は見つかりません。
方々を探し回った挙げ句、漢方の専門書に記されてあった
名前だけを頼りに、歴史家の先生方七名に手紙を出しました。
そうして、北里研究所東洋医学総合研究所の
小曽戸洋先生から返信をいただけたことで、
重誠の子孫の方とも連絡を取ることができ、
埋もれていた歴史に一条の光が差し込んできました。
著者・平野重誠の生年は一七九〇年。
幼い頃から父親に医術を学び、
徳川将軍家の主治医だった多紀元簡に師事するなど
大変な秀才でしたが、官職には就かず、
生涯を町医者として過ごしたといいます。
一七一三年、『養生訓』の刊行を機に
健康指南書が相次いで出されたものの、
いつしか「医」は仁術から算術へと堕落し、
人々の間にも健康はお金で買うもの、
といった風潮が広まっていました。
そうした世の流れに抗い、日本人が伝えてきた
日常の心がけを基本に養生や看護の方法をまとめ、
一八三二年に出されたのが『病家須知』でした。
本書が他の養生書と異なるのは、
重誠が実際に現場で行ってきた臨床体験や
自らが試して効果を得たことを
具体的に書き記していることです。
大病後に夜寝つかれない人を眠らせる方法を
挿絵入りで解説したり、産後の寝床の図を示したり……。
医者は病気になった人を治療するのではなく、
病人が回復に向かう過程を手助けしていくのが
本来の役割であること。
そして自分の健康を自ら維持し、
未病で防ぐための養生法に、最も重点が置かれているのです。
結果的にこれが最も医療費を安く済ませる手段に
なるのではないでしょうか。
中でも私が強く衝撃を受けたことが三つありました。
一つは、およそ病気というものは、
皆自分の不摂生や不注意が招くわざわいであること。
二つ目は、摂養を怠らず、
療薬を軽んじてはならないこと。
三つ目は病人の回復は看病人の良し悪しで
大きく変わる――「医者三分、看病七分」の考え方でした。
これは私自身が老輩者を看護したり、
家族の看護に十数年間携ったりした経験からも、
実感としてありました。
これまでの日本の近代看護は、ナイチンゲールをはじめ、
欧米から移入されてきたことから教育が始まっていますが、
『病家須知』の成立はそれから二十年を遡ります。
人間が本来持つ自然治癒力を高め、
それを引き出していくという日本独自の視点や
看護の土壌が存在したのではないか、
というのが私たち研究会の見方でした。
「日本を知ることは江戸を知ることである」と言われますが、
江戸時代と現代とは共通する部分が数多くあります。
重誠は薬の服用について
「薬をみだりに飲んではいけない」、
医者を選ぶ時は
「常に勉強している先生を選ばなければならない」等と
記述していますが、重誠自身がまさに
そのように生きた人でありました。
彼の生きた時代は、ちょうど和蘭から
西洋医学が入ってきた頃でしたが、
重誠は治療の役に立ちそうなことは何でも取り入れ、
普段の治療に役立てています。
その克己的な生き方は、医聖と呼ばれた
ヒポクラテスの「医の倫理」にも通じるものがありますが、
これを言行一致させ、その通りに生きていくのは
並大抵のものではありません。
重誠は自分がした辛い思いを子孫には
させたくないとの考えからか、
孫の代まで医者を継がせることはしませんでした。
『病家須知』には、先に述べた養生の心得などの他に、
健康を保つための食事や病気をした時の食事療法、
子どもを育てる心得、病気が伝染る理由、
消化不良や吐き下し、吐血、ひきつけ、脳梗塞、
動物から咬まれた時、切り傷など、
日常生活で起こり得る病の対応、
婦人病、懐妊時の心得から無事に子どもを産ませることまで、
実に事細かに記されています。
そして片目を失明していたにもかかわらず、
各漢字の横には小さな小さな文字で、
素人にも読めるよう意味振り仮名が打ってありました。
重誠はそんな自身の生き方を
「世話焼き心で、いても立ってもおられない性格」
と自嘲気味に語っていますが、その根本には、
人々を何とかして救いたいという
重誠の迸るような情熱と人間愛とがあったのでしょう。
現代は簡単に自殺をしたり、
人を殺めたりしてしまう時代です。
私は助産師をしていたせいか、
人間は一人ひとりが選ばれて
この世に誕生しているわけですから、
どんなに辛い思いをしても、
人間として生きてこそ価値があると考えます。
子どもたちには、踏まれても踏まれても
強く生きていく雑草のような存在であってほしい。
その逞しい元気な体と心をつくるのは、
やはり大人の責任であると思うのです。
『病家須知』の現代語訳完成は、
皆様の健康づくりのための
一滴の雫のようなものかもしれません。
しかし、それを読んだ人たちがいかに内容を吸収し、
自分の中に広げていってくださるか――。
それが私たちの願いであり、
人々の健康と幸福を心から願った
重誠の切なる祈りではないかと思うのです。


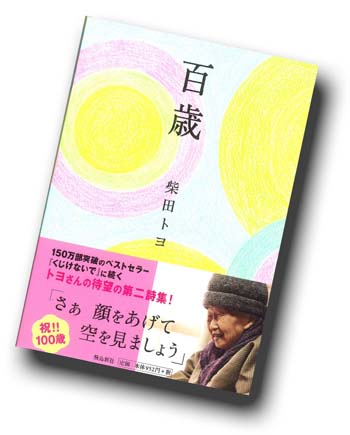
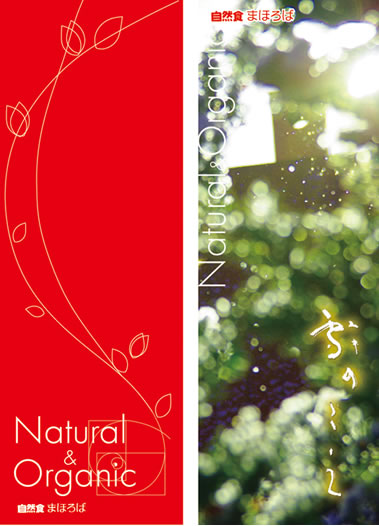
![pana02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/pana021-150x150.jpg)
![h323500pm4_a[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/h323500pm4_a1.jpg)
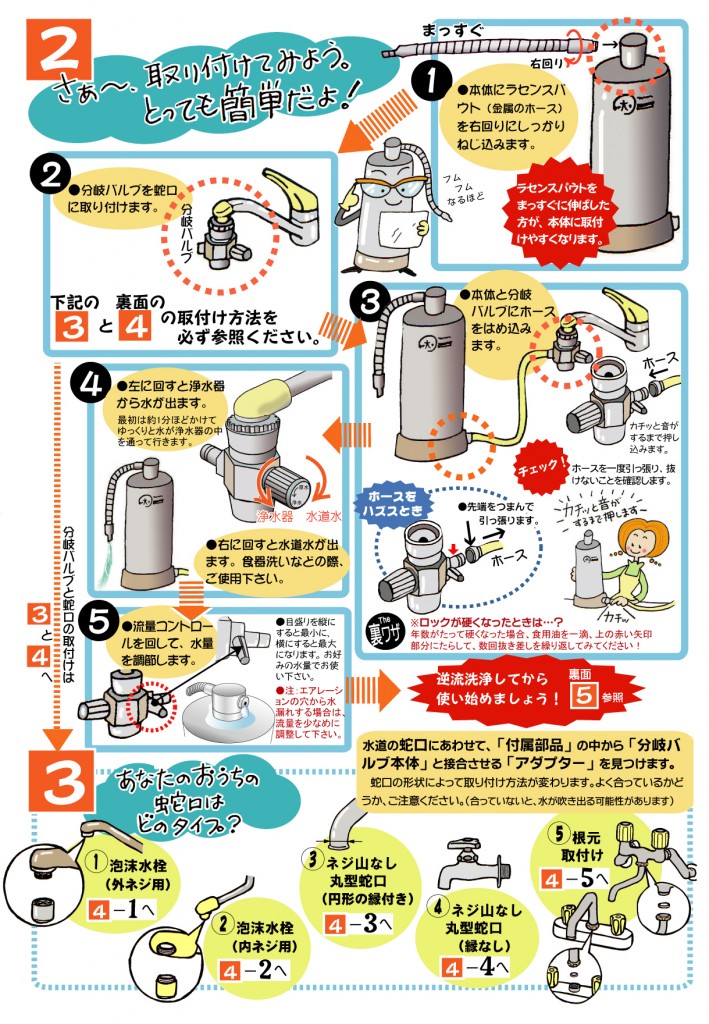
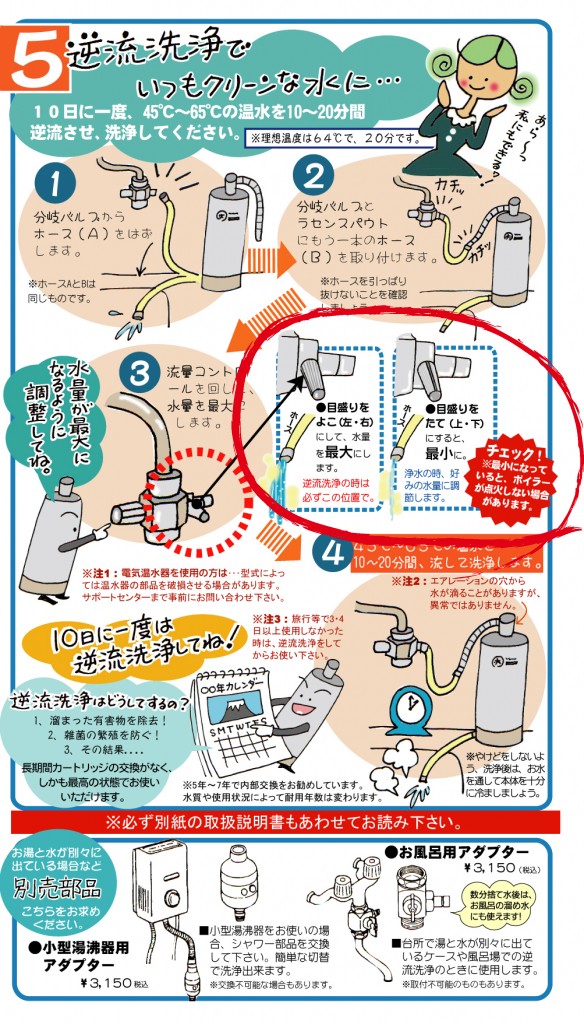

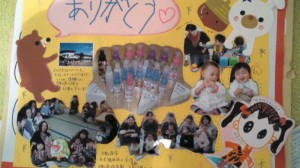
![35[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/351-150x150.jpg)
![shisei-b.ai[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/shisei-b.ai1_.jpg)