若者よ、君たちが生きる今日という日は・・・・・・
水曜日, 8月 15th, 2012![2011103120290955d[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/2011103120290955d1-246x300.jpg) 「若者よ、君たちが生きる今日という日は
「若者よ、君たちが生きる今日という日は
死んだ戦友たちが生きたかった未来だ」
八杉 康夫 (戦艦大和語り部)
『致知』2006年7月号
特集「人学ばざれば道を知らず」より
───────────────────────────────
大和の後部が白煙を上げているのが私にも分かりました。
なおも攻撃が続けられ、
魚雷が的中した時は震度5にも感じられるほど激しく揺れました。
次第に船は傾いていきます。
砲術学校では、戦艦は15度傾いたら限界と習ってきましたが、
25度、30度とどんどん傾いていきます。
それでも、戦闘中は命令がない限り
持ち場を離れることはできません。
その時「総員、最上甲板へ」との命令が出ました。
軍には「逃げる」という言葉はありませんが、
これが事実上「逃げろ」という意味です。
すでに大和は50度ほど傾いていましたが、
この時初めて、「大和は沈没するのか」と思いました。
それまでは本当に「不沈戦艦」だと思っていたのです。
もう海に飛び込むしかない。
そう思った時、衝撃的な光景を目の当たりにしました。
私が仕えていた少尉が日本刀を抜いたかと思うと、
自分の腹を掻っ捌いたのです。
噴き出す鮮血を前に、私は凍り付いてしまいました。
船はますます傾斜がきつくなっていきました。
90度近く傾いた時、私はようやく海へ飛び込みました。
*********************************************
![250px-Explosion_of_the_battleship_Yamato[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/250px-Explosion_of_the_battleship_Yamato1.jpg)
飛び込んだのも束の間、
沈む大和が生み出す渦の中へ巻き込まれてしまいました。
その時、私の頭に過ったのは海軍で教わった
「生きるための数々の方策」です。
海軍に入ってからというもの、
私たちが教わったのは、ひたすら「生きる」ことでした。
海で溺れた時、どうしても苦しかったら水を飲め。
漂流した時は体力を消耗してしまうから泳いではならない……。
陸軍は違ったのかもしれませんが、海軍では
「お国のために死ね、天皇陛下のために死ね」
などと言われたことは一度もありません。
ひたすら「生きること、生き延びること」を教わったのです。
だから、この時も海の渦に巻き込まれた時の対処法を思い返し、
実践しました。
しかし、どんどん巻き込まれ、
あまりの水圧と酸欠で次第に意識が薄れていきます。
その時、ドーンという轟音とともにオレンジ色の閃光が走りました。
戦艦大和が大爆破したのです。
そこで私の記憶はなくなりました。
*********************************************
気づいたら私の体は水面に浮き上がっていました。
幸運にも、爆発の衝撃で水面に押し出されたようです。
しかし、一所懸命泳ぐものの、次第に力尽きてきて、
重油まみれの海水を飲み込んでしまいました。
「助けてくれ!」と叫んだと同時に、
なんともいえない恥ずかしさが込み上げてきました。
この期に及んで情けない、誰にも聞かれてなければいいが……。
![t02200330_0267040011930284627[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/t02200330_026704001193028462711.jpg)
すると、すぐ後ろに川崎勝己高射長がいらっしゃいました。
「軍人らしく黙って死ね」と怒られるのではないか。
そう思って身構える私に、彼は優しい声で
「落ち着いて、いいか、落ち着くんだ」と言って、
自分がつかまっていた丸太を押し出しました。
そして、なおもこう言ったのです。
「もう大丈夫だ。おまえは若いんだから、頑張って生きろ」
4時間に及ぶ地獄の漂流後、駆逐艦が救助を始めると、
川崎高射長はそれに背を向けて、
大和が沈んだ方向へ泳ぎ出しました。
高射長は大和を空から守る最高責任者でした。
大和を守れなかったという思いから、
死を以て責任を取られたのでしょう。
高射長が私にくださったのは、浮きの丸太ではなく、
彼の命そのものだったのです。
(中 略)
昭和60年のことです。
いつもピアノの発表会などでお会いしていた女性から
喫茶店に呼び出されました。
彼女は辺見さんが書かれた『男たちの大和』を取り出し、
こう言ったのです。
「八杉さん、実は川崎勝己は私の父です」
驚いたなんていうものじゃありません。
戦後、何とかしてお墓参りをしたいと思い、
厚生省など方々に問い合わせても何の手がかりもなかったのに、
前から知っていたこの人が高射長のお嬢さんだったなんて……。
念願叶って佐賀にある高射長の墓前に
手を合わせることができましたが、
墓石には「享年31歳」とあり、驚きました。
もっとずっと年上の人だと思い込んでいたからです。
その時私は50歳を超えていましたが、
自分が31歳だった時を思い返すと
ただただ恥ずかしい思いがしました。
そして、不思議なことに、それまでの晴天が
急に曇天となったかと思うと、
突然の雷雨となり、
まるで「17歳のあの日」が巡ってきたかのようでした。
天皇も国家も関係ない、自分の愛する福山を、
そして日本を守ろうと憧れの戦艦大和へ乗った感動。
不沈戦艦といわれた大和の沈没、原爆投下によって被爆者になる、
そして、敗戦。
そのすべてが17歳の時に一気に起こったのです。
17歳といえば、いまの高校2年生にあたります。
最近は学校関係へ講演に行く機会もありますが、
現在の学生の姿を見ると、
明らかに戦後の教育が間違ったと思わざるを得ません。
いや、生徒たちだけではない。
間違った教育を受けた人が先生となり、
親となって、地域社会を動かしているのです。
その元凶は昭和史を学ばないことに
あるような気がしてなりません。
自分の両親、祖父母、曾祖父母が
どれほどの激動の時代を生きてきたかを知らず、
いくら石器時代を学んだところで、
真の日本人にはなれるはずがない。
現に「日本に誇りを持っていますか」と聞くと、
学校の先生ですら「持ってどうするんですか?」と
真顔で聞き返すのですから。
よく「日本は平和ボケ」などと言われますが、
毎日のように親と子が殺し合うこの日本のどこが平和ですか?
確かに昔も殺しはありました。
しかし、「殺してみたかった」などと、
意味もなく殺すことは考えられませんでした。
真の平和とは、歴史から学び、
つくり上げていくほかありません。
鶴を折ったり、徒党を組んでデモをすれば
天から降ってくるものではないのです。
しかし、一流の国立大学の大学院生ですら、
「昭和史は教えてもらっていないので分かりません」
と平気で言います。
ならば自分で学べと私は言いたい。
自分で学び、考えることなしに、
自分の生きる意味が分かるはずがないのです。
人として生きたなら、その証を残さなければなりません。
大きくなくてもいいのです。
小さくても、精一杯生きた証を残してほしい。
戦友たちは若くして戦艦大和と運命をともにしましたが、
いまなお未来へ生きる我々に大きな示唆を与え続けています。
復員後、長く私の中に渦巻いていた
「生き残ってしまった」という罪悪感。
それはいま使命感へと変わりました。
私の一生は私だけの人生ではなく、
生きたくても生きられなかった戦友たちの人生でもあるのです。
うかうかと老年を過ごし、死んでいくわけにはいきません。
未来の日本を託す若者たちが歴史を学び、
真の日本人になってくれるよう私は大和の真実を語り続け、
いつか再び戦友たちに会った時、
「俺も生かされた人生でこれだけ頑張った」と
胸を張りたいと思います。
<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/q8ijMc_Tvdc” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
(八杉氏 講演会)
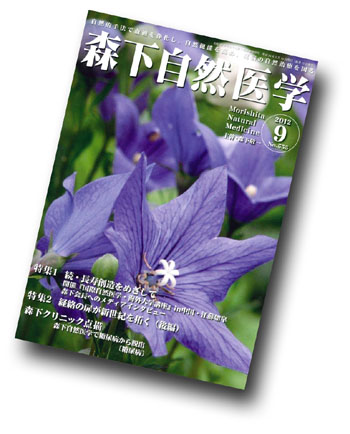
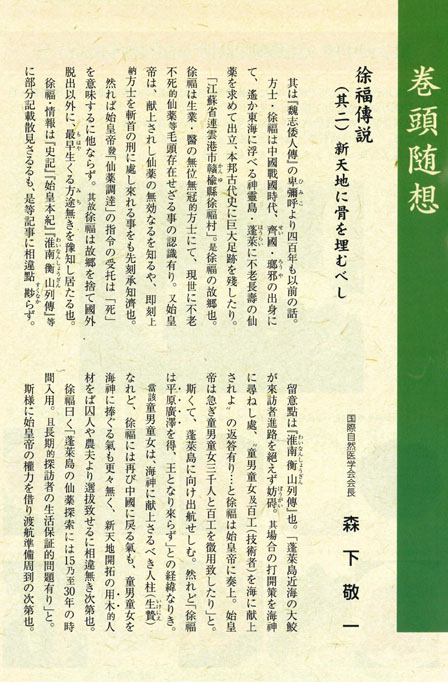
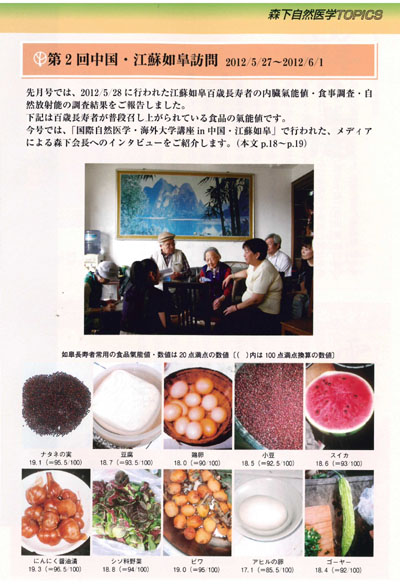
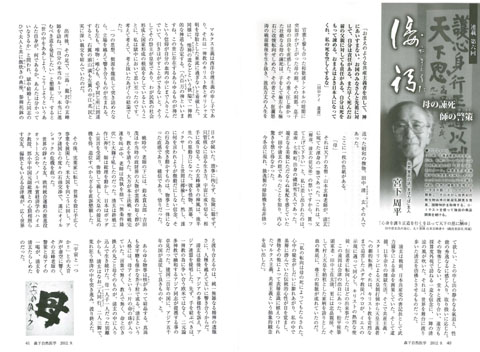
![aitai02_02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/aitai02_021.jpg)
![201111150013-spnavi_2011111500024_thumb[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/201111150013-spnavi_2011111500024_thumb1.jpg)
![090117_toray-hisamitu49[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/090117_toray-hisamitu491.jpg)
![photo_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/photo_11.jpg)
![6t5h7p0000007fca[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/6t5h7p0000007fca11.jpg)
![000043_01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/07/000043_0111.jpg)
![201207001_tsrc_5[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/07/201207001_tsrc_511-150x150.jpg)