「サムライの精神を育てる」
日曜日, 11月 13th, 2011(住宅産業研修財団理事長、大工育成塾塾長)
『致知』2005年9月号より
※肩書きは掲載当時です
────────────────────────────────────
「よく来てくださいました」
大工育成塾スタートから二か月後、
受け入れ先の工務店を訪れて驚きました。
入塾式まで茶髪にピアス、
人の話も聞かずにふんぞり返っていた若者のうちの一人が、
背筋をピンと伸ばし、こう話しかけてきたのです。
「あんた、ずいぶんいい男になったわねぇ」
彼の成長ぶりに目を見張りながら、
私の心は喜びに溢れていました。
真の職人たるもの、卓越した技術とともに、
立派な人格も備えていなければなりません。
棟梁の厳しい指導のもと、日々修業に励んできた成果が
こうした行動に表れたのでしょう。
三年間、棟梁のもとで学ばせ、一人前の大工に育てる――
この「大工育成塾」のアイデアを思いついたのは、数年前のこと。
三十七歳の時、住宅会社を設立した私は、
以来四十年近くにわたり、
「よい住まいとは何か」と自問し続けてきました。
そして折に触れて話してきたのは、
「住まいは、家族の幸せの容れもの」という考え方です。
ところが最近になって人々は、幸せの尺度を、
精神面よりも物質面に求める傾向が強まってきました。
住まいに関していえば、いかに広く、立派な見栄えで、
利便性はどうかといったハード面のことばかり。
つまり、日本人にとっての家は
「ホーム」から「ハウス」へと変容してしまったのです。
一九六〇年代、価格高騰を続ける住宅産業界に
メスを入れるべく、私は米国の2×4(ツーバイフォー)工法を紹介し、
以来、良質で低価格のマイホーム開発の普及に尽力してきました。
そして人々に、価値と価格の見合った住まいを
提供してきたという自負があります。
しかしそれと並行するように、社会では、
家庭内暴力や青少年の非行、離婚率の増加などが
問題視されるようになってきました。
私はその要因の一端が、安価で個室主義的な
建築工法にあるのではと考えました。
これは私自身の自戒と反省でもあります。
中国の孟子の言には
「家に三声あり(三声あれば安泰なり)」
とあります。
三声とは、
一、家族が働いている声や物音。
二、赤ん坊の泣き声。
三、読書の声のこと。
その家族の安泰を築くための住宅環境が、
いまの日本にあるといえるでしょうか。
また、真の日本の住まいとは、どんなものを指すのでしょう。
あるヨーロッパの友人はいいました。
「日本には、千年の風雪にも耐え得る寺社仏閣が数多くある。
これらは世界にも誇れる建築技術です。
日本人はなぜこんな素晴らしいものを忘れてしまったのですか」
考えてみると、昔の日本の住宅には、
襖や障子、引戸など、家族の関係を優しく包む創意工夫が
数多く見られます。
そんな先達の知恵が残る空間には、
孟子のいう「三声」が、ちゃんとあるではありませんか。
ところが、その伝統技術を継承する者の高齢化が進み、
大工の数は二十年間で、約三十万人も減少してしまいました。
そこで、次代を担う立派な職人を育てたいと思い、
大工育成塾をスタートさせたのです。
開塾にあたり、国からは補助金を取り付け、
受け入れ先の工務店を東京・大阪・福岡の三都市で
百以上手配しました(二期目からは名古屋でも開塾)。
職人気質の棟梁のもと、マンツーマンの指導を受けるのは、
生易しいことではありません。
技術的な指導はもちろん、挨拶の仕方や掃除の方法など、
日常の居ずまいを徹底的に鍛え直させられます。
さらに育成塾では、座学の講義も定期的に設けています。
道具の名称に始まり、尺貫法、住まいの歴史、
住宅構造の理論等を通じ、大工の世界を体系的に学ぶことで、
建築に対する理解を深めます。
講師役には、棟梁や大学教授、研究者のほか、
私自身も教壇に立つことがあります。
その際、塾生に向かってよく口にしているのは、
「武士道の精神を持ったサムライたれ」
ということです。
昔のサムライは、すぐれた剣術の腕とともに、
古典や歴史などの教養を幅広く身につけていました。
そして立派な道徳観を持ち、
正道を歩む術を心得ていたといいます。
「職人の精神は、武士道の道徳につながる」
が私の持論ですが、年間百人、十年間で千人のサムライを、
塾を通じて育てたいと考えています。
さて、今年で三期目を迎えた大工育成塾ですが、
入塾面接でこのようにいった子がいました。
「何代にもわたって受け継がれていく住まいづくりでは、
大勢の方を幸せにすることができます。
その家づくりを私はしたいのです」
この若者がいうように、私の考えるよい住まいとは、
そこで健全な人格が形成され、
家族の絆が育まれるような家のことです。
すなわち、家づくりは人づくりにつながるのです。
塾生たちには、サムライの刀を道具に替え、
人の上に立つリーダーとなって、
この国をつくる人間になってほしいと切に願っています。
![matsuda_photo1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/matsuda_photo11.jpg)
![51QOLXpRaqL[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/51QOLXpRaqL1.jpg)
![saku_yasushi[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/saku_yasushi1.jpg)
![img12[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/img121.jpg)
![img_354756_3904293_0[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/img_354756_3904293_01.jpg)
![1717379587[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/17173795871.jpg)
![20111006122458[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/201110061224581.jpg)
![winner_h13_13a[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/winner_h13_13a1.jpg)
![yasu1_img01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/yasu1_img011.jpg)
![s0115l[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/s0115l1.jpg)
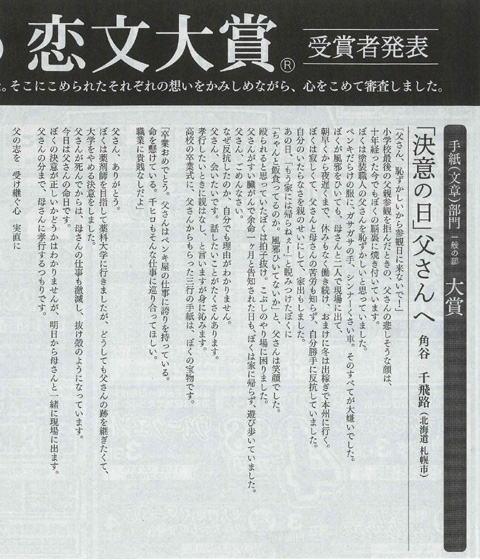
![6120[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/61201.jpg)
![f0121909_11444059[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/f0121909_114440591.jpg)
![12803156190001[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/11/1280315619000111.jpg)