![201105060706436ef[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/201105060706436ef1.jpg) 秋丸 由美子(明月堂教育室長)
秋丸 由美子(明月堂教育室長)
『致知』2007年5月号「致知随想」
※肩書きは『致知』掲載当時のものです
※明月堂は「博多通りもん」で有名な福岡の和菓子店です。
…………………………………………………………………………………………………
■医師からの宣告
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
主人が肝硬変と診断されたのは昭和54年、
結婚して間もなくの頃でした。
「あと10年の命と思ってください」
という医師の言葉は、死の宣告そのものでした。
主人は福岡の菓子会社・明月堂の五男坊で、
営業部長として会社を支えていました。
その面倒見のよさで人々から親しまれ、
たくさんの仕事をこなしていましたが、
無理をして命を落としては、元も子もありません。
私は「まずは身体が大事だから、仕事は二の次にして
細く長く生きようね」と言いました。
しかし主人は「精一杯生きるなら、太く短くていいじゃないか」
と笑って相手にしないのです。
この言葉を聞いて私も覚悟を決めました。
10年という限られた期間、
人の何倍も働いて主人の生きた証を残したいと思った私は、
専業主婦として歩むのをやめ、
会社の事業に積極的に関わっていきました。
30年前といえば、九州の菓子業界全体が
沈滞ムードを脱しきれずにいた時期です。
暖簾と伝統さえ守っていけばいいという考えが
一般的な業界の意識でした。
明月堂も創業時からの主商品であるカステラで
そこそこの利益を上げていましたが、
このままでは将来どうなるか分からないという思いは
常に心のどこかにありました。
そこで私は主人と一緒に関東・関西の菓子業界を行脚し、
商品を見て回ることにしました。
そして愕然としました。
商品にしろ包装紙のデザインにしろ、
九州のそれと比べて大きな開きがあることを思い知らされたのです。
あるお洒落なパッケージに感動し、
うちにも取り入れられないかと
デザイナーの先生にお願いに行った時のことです。
「いくらデザインがよくても、それだけでは売れませんよ。
それに私は心が動かないと仕事をお受けしない主義だから」
と簡単に断られてしまいました。
相手の心を動かすとはどういうことなのだろうか……。
私たちはそのことを考え続ける中で、一つの結論に達しました。
それは、いかに商品が立派でも、
菓子の作り手が人間的に未熟であれば、
真の魅力は生まれないということでした。
人づくりの大切さを痛感したのはこの時です。
■「博多通りもん」の誕生
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
以来、菓子屋を訪問する際には、
売れ筋の商品ばかり見るのではなく、
オーナーさんに直接会ってその考え方に触れることにしました。
しかし、同業者が突然訪ねていって、
胸襟を開いてくれることはまずありません。
行くところ行くところ門前払いの扱いでした。
忘れられないのが、神戸のある洋菓子店に
飛び込んだ時のことです。
そのオーナーさんは忙しい中、一時間ほどを割いて
ご自身の生き方や経営観を話してくださったのです。
誰にも相手にされない状態が長く続いていただけに、
人の温かさが身にしみました。
人の心を動かす、人を育てるとはこういうことなのかと思いました。
いま、私たちの長男がこのオーナーさんのもとで
菓子作りの修業をさせていただいています。
全国行脚を終えた私たちは、社員の人格形成に力を入れる一方、
それまで学んだことを商品開発に生かせないかと
社長や製造部門に提案しました。
そして全社挙げて開発に取り組み、
苦心の末に誕生したのが、「博多通りもん」という商品です。
まったりとしながらも甘さを残さない味が人気を博し、
やがて当社の主力商品となり、いまでは
博多を代表する菓子として定着するまでになっています。
「天の時、地の利、人の和」といいますが、
様々な人の知恵と協力のおかげで
ヒット商品の誕生に結びついたことを思うと、
世の中の不思議を感ぜずにはいられません。
■「父を助けてください」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ところで、余命10年といわれていた主人は
その後も元気で働き続け、私も一安心していました。
しかし平成15年、ついに肝不全で倒れてしまいました。
手術で一命は取り留めたものの、
容態は悪化し昏睡に近い状態に陥ったのです。
知人を通して肝臓移植の話を聞いたのは、そういう時でした。
私の肝臓では適合しないと分かった時、
名乗り出てくれたのは当時21歳の長男でした。
手術には相当の危険と激痛が伴います。
万一の際には、命を捨てる覚悟も必要です。
私ですら尻込みしそうになったこの辛い移植手術を、
長男はまったく躊躇する様子もなく
「僕は大丈夫です。父を助けてください」
と受け入れたのです。
この言葉を聞いて、私は大泣きしました。
手術前、長男はじっと天井を眺めていました。
自分の命を縮めてまでも父親を助けようとする
息子の心に思いを馳せながら、
私は戦場に子どもを送り出すような、
やり場のない気持ちを抑えることができませんでした。
そして幸いにも手術は成功しました。
長男のお腹には、78か所の小さな縫い目ができ、
それを結ぶと、まるで「人」という字のようでした。
長男がお世話になっている
神戸の洋菓子店のオーナーさんが見舞いに来られた時、
手術痕を見ながら
「この人という字に人が寄ってくるよ。
君は生きながらにして仏様を彫ってもらったんだ。
お父さんだけでなく会社と社員と家族を助けた。
この傷は君の勲章だぞ」
とおっしゃいました。
この一言で私はどれだけ救われたことでしょう。
お腹の傷を自慢げに見せる息子を見ながら、
私は「この子は私を超えた」と素直に思いました。
と同時に主人の病気と息子の生き方を通して、
私もまた大きく成長させてもらったと
感謝の思いで一杯になったのです。
![fs_080602_mitsui2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/fs_080602_mitsui212.jpg)


![201105060706436ef[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/201105060706436ef1.jpg)
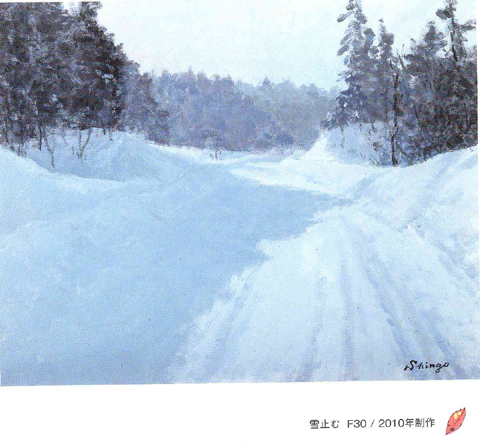
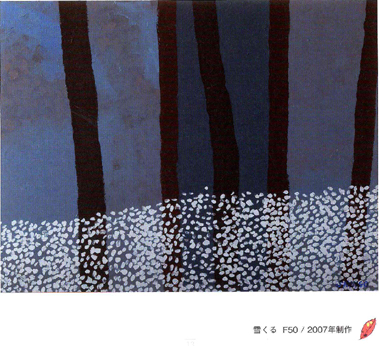
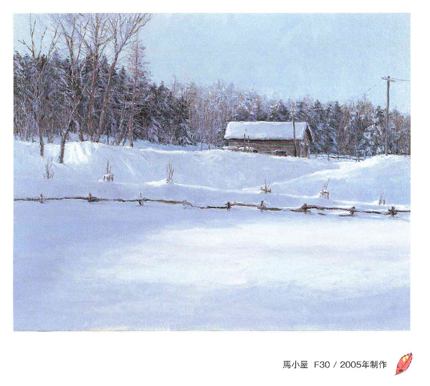
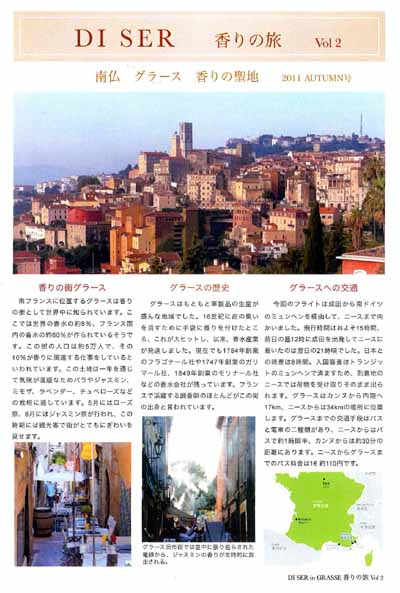

![20060310johnlennon[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/20060310johnlennon11.jpg)
![meisyou12[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/meisyou121.jpg)
![20100611_985637[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/20100611_9856371-300x298.jpg)
![sibelius[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/sibelius1-231x300.jpg)

![kankou2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/kankou21.jpg)
![1109_1c[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/09/1109_1c1-231x300.jpg)