尾角 光美 (おかく・てるみ=一般社団法人リヴオン代表)
『致知』2012年12月号
致知随想より
└─────────────────────────────────┘
私が母を失ったのは九年前、十九歳の時でした。
長年、鬱状態が続いていた母はいつも
「死にたい」と繰り返していました。
「あんたなんか生まれてこなければよかった」と
辛辣な言葉を毎日のように浴びせかけられ、
大切な肉親でありながら、
一緒に暮らすのが辛くてしかたがありませんでした。
それでも母を少しでも喜ばせたいと思い、
浪人生活を送りながら内緒でアルバイトをして貯めたお金で、
母の日にバッグをプレゼントしました。
よもやそれが最後のプレゼントになるとは
思いもよりませんでした。
程なく、経営する会社を倒産させた父が失踪。
経済的にも精神的にも負担が過度に重なった末、
母は私が大学に入る二週間前に自ら命を絶ったのです。
以来、私のカレンダーから母の日はなくなりました。
ところが五年前、母の日というのは、
一九〇八年五月十日に母親を亡くしたアメリカの女の子が、
教会で行われた追悼の集いで白いカーネーションを配り、
亡き母親への想いを伝えたことが始まりだと知りました。
その年は、母の日が始まってからちょうど百周年。
私は、それまで心の奥にしまい込んでいた
母への想いを伝えたいと強く思いました。
そして、同じような想いを抱いている人がいるなら
一緒に想いを伝えたいと考え、
母親を亡くされた方々から手紙を募り、
『百一年目の母の日』という本をつくりました。
マスコミで報道されて話題になり、以来毎年刊行しています。
日本ではこの十五年、毎年三万人以上もの人が
自ら命を絶っています。
東日本大震災でも多くの方が突然の死別を経験されました。
それに伴い、大切な人を失った人びとを精神的、
社会的に支えるグリーフサポートの重要性が高まっています。
大切な人を失った悲しみは、一人ひとり異なります。
私の場合、母に対する感情的なわだかまりや、
拭いがたい孤独感など、様ざまな感情が
心の中で複雑に交錯し苦しめられました。
大学にはなんとか入学したものの、
身体をこわして講義への出席もままならなくなりました。
学業復帰への足がかりをいただいたのは、
親を亡くした子供に奨学金貸与を行っている
あしなが育英会でした。
同会が開催したテロ、戦争、病気などによる
遺児たちへのケアの現場で、
悲しみと悲しみが出合ったところから
希望が生まれるのを目の当たりにしました。
二〇〇六年に自殺対策基本法が制定されて以来、
国内の地方自治体が遺族支援に取り組んできました。
その流れの中で、自治体をはじめ、学校、寺院などでの講演、
研修などで全国から呼ばれるようになりました。
年間三万人以上もの方が自ら命を絶ついま、
自殺の問題は決して他人事ではなく、
自分事として考えていきたい。
そしてこの問題が私たちに問い掛けているのは、
自分たちの生き心地について。この生きづらい社会を、
どうすれば生き心地のよい社会にできるかを
ともに考えていくことが、いまを生きる
私たちの役目だということを体験を交えてお話ししました。
二〇一〇年三月、社会起業家を目指す
若者のためのビジネスプランコンペ「edge2009」での
優秀賞受賞をきっかけに、本格的に社会に
グリーフサポートを根づかせていくために、
確実に遺族にサポートが届く仕組みを考えました。
寺院や葬儀社は必ずご遺族と出会います。
そこで、研修で出会った石川県小松市の僧侶の方と
協力して地域にサポートを産み落とすことを目的とした
グリーフサポート連続講座を開催。僧侶、坊守(僧侶の妻)、
葬儀社、一般市民の方が定員を超えるほど参加されました。
自殺遺族にどんな話をすべきか。実は人を導く
僧侶の方々ですら悩んでいらっしゃるのです。
いま求められるのは、遺族が頼れる人の繋がりやサポートの場です。
講座を通じて、去年の冬にグリーフサポートの団体が
二つ発足しました。
かつてお寺は地域と深く結びついていました。
いま日本にはコンビニの二倍にも当たる
七万以上ものお寺があります。
かつてのような地域との絆を取り戻せれば、
もっと生き心地のよい社会になると考え、
「寺ルネッサンス」と銘打って
小松市以外でも働きかけをしています。
グリーフケアで大切なことは、聴く力です。
聴の字は耳+目+心で成り立っており、
自分のすべての注意力を相手に向けること。
受け身でなく能動的な行為であって、
聴くことを通じて相手の痛みや苦しみを
ジャッジせずに少しでも近づくことが重要です。
もう一つ大切なことは、相手のことを気にかけてあげること。
母を失い、自室に籠もって死を思い詰めていた
私の心に光を灯してくれたのが友人のメールでした。
友人は私をむやみに励ましたりすることなく、
ただ「きょうは食べられた?」「眠れた?」と
毎日声を掛け続けてくれました。
一通のメールでもいい。
誰かが自分のことを気にかけてくれている。
その実感が命を繋ぎ止めてくれるのです。
友人のおかげで、私はその後様ざまなご縁に恵まれ、
グリーフケアというライフワークを見出すことができました。
そしていま、いただいたたくさんのご縁は
亡き母からのギフトとして感謝の念を胸に抱いています。
旗を揚げることで繋がることのできる人がいます。
私は、大切な人の死を経験した人の目に
留まるよう高く旗を揚げ、確かに繋がっていくことで、
その喪失から希望を見いだせる社会を実現していきたいと思います。
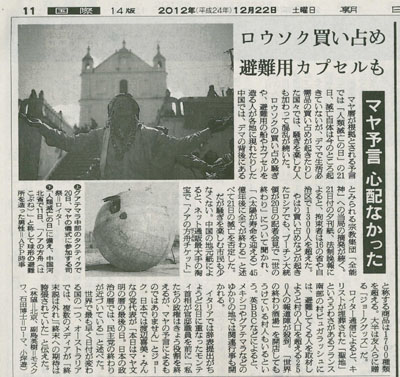










![shoen_machidugi[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/12/shoen_machidugi1.jpg)



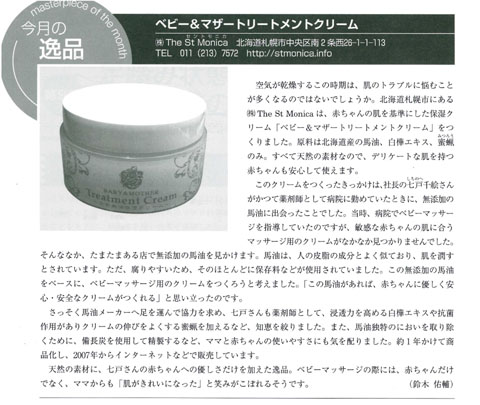

![_IGP0579[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/12/IGP05791.jpg)