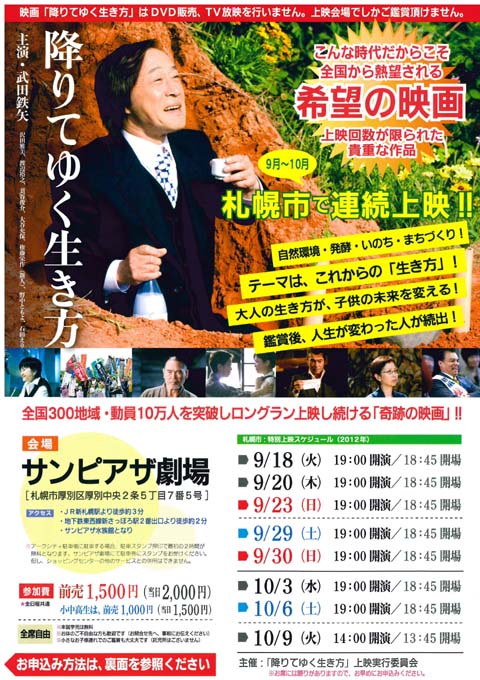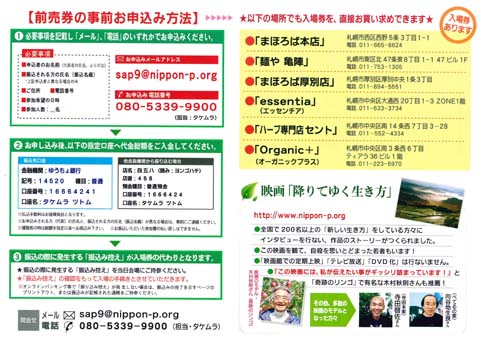![2010_12_24_01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/2010_12_24_011-150x150.jpg) 「どうすれば成功できますか?」
「どうすれば成功できますか?」
浜田 和幸 (国際未来科学研究所代表)
『致知』2004年7月号
特集「熱意・誠意・創意」より
─────────────────────────
1914年12月、エジソンが67歳のときのことです。
災難が彼を襲います。
ウエスト・オレンジにあった研究施設が火事になってしまったのです。
連絡を聞いて駆けつけ、実験道具や資料など重要な物を持ち出そうと
陣頭指揮を執りましたが、時すでに遅し。
施設はすべて焼け落ち、当時の金額で500万ドル近い損害を
被ってしまいました。
目の前で、いままで自分が築いてきたものが
すべて燃える光景を眺めながら、エジソンがしたこと。
それは家族を呼び、こう告げることでした。
「こんなに大きな花火大会はまず見られない。
とにかく楽しめ」
そして集まった記者たちに、
「自分はまだ67歳でしかない。
明日からさっそくゼロからやり直すつもりだ。
いままで以上に立派な研究施設をつくればいいのだ。
意気消沈している暇はない」
と、平然と言ってのけたのです。
エジソンは、常識だけでなく、
時間という概念に縛られることもたいへん嫌っていました。
普通、我々は「1日24時間」という時間の中で生活しています。
しかしエジソンに言わせれば、1日が24時間であるというのは、
人間が人工的につくったもの。
自分が時間の主人公になれば、1日を36時間でも48時間でも、
自分の好きなように使えるはずだ、というのです。
エジソンの工場の壁には、長針も短針もない
大きな時計が掛けられていました。
ある日、友人の自動車王フォードが
「針がなければ、時計の意味がないのでは」
と訊ねると、
「そうじやない。時間というものは、自分でコントロールすべきもの。
時計のような出来合いのバロメーターに左右されているようでは何もできない。
疲れたと思えば、その場で休めばいい。
仕事が完成するまでが昼間だ。
自分の体にあったリズム、
これを自分でコントロールすることが大切だ」
と答えたといいます。
驚異的なひらめきをつかんで形にし、「天才」と賞されることの多い
エジソンですが、決して努力を軽んじていたわけではなく、
むしろその逆でした。
世界中から寄せられる「どうすれば成功できるか」という問いに、
エジソンは、
「野心、
常識にとらわれない創造力、
昼夜を問わず働く意志」
の3要素を挙げています。
1日18時間は働くことにしていたといいますから、
人の2、3倍は濃密な仕事人生を歩んできた自負があったのでしょう。
ですから、エジソンにとっては「まだ67歳」。
まだまだ大きな仕事をするのには十分な時間がある、
という発想だったのです。
それどころか、
「肉体は魂の仮の宿り木。
滅びれば次の宿り先に移動する」
という死生観を持ち、それを証明するための実験を重ねていたくらいですから、
「死」という概念すら超え、次なる成功に野心を燃やしていたのです。
すべての常識を超えて自分で新しい未来を見据え、
創造力を発揮して目の前の「壁」を超える。
天才とはいえ、その裏に、常に前向きに歩みつづけようとする
強い意志とひたむきな努力があったことは、言うまでもないのです。
![staff-naka[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/staff-naka11-150x150.jpg)
![dbec769d1d6c8f53e6f7df873d4e860c[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/09/dbec769d1d6c8f53e6f7df873d4e860c1.jpg)
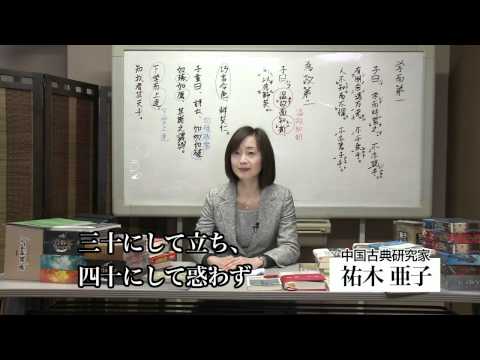
![o051407091279020841278[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/o05140709127902084127811.jpg)


![00636-thumb-208xauto-8493[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/00636-thumb-208xauto-84931.jpg)
![2010_12_24_01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2012/08/2010_12_24_011-150x150.jpg)
.jpg)