「駐在員の三段階」
水曜日, 12月 21st, 2011![8[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/81-150x150.jpg)
桜井 正光 (リコー会長)
『致知』2008年3月号
特集「楽天知命」より
http://www.chichi.co.jp/monthly/200803_pickup.html#pick3
────────────────────────────────────
向こう(イギリス)にいた時に、
これは日本とは違うなと実感する場面に出くわすたびに、
その出来事を二百ページくらいの分厚い手帳に
メモしておいたんです。
そして社長になって自分のホームページに
「世界の中の日本」というページを設けて、
それを順番に紹介したんです。
その中に、「駐在員の三段階」というのがあります。
最初の段階は語学もそんなに流暢ではなくて、
表現力もヒアリング能力もあまりないから、
誰もが相手の話を真剣に聞くんです。
先方も日本人のことをあまり知りませんから同じで、
お互いにそうやって非常に
いいコミュニケーションが取れるんですね。
ところが、いくらコミュニケーションを取っても、
リコーでいうと厚木工場の生産性や品質レベルを
上回るものにはならない。
「いったいどうなってるんだ」
とお互いに相手のせいにし始めるのが第二段階です。
イギリス人というのは出勤率が90%で、
だいたい十人に一人はいつも来ないんです。
それでこちらが
「出勤率が悪いからダメなんだ」
と言えば、彼らは
「日本人はいつも昼間に仕事をしないで、
残業や休日出勤で仕事をする。
我々と一緒になってやってくれない」
と言い返す。お互いに批判し合うんです。
だけどこの批判の時代が案外大事で、
これをやっていると、お互いにいくら批判し合っても
何も生まれないことが分かってくる。
現実を受け入れ、どうすべきかを考え始める。
ここは厚木ではなくイギリスなんだと。
ここでいかに品質を上げ、生産性を上げるかということで、
出勤率90%でも生産性が落ちない方法を考え始めるわけです。
これが第三段階なんです。
経験からすると、一段階、二段階がそれぞれに約一年半。
三年くらいしてようやく建設的、改革的な関係を築けるんです。
だから、駐在員を二段階の誹謗中傷の時代に
日本に戻してしまうと、外国に対して
非常に悪い印象を持って戻ってくるからよくない。
三段階の建設期までいって戻すのが一番いいですね。
![k900688499[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/k9006884991-203x300.jpg)
![083-epictetus-2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/083-epictetus-21.jpg)
![portrait_03-hilty-jung-vekl[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/portrait_03-hilty-jung-vekl1-245x300.jpg)
![100513_01[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/100513_011-150x150.jpg)
![k04_P1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/k04_P11.jpg)
![20051026193409[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/200510261934091.jpg)
![PN2008111501000150.-.-.CI0003[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/PN2008111501000150.-.-.CI00031.jpg)
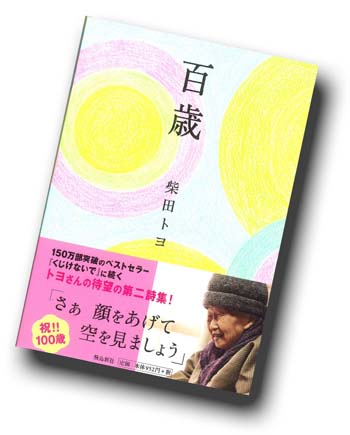
![pana02[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2011/12/pana021-150x150.jpg)