「安岡正篤師とドラッカー氏の共通点(学びの手法編)」
金曜日, 10月 25th, 2013佐藤 等(ナレッジアドバイザー、公認会計士、税理士)
『致知』2013年10月号
特集「一言よく人を生かす」より
└─────────────────────────────────┘
両者の著作は膨大ですが、
その教えの根本は活学であり、実践である点で一致しています。
さらに二つの教えは、学びの手法においても共通しています。
「一度古人に師友を求めるならば、
それこそ真に蘇生の思いがするであろう」
(安岡正篤『いかに生くべきか』)
「理論化に入る前に、
現実の企業の活動と行動を観察したい」
(ドラッカー『現代の経営(上)』)
ドラッカー教授の本には「IBM物語」「フォード物語」
といった経済人や企業の逸話が随所に盛り込まれています。
彼の著作には机上で生み出されたものは一つもなく、
すべて自らの目で見たものに基づいて記されています。
現実を観察し、一つの理想を提示し、実現を促しました。
これは安岡先生がお示しになる造化(ぞうか)の位どり、
つまり理想‐実現‐現実、天‐人‐地の教えに適っています。
それは歴史や人物に学ぶことの大切を説き続けた
安岡先生と共通するスタンスといえるでしょう。
「自分を知り、自分をつくすことほど、むずかしいことはない。
自分がどういう素質、能力を天賦されているか、
それを称して『命』という。
これを知るのを『知命』という。
知ってこれを完全に発揮してゆくのを『立命』という」
(『安岡正篤一日一言』)
「自らの成長のために最も優先すべきは卓越性の追求である。
そこから充実と自信が生まれる。
能力は、仕事の質を変えるだけでなく
人間そのものを変えるがゆえに重大な意味をもつ。
能力なくしては、優れた仕事はありえず、
自信もありえず、人としての成長もありえない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
安岡先生の説く「知命」「立命」は、
『大学』の「明徳を明らかにする」という言葉にも置き換えられ、
それはドラッカー教授の
「自分の持っているものを発現させる」
「卓越性の追求によって社会の役に立つ」
という言葉によって、
より現代人にも分かりやすい教えに転換されています。
![201311pick3[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/201311pick31.jpg)
![0321s[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/0321s1.jpg)
![1102984551[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/11029845511.jpg)
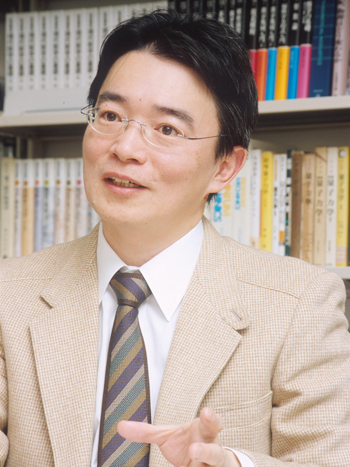

![6549775c6d752afb353ddaacdcde4a706b5deb6a.56.2.9.2[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/6549775c6d752afb353ddaacdcde4a706b5deb6a.56.2.9.21.jpg)
![1319440173[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/13194401731.jpg) 安岡先生とドラッカー教授の教えが驚くほど
一致しているのを実感するようになったのは、
『易経』研究の第一人者である竹村亞希子先生に学んでからでした。
竹村先生によれば、
『易経』は時の変化の原理原則を説く書です。
そしてドラッカー教授もその著書において時の変化、
世界の変化を広く記されており、
変化を見る目が人一倍優れていました。
つまり『易経』もドラッカー教授も、
変化、特に兆しを知ることが
重要であるという点で一致しています。
『易経』は東洋思想の中核をなす古典であり、
安岡先生の教えとも深く結びついています。
そこに思い至り、私は安岡先生とドラッカー教授の教えの
共通点について思索を深めてきたのです。
ここで具体的に、安岡先生とドラッカー教授の言葉を通じて、
両者の教えの共通点を見てゆきましょう。
「人々は意識しないけれども、
何か真剣で真実なるものを求めるようになる。
これが良知というもので、
人間である以上誰もが本具するところであります。
致良知とは、その良知を発揮することであり、
それを観念の遊戯ではなくて、
実践するのが知行合一であります」
(安岡正篤『人生と陽明学』)
「自らを成果をあげる存在にできるのは、自らだけである。
(中略)したがってまず果たすべき責任は、
自らのために最高のものを引き出すことである。
人は、自らがもつものでしか仕事はできない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
「知識とは、それ自体が目的ではなく、
行動するための道具である」
(ドラッカー『既に起こった未来』)
両者の著作は膨大ですが、その教えの根本は活学であり、
実践である点で一致しています。
さらに二つの教えは、学びの手法においても共通しています。
「一度古人に師友を求めるならば、
それこそ真に蘇生の思いがするであろう」
(安岡正篤『いかに生くべきか』)
「理論化に入る前に、現実の企業の活動と行動を観察したい」
(ドラッカー『現代の経営(上)』)
ドラッカー教授の本には「IBM物語」「フォード物語」
といった経済人や企業の逸話が随所に盛り込まれています。
彼の著作には机上で生み出されたものは一つもなく、
すべて自らの目で見たものに基づいて記されています。
現実を観察し、一つの理想を提示し、実現を促しました。
これは安岡先生がお示しになる造化の位どり、
つまり理想‐実現‐現実、天‐人‐地の教えに適っています。
それは歴史や人物に学ぶことの大切を説き続けた
安岡先生と共通するスタンスといえるでしょう。
「自分を知り、自分をつくすことほど、
むずかしいことはない。
自分がどういう素質、能力を天賦されているか、
それを称して『命』という。
これを知るのを『知命』という。
知ってこれを完全に発揮してゆくのを『立命』という」
(『安岡正篤一日一言』)
「自らの成長のために最も優先すべきは卓越性の追求である。
そこから充実と自信が生まれる。
能力は、仕事の質を変えるだけでなく
人間そのものを変えるがゆえに重大な意味をもつ。
能力なくしては、優れた仕事はありえず、
自信もありえず、人としての成長もありえない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
安岡先生の説く「知命」「立命」は、
『大学』の「明徳を明らかにする」という言葉にも置き換えられ、
それはドラッカー教授の
「自分の持っているものを発現させる」
「卓越性の追求によって社会の役に立つ」
という言葉によって、より現代人にも
分かりやすい教えに転換されています。
安岡先生とドラッカー教授の教えが驚くほど
一致しているのを実感するようになったのは、
『易経』研究の第一人者である竹村亞希子先生に学んでからでした。
竹村先生によれば、
『易経』は時の変化の原理原則を説く書です。
そしてドラッカー教授もその著書において時の変化、
世界の変化を広く記されており、
変化を見る目が人一倍優れていました。
つまり『易経』もドラッカー教授も、
変化、特に兆しを知ることが
重要であるという点で一致しています。
『易経』は東洋思想の中核をなす古典であり、
安岡先生の教えとも深く結びついています。
そこに思い至り、私は安岡先生とドラッカー教授の教えの
共通点について思索を深めてきたのです。
ここで具体的に、安岡先生とドラッカー教授の言葉を通じて、
両者の教えの共通点を見てゆきましょう。
「人々は意識しないけれども、
何か真剣で真実なるものを求めるようになる。
これが良知というもので、
人間である以上誰もが本具するところであります。
致良知とは、その良知を発揮することであり、
それを観念の遊戯ではなくて、
実践するのが知行合一であります」
(安岡正篤『人生と陽明学』)
「自らを成果をあげる存在にできるのは、自らだけである。
(中略)したがってまず果たすべき責任は、
自らのために最高のものを引き出すことである。
人は、自らがもつものでしか仕事はできない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
「知識とは、それ自体が目的ではなく、
行動するための道具である」
(ドラッカー『既に起こった未来』)
両者の著作は膨大ですが、その教えの根本は活学であり、
実践である点で一致しています。
さらに二つの教えは、学びの手法においても共通しています。
「一度古人に師友を求めるならば、
それこそ真に蘇生の思いがするであろう」
(安岡正篤『いかに生くべきか』)
「理論化に入る前に、現実の企業の活動と行動を観察したい」
(ドラッカー『現代の経営(上)』)
ドラッカー教授の本には「IBM物語」「フォード物語」
といった経済人や企業の逸話が随所に盛り込まれています。
彼の著作には机上で生み出されたものは一つもなく、
すべて自らの目で見たものに基づいて記されています。
現実を観察し、一つの理想を提示し、実現を促しました。
これは安岡先生がお示しになる造化の位どり、
つまり理想‐実現‐現実、天‐人‐地の教えに適っています。
それは歴史や人物に学ぶことの大切を説き続けた
安岡先生と共通するスタンスといえるでしょう。
「自分を知り、自分をつくすことほど、
むずかしいことはない。
自分がどういう素質、能力を天賦されているか、
それを称して『命』という。
これを知るのを『知命』という。
知ってこれを完全に発揮してゆくのを『立命』という」
(『安岡正篤一日一言』)
「自らの成長のために最も優先すべきは卓越性の追求である。
そこから充実と自信が生まれる。
能力は、仕事の質を変えるだけでなく
人間そのものを変えるがゆえに重大な意味をもつ。
能力なくしては、優れた仕事はありえず、
自信もありえず、人としての成長もありえない」
(ドラッカー『非営利組織の経営』)
安岡先生の説く「知命」「立命」は、
『大学』の「明徳を明らかにする」という言葉にも置き換えられ、
それはドラッカー教授の
「自分の持っているものを発現させる」
「卓越性の追求によって社会の役に立つ」
という言葉によって、より現代人にも
分かりやすい教えに転換されています。![column_206_1[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/column_206_11.jpg) 人生とは不思議なものです。
私は大学卒業後、七年間クビ寸前の
ダメ営業マンをしていました。
ところが、そこから一転して四年連続トップ営業。
2006年に営業サポート・コンサルティング
という会社を立ち上げ、大企業の営業研修や
全国初となる大学での営業の授業を行っています。
まさか自分が他人様に何かを教える立場になるとは、
思ってもみませんでした。
そもそも私が営業の道に進んだのは、
友人の父親が車の営業をしており、
その自由奔放な姿に憧れたことがきっかけでした。
ある時、トヨタに面接を受けに行くと
「月に五台売ってください」。
一方、
「うちは住宅もやっていて、
そっちは四か月に一戸売れればいい」
とのこと。それならできるかもしれない。
そう思い、トヨタホームに入社しました。
ただ、よく考えてみれば、トヨタ車は人気が高く、
店で待っていてもお客様が来てくださるのに対し、
トヨタホームを買いたいというファンは少ない。
大手メーカーがひしめき合う住宅業界にあっては
「○○会社もいいけど、菊原さんが素晴らしい方なので
トヨタホームにします」
と、お客様から思っていただかなければ売れないのです。
しかし、当時の私にそのような人間的魅力はありません。
電話をしても
「ちょうど子供が寝たところになんで電話してくるんだ!」
と怒鳴られ、訪問しても
「資料だったらポストに入れてもらえますか」
と言ってTVドアフォンを切られてしまう。
会社に戻れば「またアポ取れなかったな」と散々叱られる。
半年もゼロで、俺って存在価値あるのかな……。
周りからすべて否定され、
次第に自分で自分を責めるようになってしまいました。
そんな中、私の支えとなっていたのが週末の飲み会でした。
そこに集まるのは、売れない同期や後輩たち。
結果の出ない者同士で酒を飲むことで、
現実から目を逸らし、ストレスを発散していたわけです。
その当時は、朝九時に朝礼が始まり、
毎日夜中の十二時まで帰れない、
まさに地獄のような日々でした。
それに耐え切れずに辞めていく社員も数多くいました。
彼らが手放したお客様をフォローしたり、
大手が相手にしないクレーマーのような
お客様から契約をいただいて、
年間三棟の最低ノルマをどうにか達成する。
そんなギリギリの生活が七年も続き、
気づけば二十九歳になっていました。
それまでは
「別に売れないけど、仲間がいるし、
飲んで忘れてしまえばいいや」
と思っていたものの、三十を目前に控えた頃から
飲み会が徐々に楽しくなくなっていきました。
ある時、いつものように飲んでいると、
「いま確かに楽しいかもしれない。
でも、おまえってダメな人間だよな」
と、もう一人の自分が囁くように感じたのです。
本当は仕事で結果を出したいという思いが、
心の叫びとして聞こえてきたのでしょう。
しかし、七年やってダメな人間が八年目から
爆発するという話は聞いた例がありません。
ちょうどその頃、結婚したこともあり、
家を建てて転職しようと考えました。
せっかく家を建てるのならば、失敗したくない。
そう思い、様々な情報を集めていると、
ある資料が目に飛び込んできました。
「もう少しコンセントを増やしておけばよかった」
「濃い床にしたら傷や埃が目立つ」
等々、そこには実際に家を建てたお客様が
後悔した事例がたくさん載っていたのです。
「これは面白い! きっとお客様にも喜んでいただける」
私はすぐに“お役立ち情報”として、
そのリストをお客様に郵送しました。
するとどうでしょう。
「いくつか見積もりを出したんだけど、
ちょっとよく分からないので相談に乗ってくれませんか」
「とりあえず菊原さんにお願いしますよ」
というお客様が現れたのです。
営業の仕事が面白いと、
心の底から感じられた初めての瞬間でした。
人生とは不思議なものです。
私は大学卒業後、七年間クビ寸前の
ダメ営業マンをしていました。
ところが、そこから一転して四年連続トップ営業。
2006年に営業サポート・コンサルティング
という会社を立ち上げ、大企業の営業研修や
全国初となる大学での営業の授業を行っています。
まさか自分が他人様に何かを教える立場になるとは、
思ってもみませんでした。
そもそも私が営業の道に進んだのは、
友人の父親が車の営業をしており、
その自由奔放な姿に憧れたことがきっかけでした。
ある時、トヨタに面接を受けに行くと
「月に五台売ってください」。
一方、
「うちは住宅もやっていて、
そっちは四か月に一戸売れればいい」
とのこと。それならできるかもしれない。
そう思い、トヨタホームに入社しました。
ただ、よく考えてみれば、トヨタ車は人気が高く、
店で待っていてもお客様が来てくださるのに対し、
トヨタホームを買いたいというファンは少ない。
大手メーカーがひしめき合う住宅業界にあっては
「○○会社もいいけど、菊原さんが素晴らしい方なので
トヨタホームにします」
と、お客様から思っていただかなければ売れないのです。
しかし、当時の私にそのような人間的魅力はありません。
電話をしても
「ちょうど子供が寝たところになんで電話してくるんだ!」
と怒鳴られ、訪問しても
「資料だったらポストに入れてもらえますか」
と言ってTVドアフォンを切られてしまう。
会社に戻れば「またアポ取れなかったな」と散々叱られる。
半年もゼロで、俺って存在価値あるのかな……。
周りからすべて否定され、
次第に自分で自分を責めるようになってしまいました。
そんな中、私の支えとなっていたのが週末の飲み会でした。
そこに集まるのは、売れない同期や後輩たち。
結果の出ない者同士で酒を飲むことで、
現実から目を逸らし、ストレスを発散していたわけです。
その当時は、朝九時に朝礼が始まり、
毎日夜中の十二時まで帰れない、
まさに地獄のような日々でした。
それに耐え切れずに辞めていく社員も数多くいました。
彼らが手放したお客様をフォローしたり、
大手が相手にしないクレーマーのような
お客様から契約をいただいて、
年間三棟の最低ノルマをどうにか達成する。
そんなギリギリの生活が七年も続き、
気づけば二十九歳になっていました。
それまでは
「別に売れないけど、仲間がいるし、
飲んで忘れてしまえばいいや」
と思っていたものの、三十を目前に控えた頃から
飲み会が徐々に楽しくなくなっていきました。
ある時、いつものように飲んでいると、
「いま確かに楽しいかもしれない。
でも、おまえってダメな人間だよな」
と、もう一人の自分が囁くように感じたのです。
本当は仕事で結果を出したいという思いが、
心の叫びとして聞こえてきたのでしょう。
しかし、七年やってダメな人間が八年目から
爆発するという話は聞いた例がありません。
ちょうどその頃、結婚したこともあり、
家を建てて転職しようと考えました。
せっかく家を建てるのならば、失敗したくない。
そう思い、様々な情報を集めていると、
ある資料が目に飛び込んできました。
「もう少しコンセントを増やしておけばよかった」
「濃い床にしたら傷や埃が目立つ」
等々、そこには実際に家を建てたお客様が
後悔した事例がたくさん載っていたのです。
「これは面白い! きっとお客様にも喜んでいただける」
私はすぐに“お役立ち情報”として、
そのリストをお客様に郵送しました。
するとどうでしょう。
「いくつか見積もりを出したんだけど、
ちょっとよく分からないので相談に乗ってくれませんか」
「とりあえず菊原さんにお願いしますよ」
というお客様が現れたのです。
営業の仕事が面白いと、
心の底から感じられた初めての瞬間でした。![l_a5157a68885a7ff1dd44769f3c98e4e673a5a7e8[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/l_a5157a68885a7ff1dd44769f3c98e4e673a5a7e81.jpg)
![r_3761991img20060426172126[1]](https://www.mahoroba-jp.net/newblog/wp-content/uploads/2013/10/r_3761991img200604261721261.jpg)